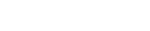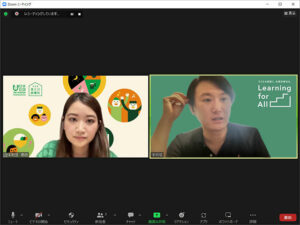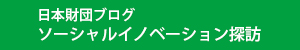ソーシャルイノベーション
Sponsored by 日本財団
日本財団が考える〈ソーシャルイノベーション〉とは、「よりよい社会のために、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実践」のこと。
〈ソーシャルイノベーション〉の実践を通じて、本当の意味での持続可能な「みんながみんなを支える社会」を実現しましょう。
記事一覧
- 全国初”脱”福祉型就労の今までとこれから2024年6月4日
日本財団と社会福祉法人チャレンジドらいふは、障害者の就労支援の一環として、3月15日に「チャレンジドらいふ ソーシャルファーム大崎」の落成式を実施し、植物工場の運営を開始した。
- 18歳意識調査-日本政治は「クリーンでない」9割、「説明責任を果たしていない」8割超の回答結果に2024年5月14日
自民党派閥の政治資金規正法違反事件を受け、日本財団は4月、「政治とカネ」をテーマに63回目の18歳意識調査を実施しその結果を発表しました。
- 岡山・広島・香川・愛媛の4県が「瀬戸内オーシャンズX」トップ会合を初開催2024年5月8日
日本財団は、瀬戸内海の海洋ごみ対策を目的としたプロジェクト「瀬戸内オーシャンズX」の一環として、4県(岡山・広島・香川・愛媛)の知事との会合を初開催した。
- 日本で初めて受刑者に対する VR を活用した就労支援を実施2024年3月19日
日本財団は受刑者等に対する就労支援策として、2024年3月8日(金)にVRを使用した職業体験を実施した。これは同年2月2日(金)に実施したメタバース空間での企業説明会等に続く、矯正施設内でのIT等を活用した画期的な就労支援の取り組みとなる。
- メタバース空間で受刑者・少年院在院者への就労支援を実施2024年2月15日
日本財団は2024年2月2日(金)、受刑者等に対する就労支援策として、日本初となるメタバース空間での企業説明会等を実施した。
- 「自分で決める」を支える社会へ‐日本財団が知的障害者の実態調査を実施2024年1月10日
自らの意思の形成や意思決定そのものに困難が伴う知的障害者の置かれている現状と課題を明らかにし、今後のあるべき意思決定支援を提言しようとするもので、調査の結果をもとに、課題解決に向けた提言を行うことによって、知的障害者一人一人が自らの可能性を生かし、その人らしく暮らすことができるような意思決定の仕組みを構築することを目指して行われました。
- 衣替えや大掃除もサステナブルに‐エコボックスと梱包資材を23自治体へ配布2023年12月1日
日本財団と株式会社メルカリ(以下、メルカリ)は、衣替えや大掃除等により不要品を処分するニーズが高まる年末に向け、「メルカリエコボックス」15,300個とメルカリ取引時の発送に使える「梱包資材」45,900個を全国23の自治体の協力を得て、希望する住民に配布すると発表しました。
- ⼿話学習を手軽に気軽に始められるアプリ「⼿話タウンハンドブック」公開2023年10月11日
⽇本財団は、9⽉23⽇の「⼿話⾔語の国際デー」に合わせて、⼿話学習アプリ「⼿話タウンハンドブック」を9⽉10⽇に公開しました。このアプリは⼿話を検索・練習することのできる簡易辞書で、⽇本財団が主導する「プロジェクト⼿話 […]
- 生成AI、3人に1人は「使ったことがある」-18歳意識調査2023年9月13日
日本財団は8月、ChatGPTなど文章や画像を作ることができる「生成AI」をテーマに 57回目の18歳意識調査を実施しました。対象1000人のうち90%近くが生成AIを「知っている」、40%近くがテキスト生成AIを中心に使用経験がある、と答えているほか、
- 18歳意識調査-8割がマイナンバーカード取得、政府の対応は6割が評価せず2023年8月7日
日本財団は7月、「マイナンバーカード」をテーマに56回目の18歳意識調査を実施し、その結果を発表しました。行政手続きのデジタル化については、全体の60%以上が「進めるべき」と回答、80%近くが「マイナンバーカードを持っている」、あるいは「交付申請中」と答えており、政府が発表した全人口の保有枚数率※より高くなっています。
- 「THE TOKYO TOILET」プロジェクト-2024年度から維持管理は渋谷区へ2023年7月7日
「THE TOKYO TOILET」プロジェクトで整備した公共トイレの、日本財団から渋谷区への譲渡式が6月23日(金)に渋谷区役所で開催されました。
- 4割が「理想の子ども数は2人」、5人に1人は「持ちたくない」と回答-1万人女性意識調査2023年5月30日
日本財団は、少子化対策が大きな問題となる中、日本財団は2023年3月、「少子化と子育て」(少子化を背景とした女性の子育て意識)をテーマに、4回目となる1万人女性意識調査を行いました。
- ヤングケアラーの早期発見・支援提供へ、日本財団と東京都府中市が連携協定を締結2023年5月15日
日本財団は、すべての子どもたちが子どもらしい時間を過ごせる社会の構築を目指し、子どもを支援する多様なプロジェクトを推進しており、その取り組みのひとつである「ヤングケアラーとその家族に対する支援」を加速させるため、東京都府中市と2023年4月から2026年3月まで3年間の連携モデル事業を実施することとなり、4月28日に連携協定締結式が府中市役所にて行われました。
- 雲仙市で初の子ども第三の居場所「メットライフ財団支援 らたん」が開所2023年4月12日
メットライフ生命保険株式会社と日本財団は、2023年3月21日(火)に長崎県雲仙市で「メットライフ財団支援 らたん」の開所式を行いました。これは、子ども第三の居場所として雲仙市で初となるだけでなく、メットライフ財団からの寄付を受けて行う「メットライフ財団×日本財団 高齢者・子どもの豊かな居場所プログラム」で開所する子ども第三の居場所としても第1号施設となります。
- 46.7%が地方議会の役割「知らない」と回答―18歳意識調査2023年3月24日
4月の統一地方選を前に、日本財団は「地方議会」をテーマに55回目の18歳意識調査を実施しました。選挙が予定されている地域に住民票がある18歳以上の若者のうち、選挙があることを認識していたのは約15%、うち8割超が投票する意向を示していますが、単純推計すると実際に投票に行く若者は12%前後に留まる計算になります。
- 「日本の政治に期待」は5人に1人、改善には若手議員の選出が必要―18歳意識調査2023年3月3日
日本財団は1月から2月にかけて、「国会と政治家」をテーマに54回目の18歳意識調査を実施し、政治に対する関心の度合い、国会・国会議員に対する印象や意見を聞きました。
- 日本の脅威、トップは「周辺他国間の戦闘・紛争」―18歳意識調査2023年2月9日
日本財団は1月中旬、「国家安全保障」をテーマに53回目の18歳意識調査を実施し、平和や日本の安全保障政策に対する考え、防衛関連予算の増額などに対する意見を聴きました。
- 「こども家庭庁」創設を考える特別対談―子どもを真ん中においた政策づくりを2022年8月18日
2023年4月に創設されるこども家庭庁では「こどもの居場所づくり指針」の策定を掲げています。新たな組織には、今後どのような役割が求められるのでしょうか。これまで民間の立場から「子ども第三の居場所」事業に取り組んできた、認定NPO法人Learning for All の李炯植(り ひょんしぎ)代表理事と日本財団の経営企画広報部 高田祐莉(たかだ ゆり)さんとの対談をお届けします。
- 「子ども第三の居場所」がもたらす効果について、日本財団が調査を実施2022年5月19日
日本財団は、同財団が全国に展開する「子ども第三の居場所」の効果や支援の内容を把握するため、開所から1年以上経過している32拠点のスタッフ、そこに半年以上通う小学生約300人、その保護者約300人を対象にアンケート調査を実施しました。