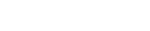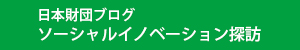ソーシャルイノベーション
Sponsored by 日本財団
日本財団が考える〈ソーシャルイノベーション〉とは、「よりよい社会のために、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実践」のこと。
〈ソーシャルイノベーション〉の実践を通じて、本当の意味での持続可能な「みんながみんなを支える社会」を実現しましょう。
記事一覧
- 里親家庭の支援拡大へ―新たなシンボルマーク登場2018年6月22日
「子どもの家庭養育推進官民協議会」の第3回総会が6月1日、東京・赤坂の日本財団ビルで開かれ、すべての子どもが愛情豊かな家庭で育つ社会の建設に向けた施策や財源措置を政府に求める提言をまとめた。併せて里親家庭を社会で支えるシンボルとして新たに「フォスタリングマーク」を作成、支援の拡大を目指すことになった。
- 熊本地震の復興へ、ネスレ日本と日本財団が農家支援2018年6月8日
熊本地震復興を応援するネスレ日本(神戸市)は5月26日、熊本県南阿蘇村で開かれた「阿蘇ロックフェスティバル2018」の開会式で、4月に発売した「キットカット いきなり団子味」の売上金の一部600万円の贈呈式を行った。日本財団とともに、地元農家らが行う農業支援のための活動を支援する。
- 再犯防止を目指す職親プロジェクト、初の全国幹事会を大阪で開催2018年6月5日
安心・安全な社会や、挫折しても再挑戦ができる社会を実現しようと、少年院や刑務所を出た人の再犯防止計画に取り組む日本財団は5月18日、就労の機会や教育を提供する「日本財団職親プロジェクト」の第1回全国幹事会(仮称)を大阪市内で開催。プロジェクトの目的・目標を再確認するとともに、課題への対応策や職親教育モデルの確立について意見を交換した。
- 難病支援の地域連携ハブ拠点「くるみの森」―富山県高岡市にオープン2018年6月1日
難病の子どもと家族が安心して利用できる地域連携ハブ拠点「くるみの森」が富山県高岡市に完成し、5月6日、開所式が行われた。日本財団が全国で整備しているハブ拠点の18カ所目となる。全国的に不足する小児専門の理学療法士をスタッフに迎え、設備の充実したリハビリルームがあるのが特徴だ。
- 職親プロジェクトにインターンシップ―多摩少年院などモデル矯正施設で実施2018年5月29日
少年院や刑務所を出た人に働く場と住居を提供する「日本財団職親(しょくしん)プロジェクト」の第16回東京連絡会議が4月18日、東京都八王子市の法務省多摩少年院会議室で開かれた。
- 障害者アートなど国内外2000点から選出―渋谷で作品展、6月5日まで2018年5月25日
障害者のアート活動を中心に、多様性の意義と価値を広く伝えるために設立された日本財団DIVERSITY IN THE ARTSは、国内外から公募した2,150点の中から入賞作52点を選んで「日本財団DIVERSITY IN THE ARTS作品展」を東京・渋谷のBunkamura Galleryで23日から6月5日まで開催する。
- アジア太平洋障害者芸術祭(下)障害者・健常者の分け目なくなる2018年5月22日
ダンスカンパニー DAZZLEと障害がある若者7人のダンスチーム BOTANは、この公演のために結成されたダンスチームです。BOTANのメンバーはオーディションで選ばれ、約2カ月半の練習を経て、アジア太平洋障害者芸術祭のオープニングを見事に演じきりました。
- アジア太平洋障害者芸術祭(上)2020年に向け、ひとつになれる場を2018年5月18日
日本財団DIVERSITY IN THE ARTS パフォーミングアーツ・グループの2017年度活動報告会が4月21日、日本財団ビル(東京都港区)で行われ、シンガポールで3月開催されたアジア太平洋障害者芸術祭「True Colours Festival」に出演したアーティストや関係者が出席しました。
- 「学校が嫌だ」と言えるのも挑戦―子どもの才能を潰さない教育を2018年5月15日
「異才発掘プロジェクトROCKET」(以下、ROCKET)の説明会は全国14カ所で行われており、11日に東京・赤坂の日本財団ビルで行われた説明会には100人超の親子連れが参加しました。
- 手話言語法の早期制定を―178自治体が手話言語条例制定2018年5月11日
全都道府県知事が参加する「手話を広める知事の会」の総会が4月25日、東京・永田町の参議院議員会館で開催され、178自治体が4月までに手話言語条例を制定、約100自治体が検討中と全国的な広がりを見せている実態が報告された。
- 熊本城大天守のしゃちほこ2年ぶりに復活!2018年5月8日
日本財団は熊本地震で被災した熊本城の再建支援のため、しゃちほこを復元・制作し、4月28日、地震発生から2年ぶりに大天守に設置した。2016年4月の地震発生直後、同財団は県民の誇りである熊本城の再建資金として約30億円の支援を発表、そのシンボルとしてしゃちほこの復元を進めてきた。
- 分身ロボ「オリヒメ」開発者インタビュー「孤独の解消に人生を賭けようと思った」2018年5月2日
分身ロボ「オリヒメ」を開発したオリィ研究所の吉藤健太朗代表(30)は、東京都三鷹市の閑静な住宅街の一室で働いていた。吉藤代表へのインタビューを通じて、ロボット開発への思いや今後の計画を聞いた。
- 分身ロボ「オリヒメ」、鳥取県米子市の小学校で授業に活用2018年5月1日
鳥取県米子市の市立就将小学校で、教室の授業風景を撮影し、リアルタイムで院内学級の児童にタブレット端末で伝える人型ロボット「OriHime(オリヒメ)」が人気だ。オリヒメを活用している教育現場と、制作しているオリィ研究所から2回に分けて現状を報告する。
- 相次ぐ閉鎖と障害者の大量解雇―A型事業所の在り方を問うフォーラム開催2018年4月27日
相次ぐ閉鎖で障害者の大量解雇が続く就労継続支援A型事業所問題を考えるフォーラム「A型せとうちサミットin倉敷」が3月18日、岡山県倉敷市で開催された。厚生労働省の調査ではA型事業所の70%以上が事業収益だけでは賃金を賄えない状況にあり、相次ぐ閉鎖を前にA型事業所の在り方があらためて問われる事態となった。
- 福島市に「パンダハウス」開所、難病の子どもと家族を支える地域連携ハブ拠点に2018年4月24日
21日、日本財団は「日本財団難病の子どもと家族を支えるプログラム」の一環として、入院中の子どもに付き添う家族が休息(宿泊)でき、さらに退院後も地域で安心して生活するための相談ができる拠点「パンダハウス」の開所式を行いました。
- 難病の子どもと家族を支える地域連携ハブ拠点、茨城県古河市にオープン2018年4月20日
日本財団は全国で25万人以上といわれる難病の子どもと、その家族が孤立しない地域づくりを目指し、「難病の子どもと家族を支える地域連携ハブ拠点」を推進中。その15カ所目にあたる茨城県古河市の日中お預かり施設「Burano」(ブラーノ)で4月1日、開所式が行われた。
- 「夢の奨学金」3期生に奨学生認定証―「情熱を持てば困難は乗り越えられる」2018年4月17日
様々な事情から児童養護施設などで育った社会的養護出身者の進学・就職を支援している日本財団は、「夢の奨学金」3期生17人を選抜し3月30日、東京・赤坂の日本財団ビルで奨学生認定証の授与式を行った。
- 九州北部豪雨で得た経験踏まえ、重機運用合同研修会を開催2018年4月13日
大規模災害時の支援活動に備えた「重機運用合同研修会」が3月15日~30日にかけ、九州北部豪雨で甚大な被害を受けた福岡県朝倉市の杷木寒水(そうず)地区で実施された。いざという時に被災地で重機の強みを有効に発揮できるよう操作・走行技術の向上を目指した。
- 平昌パラリンピック―挑戦する闘志、あきらめない心で獲得した10個のメダル2018年4月10日
平昌冬季パラリンピックのメダリスト4選手が20日、日本財団パラリンピックサポートセンター(パラサポ)が主催し、東京・赤坂の日本財団ビルで開かれた「メダリスト凱旋トークショー」に出席した。
- 京都錦市場「斗米庵」―食文化体験施設が4月7日開設2018年4月6日
この度、京都錦市場商店街振興組合、日本財団、およびNPO法人京都文化協会は、祇園さゝ木(主人 佐々木浩)の協力を得て、錦市場内に新たな食文化体験を可能にし、地域の福祉と食文化をつなぐ新しい施設「斗米庵」を開設することとなりました。