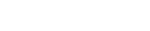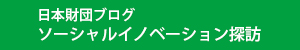ソーシャルイノベーション
Sponsored by 日本財団
日本財団が考える〈ソーシャルイノベーション〉とは、「よりよい社会のために、新しい仕組みを生み出し、変化を引き起こす、そのアイデアと実践」のこと。
〈ソーシャルイノベーション〉の実践を通じて、本当の意味での持続可能な「みんながみんなを支える社会」を実現しましょう。
記事一覧
- 福祉と出会い、社会を良くしていく一歩を―大阪で就職フェア開催2017年4月7日
社会福祉事業に従事する人材の発掘や採用、育成に取り組む一般社団法人「FACE to FUKUSHI」(大阪市北区)は3月20日、来春卒業予定の学生たちに向けた「2018新卒向け福祉就職フェア」を同市で開きました。全国各地の福祉法人を紹介する珍しい催しです。
- 4月4日は「よーしの日」、養子の日キャンペーンに川嶋あいさん登壇2017年4月4日
2日、東京都港区の日本財団ビルで、養子の日キャンペーン「よーしの日2017」が開催されました。冒頭の「特別養子縁組に関するトーク&ライブ」には、自身も特別養子縁組の家庭で育った経験を持つシンガーソングライター川嶋あいさんが登壇しました。
- 「認知症地域ネットワークフォーラム」横浜で開催2017年4月3日
認知症患者と家族・住民がタスキをつなぎ、日本を走って縦断するプロジェクト「RUN伴」を開催している「認知症フレンドシップクラブ」は3月19日、横浜市内で「認知症地域ネットワークフォーラム2016関東 in YOKOHAMA」を開きました。
- J.P.モルガン、日本財団を通じてArrow Arrow「ママインターン」を支援2017年3月29日
東京・丸の内で22日、「ママインターン」の事業報告会が開催されました。本事業は結婚や出産、介護等で離職した女性の再就職を支援するもので、講座には100人が参加し、うち66人がインターンを実施、その後32人が実際の社員採用に至っています。
- 家族それぞれの自立をめざして~親あるうちに~2017年3月28日
公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会は3月3日、東京都内で「みんなねっとフォーラム2016」を開催しました。「家族それぞれの自立をめざして~親あるうちに~」を掲げて、精神障害者と家族についての理解と啓発を進めるための講演とシンポジウムを実施し、約560人の参加がありました。
- 犯罪被害者の子どもたちへの奨学金、4月1日から給付型に2017年3月24日
振り込め詐欺などで発生する預保納付金を活用して、日本財団が担い手として実施している貸与型の奨学金事業「まごころ奨学金」が、4月1日から給付型に切り替わります。同事業を推進する日本財団ソーシャルイノベーション本部の芳川龍郎チームリーダーにお話をうかがいました。
- 「ゆいごんは 最後に書ける ラブレター」-ゆいごん大賞受賞作決まる2017年3月21日
毎年1月5日を「遺言の日」と制定した日本財団は、それを記念して川柳、手紙(400字以内)、つぶやき(140字以内)の3部門で「書こうよ、ゆいごんキャンペーン」を展開してきました。応募作品を審査した結果、大賞には川柳の作品「ゆいごんは 最後に書ける ラブレター」が選ばれました。
- 「E’s CAFE」東京・多摩市に開店-日本初の障害者就労支援スポーツバー2017年3月17日
一般社団法人 パラSCエスペランサ(川崎市幸区、神一世子代表理事)は2017年3月1日、日本初の障害者就労支援のカフェ&スポーツダイニングバー「E’s CAFE(イ一ズカフェ)」を、東京都多摩市落合のニューシティ多摩センタービル8階に開店させました。
- ものをつくる人生にリタイアなんてない!神戸パンじぃ6人衆、東京に2017年3月14日
シニアの本当の姿を知ってもらおうという「ライフ イズ クリエイティブ展」が神戸で開催されてから2年。今回初めて東京に進出し、2月3日から12日まで千代田区外神田のアーツ千代田3331で開かれました。
- 小学生が自分たちの地域を取材―「うみやまかわ新聞2016年度版」完成2017年3月10日
海と島でできた日本を、全国の子どもたちが、新聞づくりを通して学ぶ「うみやまかわ新聞2016年度版」が完成し2月19日(日)、東京都内で展示・発表会が開催されました。本年度は全国14カ所で、小学校の総合学習や地域の課外活動として、うみやまかわ新聞づくりが実施されました。
- 青パト出発式、一宮市で開催―地域の自主防犯活動に2017年3月7日
地域の防犯活動に使用する青色回転灯装備車(通称:青パト)の出発式が2月18日、愛知県一宮市立瀬部小学校で盛大に開催されました。登下校時の子どもの見守りや犯罪防止、そしてまちづくりにも役立ててほしいとの願いを込めて、日本財団が全国で展開している青パト購入のための助成事業の一環です。
- 女川町への巡検(後編)―語り部の言葉に触れ、「人に会う」大切さを学ぶ2017年3月2日
防災と海洋教育について学ぶべく、宮城県・女川町を巡検に訪れた学校の先生たち。そこで得た学びと変化について、前編に続いて川路美沙氏にお話をうかがいました。
- 女川町への巡検(前編)―防災の視点から海洋教育を考える2017年2月28日
14日に公表された「学習指導要領」の改定案に「防災」と「海洋」に関する記述が加わる見通しですが、学校の先生は、この課題にどのように向き合うべきなのでしょうか。東京都教育委員会の管理職候補者生として日本財団で研修中の川路美沙氏に、海洋教育についてお話をうかがいました。
- 英国の里親支援プログラム研修―子どもとのより良い関係に向けて2017年2月27日
英国で開発された里親支援のためのプログラム「フォスタリングチェンジ・プログラム」を促進するファシリテーターを養成するための研修会が2月20日から5日間の予定で、東京・赤坂の日本財団ビルで開催されています。プログラムを里親と子どものより良い関係作りに役立てるのが狙い。
- 日中友好と中国の公衆衛生・医療技術の向上に向け、高度の医学交流へ衣替え2017年2月22日
日中友好と中国の公衆衛生、医療技術の向上を目指す「日中笹川医学協力プロジェクト」の第5次制度がまとまり2月17日、北京の人民大会堂で中国国家衛生・計画生育委員会、日本財団、日中医学協会の間で調印式が行われました。
- ミャンマーの子どもたちに健康な歯を―歯科医師たちのボランティアツアー2017年2月10日
1月下旬、日本財団TOOTH FAIRYプロジェクトに協力する歯科医師たちのミャンマー・ボランティアツアーが行われました。5回目の今年は、これまでの北東部シャン州から南西部イラワジ地区に場所を移して実施しました。
- ALSなど難病患者の意思伝達を考える―コミュニケーション支援体制とは2017年2月7日
筋萎縮性側索硬化症(ALS)など神経系難病患者のコミュニケーション支援体制の構築を目指して一般社団法人日本ALS協会(本部・東京、岡部宏生会長)は1月29日、東京・丸の内で、シンポジウムを開きました。可能な限り最良の意思伝達方法と手段の提供を目指す日本財団助成事業の一環です。
- 障害者トップアスリートに歯科支援―TOOTH FAIRYプロジェクト2017年1月27日
障害者トップアスリートへの歯科支援事業を推進している日本財団は東京歯科大学の協力を得て1月20日、東京都内で日本障害者カヌー協会の選手らにスポーツ歯科についての講話やマウスガード作成の支援を実施しました。歯科医師による社会貢献活動「TOOTH FAIRY」プロジェクトの一環です。
- 災害時要配慮者の命と暮らしを守る(下)日常の見守り必要―別府市2017年1月24日
避難訓練を行ったその自治会は380世帯ぐらいのところでした。訓練が目的ではなくて、その先も自分たちでちゃんとやっていく、ということを地域の人たちがおっしゃってくださったのが、すごくうれしかったですね。
- 災害時要配慮者の命と暮らしを守る(上)現場経験から学ぶ―別府市2017年1月20日
日本財団は昨年12月、大分県別府市で大規模広域災害の発生を想定した「被災者支援拠点」の運営訓練を実施しました。この訓練の指導に当たっていたのが別府市企画部危機管理課の村野淳子さんです。村野さんから防災の現状や課題、今後の目標について聞きました。