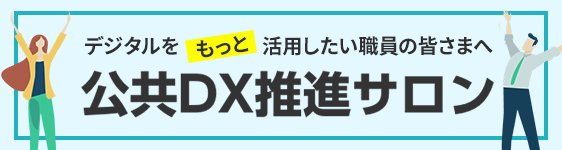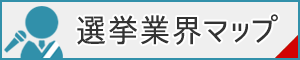平昌パラリンピック支えたボランティア―2020東京へ、聞き取り調査実施 (2018/3/23 日本財団)
「2020年東京に役立てたい」
「アニョンハセヨー(こんにちは)」
あるいは、江原道を起源とされる朝鮮民謡アリランから取った符牒の「アリ、アリ、アリ」という言葉が、笑顔とともに会場に入る見物客を迎えてくれる。そろいのグレーと薄い赤を基調としたユニホーム姿のボランティアたちの屈託のなさがうれしい。凍てつくような寒さを忘れさせてくれる。
彼、彼女らボランティアたちは、なぜ活動に応募したのか。実際の活動現場に立つために、どのような訓練をうけてきたのか。
日本財団ボランティアサポートセンター(通称・ボラサポ)では、2月のオリンピック期間中に数多くのボランティアから聞き取り調査を実施した。そして3月のパラリンピックでも引き続き、渡邉一利理事長(笹川スポーツ財団理事長)以下8人のスタッフが現地入り。オリンピックから継続的に活動している人、パラリンピックだけ参加した人などを対象に聞き取り調査を行った。

アルペンスキー会場で観客を迎えるボランティアたち
「調査内容はメンバー同士のコミュニケーションの取り方や問題が起きたときの対処方法。研修はあったのか、なかったのか。あったとすればどんな内容だったのか。ボランティアマネージメントがよかったのか、改善すべき点はあるのかなど多岐にわたります」
ボラサポの沢渡一登事務局長は調査内容についてそう語る。
オリンピックから引き続き活動している人については「気持ちの変化」や「オリンピック時の経験が活かせているか」。パラリンピックだけの参加者には「応募動機」や「日常的な障害者との関わり」、「実際に活動してみて気持ちの変化があったかどうか」など、スタッフができるだけ多くの人たちに直接取材していった。

聞き取り調査に向かうボラサポのスタッフ
なぜ、こうした調査を実施したのか。沢渡事務局長はいう。
「われわれはいま2020年に向けて、ボランティア育成のための研修プログラムを開発しています。事前研修ではどのようなことが必要とされるのか。また、平昌大会での活動実態を東京大会にどう活かしていくのか。結果を分析、報告、提言していきます」
事務局ではさっそく集計を進め、まとまったところで分析作業を行い、6月上旬にも報告を兼ねたシンポジウムを企画している。現地調査にはボラサポ参与で、まちづくりやボランティア活動などを研究テーマとする文教大学人間科学部の二宮雅也准教授も加わり、インタビューを実施した。江陵のオリンピックパークからほど近い、広報体験センターで行われた内容を紹介しよう。

笑顔で答えるクオンさん
インタビューの対象であるクオン・ヒョンムさんは1995年7月生まれの22歳、大田広域市の国立忠南大学4年生。先天的に「足の筋肉に力がいかない」ため、車いすが手放せない。それでも「自分は人の助けを借りて日々の生活を送っているが、常々、だれかのために役に立ちたいと思ってきた。オリンピック、パラリンピックのボランティア募集を目にしたとき、自分の思いが実現できる機会だと思った」と応募動機を語る。
ちなみにオリンピックとパラリンピックを合わせたボランティアの数はのべ2万人。正確に言えば、オリンピックが1万4161人でパラリンピックは5822人。うち、オリンピックとパラリンピックの両方で活動を継続した人は4724人。つまり、パラリンピックだけというのは1098人である。クオンさんは両方で活動した4724人のなかの1人であり、のべ2万人のなかでおよそ60人と数少ない「障害のあるボランティア」の1人でもある。
クオンさんの役割は広報体験センターを訪れる人たちにオリンピック、パラリンピックに関する展示物や4D映像の説明。ときには観光案内もかってでる。勤務は1日6時間から7時間、午前と午後の2交代制だ。
住まいのある大田から江陵は遠く離れているため、期間中は江陵市内の借り上げ宿舎で暮らす。「車いすで生活できるよう、(組織委員会が)フラットな宿舎を用意してくれたし、移動の車両も配慮してくれた」
ボランティア活動に向けたトレーニングは昨年4月から7月まで、10時間から20時間の研修をうけた。11月から1月まで月1度の現場教育を含む実践研修に参加した。一方、オリンピック、パラリンピックに関する知識はガイドブックによる簡単な文書を読んだ程度だという。
そのクオンさんに、二宮准教授は例えばこう問いかけた。
――障害のある方のボランティアは少ないが、活動にあたって特別な待遇はないのか?
「障害のある人には、動きやすいようにしてあげなければいけない。そんな配慮があれば、もっと参加する人は増えたと思う」
――このボランティア体験を将来にどうつなげようと考えているのか?
「大会が終わったあと、デンマークに行っていろいろ学んでくるつもりだ。北欧はボランティア活動に理解があり、いろいろな国の人と接し、その国のことも理解していくことは、自分の将来に役立つと思う」
――東京のボランティアにアドバイスを
「国家的なイベント、プログラムでボランティアとして手助けとなれるという誇りをもって行動してほしい」

二宮准教授のインタビューをうけるクオンさん
インタビューを終えて、二宮准教授はこう話した。「彼はほんとうに意識が高い。自分の役割をよく理解しているし、障害のある人が活動に関わるには周囲の理解が重要であるとの認識を持っている。将来に向けた展望もしっかりしている。しかし、彼のような人は少ないのではないか。この大会は大学生のボランティアが多いものの、自分の成績のためとか、ただキャリアアップの機会と捉えていたりする。参加することはいいことだが、ただ功利的な目的ではなく、もう少し意識を高く持ってほしい。それが共生社会、多様化社会の実現にもつながるのだから…」
二宮准教授が指摘するように、平昌大会では大学生が多く、8割以上を占めた。これは組織委員会が全国の大学に動員をかけ、出席扱いや単位として認定など特典を与え、就職難の韓国にあって「大きなキャリアとなる」という認識が広がったためとみられる。
東京では恐らく、平昌よりも大学生の比率は下がるとみられる。市民ボランティアに参加する人が多く、企業も処遇を含めて検討を始めたところも少なくない。とはいえ、若い大学生が国際イベントで体験することは重要であり、組織委員会としても活動の担い手としての期待は大きい。出席換算や単位認定などの措置、加えて全国から集まってきた学生の宿舎問題など解決する課題も少なくない。
また女性のボランティアが目立つ大会でもあった。ちなみに男女比はボランティア総数1万5259中、女性が1万627人に対し、男性は4632人に過ぎない。とくに現場では女性の比率が高く、男性は「後方部隊にまわっているか、チームリーダー的な役割ではないか」との認識がなされていた。
こうしたボランティアに対し、語学力不足を指摘する声も少なくない。韓国は日本よりも英語教育が進んでいると見られていたが、実際、英語が通じない場面にしばしばであった。英語表記による案内も少なく、身振り手振りの海外からの観戦客もみかけた。
また、大学生ボランティアは親切に話しかけてくるものの、基礎知識が不足。出入り口がわからなかったり、バスの発着について誤った情報で接し困惑させることもあった。
「ミーティングもすべて韓国語なんです。渡される資料も韓国語で書かれていて、慣れないうちは戸惑うことが少なくなかった」
そう話したのは上智大学外国語学部4年生の齋藤毬子さん。オリンピックから引き続いてパラリンピックでも国際ボランティアとして英語、日本語の通訳に活躍した。その齋藤さんによれば、研修はわずか数時間。「会場をまわって、どこに何があるか教わる程度で、問題が起きたときの対処方などは教えてもらっていない」という。
この点について、沢渡事務局長はこう指摘した。「恐らく研修はされておらず、臨機応変というか、個人の資質に任されている部分はありますね。東京に向けて、こうした点はきちんと対処していく必要があります」

二宮准教授と齋藤毬子さん(江陵のアイスホッケー競技会場前で)
高速鉄道の平昌オリンピックパーク最寄りの珍富(ジンム)駅や、高速バスのターミナルである横渓(ヘンゲ)にはそろいの赤いコートを着た通訳ボランティアがいた。ここでは比較的年齢の高い人たちが多く、海外からの観戦客の道案内に従事していた。
珍富で日本語案内を務めていたヨン・ソンホさんは70歳。覚えた日本語を試したく応募した。勤務は午前9時から午後1時、3日に1日休みをはさむ。決して上手な日本語ではないが、「参加したい。役に立ちたい」という意欲にあふれていた。
横渓にいた富澤裕子さん(50)は韓国人の夫に嫁いで19年。元教師で現在は横渓近くに住み、日本語を教えている。「地元だから」と参加した。
年配のボランティアには「地元」意識で参加する人が少なくない。研修はあまり実施されていなかったようだが、笑顔を絶やさず接している。ある意味、ボランティアの原点はそこにあるといってもいいだろう。

横渓の通訳ボランティア、富澤さん(左)と同僚スタッフ
前述の齋藤さんは、ボランティア活動について「パッションだ」と言い切る。熱い思いがなければ、確かに志願などできない。
さて11万人の参画をめざす東京ではこうした情熱の波は起こるだろうか。一方で、情熱だけでは対処できない問題も横たわる。その多くは「言葉」に関わることだが、そこをどう克服していくのか。報告、分析の次にくるボラサポに提言に注目したい。
- 関連記事
- 日本財団パラアスリート奨学生の平昌(1)「ほろ苦い経験を未来に…」
- 東京2020ボランティア文化を花咲かそう―大会組織委員会と協定締結
- 障がい者アートやパラスポーツを通じて、誰もが「自らの生き方を選択することができる」社会へ
- 2020年パラリンピックを機にインクルーシブな社会へ―パラアスリート奨学金授与式
- パラスポーツを通じて障害者への理解を―「あすチャレ!Academy」開講へ