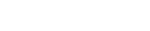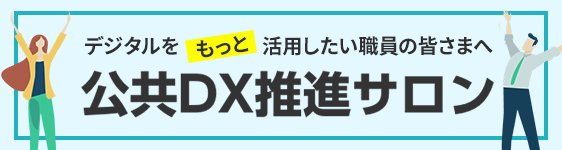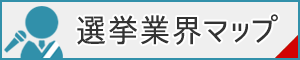パラアスリートがロボットを操る「サイバスロン」第1回国際大会が開催 (2016/10/14 日本財団)
パラアスリートがロボットを操る
器具の優劣と技術力が勝敗のカギ
最先端のロボット技術などを使った、高度な補助器具を身に付けたパラアスリートたちが、技術開発者とチームを組み、正確さと速さを競う「サイバスロン」第1回国際大会が10月8日、スイス・チューリッヒで開催されました。世界中から25カ国75チームが参加、日本からはメルティンMMI、和歌山大学RTムーバーズ、サイボーグの3チームが日本財団の支援を受けて出場しました。

サイバスロン国際大会が開催されたチューリッヒの会場
サイバスロンは、電動で制御する補助器具を使わずにスポーツで競い合うパラリンピックとは異なる、新しいコンセプトの競技会です。大会では、電動義手レース、電動義足レース、電動車いすレース、電動外骨格(下半身の動きを補うロボットスーツ)レース、FES(電気的刺激)自転車レース、BMI(脳波でコンピューターを操作する方法)レースの6種目が行われました。
器具の優劣と、それをパイロットと呼ばれるパラアスリートたちがどこまで使いこなせるかの2点が、勝敗を決めるカギです。日本チームは、メルティンMMIが電動義手レースとFESレースに、和歌山大学RTムーバーズが電動車いすレースに、サイボーグが電動義足レースに参加しました。
電動義手レースでは、コース上に設けられた6個の課題に挑戦します。例えば、お盆の上に物をのせ、落とさないようにスロープを歩く、電球を取り替える、缶を開ける、ボトルを開ける、パンを切る、洗濯物を干すといった日常にある動作が盛り込まれています。課題ごとに点数がつけられ、得点の高いチームが勝利となります。コントローラーで制御された電動義手を使いこなし、つかむ・放すという動作を正確に素早く実施することが勝敗を分けます。

電動義手レースに出場したメルティンMMI
メルティンMMIは筋電位(筋肉を動かす時に神経を伝わる電気信号)をキャッチして動く義手をパラアスリートが装着してレースに挑み、予選を通過。決勝ラウンドに勝ち残り、8位入賞となりました。
FESレースは、電気刺激で足の筋肉を動かして自転車のペダルをこぎ、フィニッシュライン(トラック10周)にどちらが先に到達するかを競うレース。トラックからはみ出るとペナルティーがつくため、正しく周回コースを回る技術も求められます。メルティンMMIはパイロットが車いすタイプのマシンに乗って登場。今回は10周には到達しませんでしたが、会場から大きな声援を受けました。

電動車いすレースに出場した和歌山大学RT-ムーバーズ。前日に行われたテクニカルチェックの様子
続いて登場したのは和歌山大学RT-ムーバーズ。街中で利用されている車いすとは異なり、レースで各チームが使ったのはタッチパネルで姿勢や階段の昇降を制御するより高度な電動車いすです。
コースは6つの課題ゾーンごとに点数が付けられ、その合計が一番高かったチームが勝利、同点の場合はクリアにかかった時間で勝敗が決まります。スラロームやドアのついたスロープの上り下り、ガタガタ道、バンク、階段と難関をクリアすることが求められます。キャタピラで障害物に挑む機体など個性的なものが続々と出てくる中、RTムーバーズは元パラリンピアン・伊藤智也さんが4つの車輪を駆使してレースを沸かせ、4位入賞を果たしました。

電動義足レースで階段に挑戦するサイボーグ
また、電動義足レースにはサイボーグが出場。電動義足レースも他のレースと同様、6つの課題ゾーンがあり、それぞれに点数がつけられます。いすに座ったり立ったり、ハードルをくぐったり、皿の上にリンゴをのせて階段を上り下りしたりと、バランスや、膝やかかとの絶妙な力の入れ具合が求められる障害にチャレンジします。普段の生活で使っている電動義足で挑戦するチームの中、サイボーグは12位で予選敗退となりました。
参加チームのいくつかは、実際に利用されている電動補助器具を装着し、勝負に臨みました。こうしたトップアスリートの大会があることで技術がさらに磨かれ、より使いやすい器具が出てくることが期待されます。

- 日本財団は、1962年の設立以来、福祉、教育、国際貢献、海洋・船舶等の分野で、人々のよりよい暮らしを支える活動を推進してきました。
- 市民、企業、NPO、政府、国際機関、世界中のあらゆるネットワークに働きかけ、社会を変えるソーシャルイノベーションの輪をひろげ、「みんなが、みんなを支える社会」をつくることを日本財団は目指し、活動しています。
- 関連記事
- 2020年東京パラリンピックに向けて、アスリート奨学金制度を設立
- みんなでつくろう!バリアフリー地図―2020年東京パラリンピックに向けて
- 「ゴールボール」スマホアプリ登場―リオパラリンピックで女子代表も活躍
- 車いすでも安心、鳥取県がユニバーサルタクシーの配備を促進
- ソーシャルイノベーション関連記事一覧