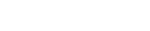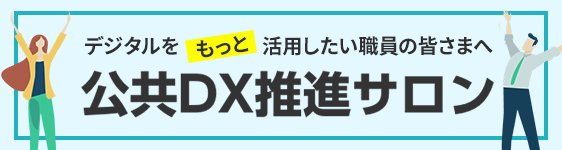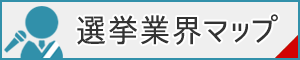[用語解説]連座制
「秘書がやりました」は許されない連座制の仕組み (2020/3/4 東京工業大学環境・社会理工学院研究員 本田正美)
議員の言い逃れとして使われるイメージのある「それは秘書がやりました」というフレーズ。それが簡単に通用しないのが選挙違反である。
選挙違反で適用される「連座制」
選挙違反は「秘書がやりました」では済まされず、もし秘書が違反を犯していた場合、当選が無効になることがある。当選が無効となれば、議員は議席を失うことになり、さらには、同じ選挙に同じ選挙区から5年間立候補できなくなるという制限まで課される。
このように、秘書であっても違反を犯せば、議員も責任を負うことになる仕組みが「連座制」である。
ここでは、「議員」としたが、正確には「候補者や立候補予定者(候補者等)」が連帯して違反の責任が問われる仕組みが、選挙違反に関わる「連座制」である。「秘書」についても、その他に選挙運動に関わった関係者が含まれる。
「連座制」に関する法律
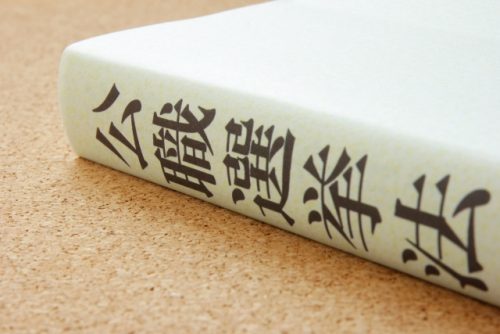
「連座制」については、公職選挙法第251条の2から第251条の3で規定されている。
残念ながら、その条文は読みにくい。そこで、選挙制度について解説した自治体のWebサイトを参照してみよう。例えば、横浜市のWebサイトの該当ページでは以下のように説明がなされている。
「連座制とは、候補者・立候補予定者と一定の関係にある者が買収などの罪をおかして刑に処せられた場合(執行猶予を含む)、たとえ候補者・立候補予定者が買収等の行為に関わっていなくともその選挙の当選を無効にするととともに、立候補を制限する制裁を科す制度です」(横浜市ホームページより)
余談だが、自治体のWebサイトでは、選挙制度に関するページは開設されていても、連座制の説明がないところがある。広島県はその例で、いくら探しても県のWebサイトの中に連座制に関する説明が見つけられない。
ここで焦点となるのは、選挙違反を犯した人物が連座制の適用される「一定の関係にある者」に含まれるのかどうかである。この適用範囲を明確にしておかないと、例えば候補者等を陥れるために、およそ無関係の人物が選挙違反をあえて犯して、当選無効を実現させることができてしまう。
「連座制」の対象者
連座制が適用される対象になるのは以下のとおりである。
- 総括主宰者
- 出納責任者
- 地域主宰者
- 候補者等の親族
- 候補者等の秘書
- 組織的選挙運動管理者等
ここまでの話の流れで一番分かりやすいのは「5」だろう。候補者が使用している秘書である。秘書という名称の他に、それに類似する名称も含めて、そのような名称の使用を候補者等から認められている人物がこれに当たる。
「4」も分かりやすい。候補者等の親族である。ここで言うところの親族の範囲、は候補者等の父母、配偶者、子または兄弟姉妹までである。
次に「6」であるが、これは選挙実務に通じていないと、少し分かりにくい。こちらは「組織的」というところがポイントである。
ここで言う「組織」とは、政党や後援会、選挙事務所はもちろんのこと、会社や労働組合、町内会や同窓会のようなものも含まれる。選挙運動を行う際に、それらの組織が協力することがある。そのような組織において、選挙運動の計画や立案から指揮や監督までを行う者というのが「組織的選挙運動管理者等」ということになる。
ここまでの4、5、6の対象者は選挙運動期間前の活動についても選挙違反に問われる可能性がある。
対して、以下の1、2、3は、選挙運動期間中の活動について違反が問われる可能性がある関係者となる。
まず、「1」であるが、これは選挙運動全般を取り仕切っていた人である。「選対本部長」とか「選挙事務局長」といった役職の人物がこれに当たる。
「2」については、選挙を行うにあたって候補者等は出納責任者の届け出を行うことになっており、その届け出された者ということになる。実際には何をしているのかというと、俗に言う「金庫番」の役割を担っており、選挙に関わるお金の出入りを管理する人物である。正式に届け出された出納責任者の他に、届け出された出納責任者と意思を通じて実質的に資金の管理を行っていた人物も含まれるとされている。
「3」は少し分かりにくい。公職選挙法には、「三以内に分けられた選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の地域のうち一又は二の地域における選挙運動を主宰すべき者」と規定されている。端的に言えば、選挙区内の一部地域の選挙運動を主宰する者であり、「1」の総括主宰者に準じる立場で一部地域において選挙運動を取り仕切っている人物である。
罰金以上か禁固以上で「アウト」
代表的な選挙違反としては、買収罪がある。選挙区内の有権者にお金を渡して投票を依頼するというのが分かりやすい買収の事例である。その他にも、無償を基本とする選挙運動にあって、公職選挙法上で報酬を支払うことが認められている範囲を超えて報酬を支払ってしまった場合にも買収罪となることがある。
選挙違反を犯し、1、2、3については罰金以上の刑に処された場合、4、5、6については禁固以上の刑に処された場合、連座制が適用されて当選の無効や立候補の制限がなされることになる。
実際には、自らの陣営の中から「1」から「6」に該当する人物の選挙違反が疑われ、起訴された段階あたりで、選挙無効となることを待たずに公職を辞職してしまうケースもある。
候補者自身が選挙違反に関与していなくても、関係者の中で選挙違反を犯し、罰金や禁固以上の刑に処されれば、選挙無効や立候補制限が課されてしまうのが連座制であり、選挙違反の疑惑が生じただけでも、選挙に勝ち抜いて公職に就いている者とすると気が気ではないだろう。
- 関連記事
- 選挙運動の手伝いは無報酬が原則
- 田母神氏が認めた運動員への報酬、知らなかったでは済まない?
- 電話作戦への報酬支払いは買収?―升田氏運動員逮捕
- 石関議員の元秘書逮捕―なぜ看板の設置が買収になるのか
- 「知らなかった」では済まない、町内会にも適用される連座制