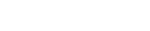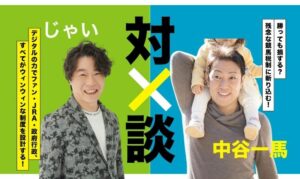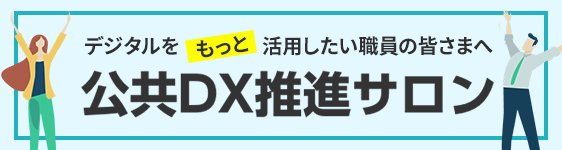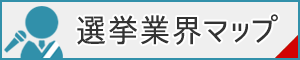【じゃい×中谷一馬】勝っても損する?残念な競馬税制に斬り込む! デジタルの力でファン・JRA・政府行政、すべてがウィンウィンな制度を設計する! (2025/11/14 政治山)
競馬での払戻金は一時所得として扱われますが、経費と認められる範囲が非常に限定的であるため、実際の収支とかけ離れた課税が行われるケースがあります。
この現状をテーマに、じゃい氏と中谷一馬衆院議員の対談の様子をご寄稿いただきました。
じゃい――いまの活動は〝人生最大のギャンブル〟
中谷―――簡素性・公平性という大原則に基づく見直しを
【じゃい】「MKK 未来の競馬税制を考える会」、通称・MKKという団体で、競馬界の健全な発展をめざす活動をしている「インスタントジョンソン」のじゃいです。僕、この活動を始めてから、結構、頻繁に議員会館へ来るようになってるんですよ。
【中谷】じゃいさんのYouTubeチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」を見たのですが、国会議員の部屋を回られているそうですね。
【じゃい】そうなんです。アンケートを配ったりとかして。芸人なのに、僕はいったいなにをやってるんだろう、って思ってますけど(笑)。
【中谷】でも、アプローチとしては、間違っていないと思います。まず議員に会って問題を知ってもらい、考えを聞く。そしてコミュニケーションを重ね、議論を深めた上で、関心を持つ方々に議員連盟などを作ってもらい、そこを通して当局とやり取りをする――そうやって少しずつ改善を図るというのがアプローチの一つだと思います。ですから、じゃいさんのやり方は、素晴らしいな、と思って見ていました。
【じゃい】ありがとうございます。結構長い闘いになるでしょうが、少しでも前に進めることができればと思っています。ご協力お願いします。
【中谷】もちろんです。乗りかかった船なので、頭をひねって研究していきたいと思っています。
「6400万円の的中」がきっかけ
【中谷】これまでさんざん話していらっしゃると思いますが、あらためて、活動を始めたきっかけを教えていただけますか?
【じゃい】発端は2020年12月に、川崎競馬で、指定された3レースの馬単を当てる「トリプル馬単」を的中させ、6410万6465円の高額配当金を受けたことです。
【中谷】さすがですね。大金持ちじゃないですか。
【じゃい】ところがそうはいかなかったんです。翌年秋、自宅に税務署員2人が家を訪ねて来ました。
【中谷】税務調査ですね。でも、競馬で得た所得はきちんと申告していたんですよね?
【じゃい】もちろんです。僕は、馬券の大半をインターネットで購入していて、使った額は5年間で合わせて数億円、配当金も数億円あって、トータルでは勝った分が多かったのですが、それは間違いなく税務申告していたのでやましいところはいっさいなく、求められるままに通帳や書類などすべて差し出しました。職員は、ネットの馬券購入システムの履歴なども閲覧し、購入金額と払戻金額をメモしていきました。
【中谷】現在の法律では、競馬で得た所得は基本的に税務申告することが義務づけられていますが、実際はほとんどが申告されていません。競馬場や場外馬券場で馬券を購入する際、あるいは配当金を受け取る際、身分証明などを登録する必要がないですからね。よって国税当局が馬券による収入を把握するのは難しい。公営ギャンブルで当たった1000万円以上の高額配当金のうち、約8割が税務申告されていないという数字もあります。
【じゃい】ただ最近だと、私のようにネットで大量の馬券を一度に購入するファンは、サイトへの登録時に身分証明が求められ、購入履歴も残りますので、税務申告しないとあとで国税当局にバレてしまう可能性があります。
【中谷】それが理由というわけではないでしょうが、じゃいさんもごまかすことなく申告していたんですね。
【じゃい】はい。きっちりと。
【中谷】ご存じのように、競馬や競輪などの配当金はたいがい「一時所得」に分類され、1年間に受けた合計が特別控除の50万円を超えていれば申告が必要となります。一時所得とは、所得税法の10種の所得区分のうちの一つで、懸賞や福引、競馬の配当など偶発的もしくは臨時的な所得を指します。
【じゃい】一時所得の場合、必要経費として認められる範囲が狭く、控除できるのは「その収入を得るために直接要した金額」のみ、つまり競馬の配当金であれば、「当たり馬券」の購入費がそれに該当します。よってハズレ馬券の分は経費として認められません。たとえば8000万円分購入し、合計で1億円の払い戻しがあったとすると、トータルの儲けは2000万円ですが、税務申告する際、購入費の負け分はほぼ経費として考慮されず、配当金の1億円から当たり馬券購入費と50万円を引いた額に税金がかかります。結果として儲けの2000万円分くらいは税金で徴収されてしまいます。よって仮に年間トータル収支がマイナスでも、税金の支払い義務が生じることがあるのです。これでは、競馬を続ける意味がなくなります。
ハズレ馬券は経費として認められず
【じゃい】このとき税務調査が入ったのは、その一時所得ではなく、「雑所得」として申告したことがひっかかったのです。
【中谷】雑所得は、事業による収益などで収入、つまり「偶発的」「臨時的」な所得ではなく、営利を目的とする継続的行為から生じた所得を指します。副業の所得なども一般的に雑所得とされます。税金の扱いとしては、一時所得とかなり仕組みが異なり、年間トータルの収入から、そのために使った総額=必要経費を引いた〝利益〟に対してのみ課税されます。
【じゃい】つまり一時所得と違い、ハズレ馬券は必要経費として認められるだろう、と。
【中谷】確かに、馬券の配当金であっても、「偶発的でない所得」あるいは「継続的かつ安定した業務で得た所得」と認められれば、「雑所得」として扱われることはあります。ただ、今回調べてみて知ったのですが、雑所得として申告するには、高いハードルがある。国税は、雑所得に分類されるものは、「他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得で、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金など」と厳格に位置づけています。
【じゃい】もちろんそのことは知っていました。実際、2015年以前は一時所得として申告していたんです。ただ、周りから「じゃいさんは競馬番組に出演し、本も出版し、スポーツ新聞で予想もしている。だから配当金は仕事の一環で得たものといえるから、雑所得でいいんじゃないか」というアドバイスを受け、それでいけると思い、変更したんです。
【中谷】つまり、「娯楽ではなく、営利目的の継続的行為」で得た収入として扱える、と判断し、ハズレ馬券分を経費として差し引いて申告していたのですね。
【じゃい】そうです。ところが、それは認められませんでした。税務署でも判断は難しかったらしく、審査に数ヵ月かかり、結局、国税局に判断を委ねたと聞いています。
【中谷】当然、追徴課税ということになりますよね。
【じゃい】2016年から2020年の5年間の配当金に対して延期分の利息含め、数千万円の請求がきました。年収の2倍以上、郊外の広めのマンションが買えるぐらいの額です。
【中谷】そんな大金、すぐに払えたんですか?
【じゃい】もちろん無理です。分割で納税しようとも考えましたが、それだとサラリーマンの年収分くらいの利息が発生してしまうので、仕方なく、子どもたちの将来のため妻が蓄えていた貯金に加え、親が老後に備えてとっておいた金を借りて一括で支払いました。
【中谷】競馬で大勝ちしたのに、そのせいで借金するなんて、たまったものじゃないですね。
【じゃい】この件については、現行法の理解が足りなかった自分が悪いので仕方ないと思っています。だから素直に従うことにしました。税務署の担当者の家族に不幸があり3ヵ月調査が中断し、その間の延滞料も請求されたのは納得いかなかったですが(笑)、それよりも勝ったところで全部持っていかれるこの法律の仕組みに対して、理不尽さを感じました。これでは、まるでカツアゲです。正直、いままで、なんのために労力を費やして競馬予想をやってきたんだろう、と虚しい気持ちになりました。
「不服申し立て」で寄せられた応援の声
【中谷】たとえば裁判をしようとは思わなかったんですか?
【じゃい】それも考えました。これまでも裁判で、ハズレ馬券の購入費が経費として認められたケースもあります。けれど国と戦うとなると、弁護士費用含め数千万円かかります。仮に敗訴となった場合、倍くらい払うことになる可能性もある。そうなったら、もっと家族に迷惑がかかるので断念しました。ただ、一連の経緯を「じゃいちゅ~ぶ」にあげたら、大変な反響を呼び、ファンから応援の声が寄せられたこともあり、追徴課税分をきちんと納付した上で、2022年6月に、「ハズレ馬券代が経費として控除されないのはおかしい」と主張し、国税不服審判所へ審査請求しました。
【中谷】確かにそれだと裁判のように長期間かかることはないですし、無料でできますが、代理人となる弁護士や税理士へ払う費用は必要です。それはどうしたんですか?
【じゃい】恥ずかしながら、そのときの僕には代理人を雇う力がありませんでしたから、同じ思いを抱く方、賛同していただける方に協力を呼び掛け、寄付を募りました。ただ、言うまでもなくこの不服申し立ては、追徴課税を払いたくないとか、自分の金を返して欲しいということではありません。理不尽な税制に対して、なにかできることがないかと考え、始めたことです。決して自分のため、ましてや金のためではありません。そもそも、そのすぐあと、妻と両親への借金は全額返済できたので、お金の問題は解決しました。
【中谷】え? どういうことですか?
【じゃい】8月に中央競馬で5レース分の勝ち馬を当てる「WIN5」を的中させまして……配当金は、自己最高の9670万6710円でした。
【中谷】なんと!
【じゃい】ただ、昔のように素直に喜ぶことはできませんでしたね。税制の問題を勉強する中で、極端なことをいえば、もはや競馬でいくら儲けたとか、そんなものはどうでもいいという気持ちになっていましたから。
【中谷】単純に競馬を楽しめなくなり、税制の理不尽さやその改正を訴える方へ気持ちがシフトしていったということでしょうか?
【じゃい】というか、競馬界を盛り上げるためにも、法律を変えたほうが断然良い、と強く思うようになっていました。それはやはり、不服申し立てと寄付金募集に賛同してくれる競馬ファンがたくさんいたからにほかなりません。貴重なご意見、アドバイスもいただいたし、「協力します」「応援します」といった励ましの声には本当に勇気づけられました。それで、僕でしかこの法律を変えられないかな、と感じ、集まった寄付金は審査請求にかかる費用以外は、ロビー活動などに使おうと考えました。
【中谷】そして活動をより本格化していったわけですね。
【じゃい】2022年12月に一般社団法人という形で、「未来の競馬税制を考える会」を立ち上げました。会の事業目的は、「デジタル時代における競馬を中心とした公営競技を取り巻く納税環境の整備と適正・公平な課税の実現」、それによって競馬界のさらなる発展に寄与し、社会へ貢献することです。
【中谷】結局、国税への不服申し立てはどうなったんですか?
【じゃい】翌年3月に棄却されました。ただ、それは想定内のことです。審査請求の目的は、競馬税制の見直しにつなげるため、一石を投じて広く問題について知ってもらうことだったので、棄却自体は重要ではありません。本筋は、それからあとの闘いになると考えていたので、棄却直後の4月、「考える会」のホームページで会員募集を始めました。会費は1口980円です。
【中谷】ロビー活動はいつからやっているんですか?
【じゃい】不服申し立てをしたころから、国会議員や都議会議員と意見交換していたのですが、「考える会」の設立以降、より力を入れています。いまは競馬ファンを代表して、法律を改正してもらえるよう地道に国会議員等に働きかけているところです。
画期的な二つの最高裁判決
【中谷】競馬の配当金についてなにが問題なのかということを、根本的なところから勉強したことがなかったので、今回、自分なりに調べてみました。さきほどの話にも出てきましたが、ハズレ馬券を経費として認めるよう求めた裁判の判例がいくつかあります。28億7000万円分の馬券を購入し、30億1000万円の払い戻しを受けた大阪市の男性が提訴した裁判では、2015年に最高裁が、「営利目的で継続的に購入していた」として、「ハズレ馬券の費用も経費になる」という判決を出しています。この男性の場合、ハズレ馬券が経費となれば、所得額は1億4000万円のみですが、一時所得だと30億1000万円から当たり馬券の購入費と特別控除額を引いて28億8000万円になります。その差は20倍ですから、どの所得区分になるかで大違いです。男性は市販の競馬予想ソフトを改良して独自のシステムを構築していたのですが、最高裁は判決の理由として、「そのシステムの予想に従い、偶然性の影響を減殺するため、ほぼすべてのレースで馬券を購入するなどして、年間通じての収支で多額の利益を上げている」ことを挙げています。
【じゃい】はい。ただ、この裁判は、提訴から判決が確定するまでに6年もかかっています。【中谷】それから2017年には、ネット上で自動的に大量購入できる予想ソフトの使用に関係なく、「競馬を事業として行っていれば、ハズレ馬券は経費となる」という最高裁判決が確定しています。提訴した札幌市の公務員男性は、数年間で70億円を超える馬券を購入して5億7000万円の「利益」を得ていましたが、彼は、大阪の男性とは異なり、ソフトを使わずレースごとに独自の理論で予想していました。
【じゃい】この二つの裁判も、スポーツ新聞などでも大きく取り上げられ、話題になりましたね。
【中谷】15年の最高裁判決を受け、国税庁は配当金の所得区分についての統一的な解釈基準を定めた国税庁通達を改正し、経費算入の要件に、自動購入できるソフトの使用を盛り込んだのですが、2年後の17年判決によって、再度の通達改正を余儀なくされています。つまり、自動購入ソフトの利用に限定せず、一定の購入パターンに従い、「年間を通じてほぼすべてのレースで馬券を購入」し続け、回収率が100%を超えるとき、配当金を雑所得とすることを認めざるをえなくなった。最高裁判決が示されるたびに国税庁による通達改正が行われるというのは、税法の基本原則である租税法律主義(何人も法律の根拠がなければ租税を賦課されたり徴収されたりすることがないとする考え方)に基づく予測可能性・法的安定性に欠け、大変問題だと思います。よってこのような取り扱いは通達ではなく法律上明記しておく必要があります。
【じゃい】「配当金は基本的に一時所得とする」というのは、1970年の国税庁通達が根拠になっているのですが、二つの最高裁判決は、その通達が時代遅れであることを示したという点で、非常に大きな意義を持つものといえます。
ルールが破綻している
【中谷】ただ、ハズレ馬券の購入代金を経費として認めるよう求めた訴訟で、原告である納税者側が勝ったのはこの2例だけ。そのあと、横浜と東京で、同様の裁判がありましたが、いずれも「恒常的に利益を上げていたと認められない」としてハズレ馬券の経費算入は認められず、「課税処分は適法」とする判決が出ています。
これらの判決内容を総合的に判断すると、自動購入ソフトなどのプログラムシステムを駆使して大量かつ継続的に馬券を購入し、そのログが残っており、かつ回収率が100%を超えている、つまり馬券を購入するのにかかった費用より勝ち馬券によって得た配当金が上回っている場合に関しては、納税者側が勝訴しています。一方、自己判断を加味しているもの、回収率が100%いっておらず、事業として認められていないものは敗訴している。投資的な意味合いではなく、趣味の領域のものも経費算入が認められていません。
【じゃい】判決が分かれた理由は、明確に分かりませんが、内容だけ見ると、課税額の大きさが関係しているように感じてしまいます。大阪と札幌の事案は、ハズレ馬券に対する控除がなければ、追徴課税は10億円をこえ、現実的にはとても払えるものではありません。一方、敗訴したケースは1000万円以下で、なんとか払える金額でした。
【中谷】納税者側を勝訴とした判決に対して、新聞などでいくつか専門家の論評が紹介されていますが、たとえば税理士で大阪国税局OBの辻一夫さんは、ネットで大量の馬券を購入できるようになった現代社会を反映した判決だから、税制はそのままで良いが、「どの程度の規模の馬券を購入すれば雑収入として認められるかといった明確な線引きが必要」と言っています。その考え方でいえば、初めから金額で線引きする方法もあるかもしれません。
【じゃい】僕は、雑所得か一時所得かに焦点を当て、その線引きをするのではなく、制度そのものを変えなくてはいけないと思っています。そもそも、裁判で勝ったり負けたりするという時点で、この制度は破綻しているといっていい。
【中谷】じゃいさんと同じように、弁護士の木山泰嗣さんは「競馬の払戻金に対する税制は非常に古いルールで、さまざまな問題がある。よって今後も同様の事案が起こるたびに裁判をやることになるので、税制の仕組み自体を見直した方がいいのではないか」と言っています。
確かに税金を適性に払ってもらうには、制度が公平で、できるだけ簡素にしなければならないというのが原則です。その意味で、所得税法の所得区分そのものを時代に即して見直すべきだと私は思います。現在の制度では、所得区分の基準や考え方が必ずしも一様ではなく、税制として分かりにくいことが問題の根幹にあります。だからたとえば、一時所得と雑所得については、双方の特別控除や課税制度を廃止した上で「その他所得」として同一の区分に統合するなど、分かりやすい税制にする選択もあるのではないでしょう。
「二重課税」問題と「還元率」のバランス
【じゃい】僕が声を大にして言いたいのは、馬券の「二重課税」問題です。例えば競馬の売り上げは、基本的に約25%が控除され、残りの約75%が配当金となります。控除分の内訳は、中央競馬の場合は約15%がJRA(日本中央競馬会)の運営費に充てられ、残りの約10%が国庫納付金となります。つまり馬券購入者は購入時点ですでに10%分を国に納めている。よって競馬ファンである時点で、すでに国に貢献してるといえます。JRAの売り上げは、いま年間3兆円ありますから、3000億円が国庫に入っている。それなのに、配当金にも税金がかかるのはおかしいでしょう。
【中谷】馬券を買った時点で国庫納付金という形で事実上の税金を納めているにもかかわらず、配当金を得たらさらに納税する必要があることを、「二重課税」と言っているわけですね。
【じゃい】「二重課税」のシステムによって長年、競馬ファンは悩まされてきました。これまでその問題はほとんど表に出ませんでしたが、さきほどの二つの裁判によって、やっとクローズアップされるようになりました。ゲームの影響などで新しいファンが競馬に入っているいまだからこそ、もっと注目されるべきだと思います。
【中谷】では、税の水平的公平性を保つという観点から、具体的にどのような税制の仕組みにするのか――これに関し、有識者の提言を紹介しましょう。税理士の芹澤光春さんの意見は、「源泉徴収制度を導入すべきではないか」というもの。つまり競馬場や場外馬券場で購入する人への配当金を把握するのは現実的に困難なのだから、払い戻しの段階で、配当金の中から税金分を源泉徴収するというやり方です。これに対し、税理士の久乗哲さんは、宝くじのように非課税化すべきという意見です。この考え方の根底にあるのは、さきほどの「二重課税」問題があります。
【じゃい】僕の目標は、当然、非課税化です。
【中谷】非課税とする場合、ネックとなるのは還元(払戻)率です。宝くじやサッカーくじが非課税となっているのは、還元率が約5割で、競馬などの公営競技のギャンブルに比べて低いという点が関係しています。よって、競馬を非課税のビジネスモデルとするには、他の公営競技や宝くじなどの還元率と、どうバランスを取っていくのか、というのが一つの焦点になると考えられます。これについて明治学院大学教授の渡辺充さんは、「『馬券税』を再開することも一考に値するのではないか」と言っています。「馬券税」とは、馬券の購入金額の7%、配当金の20%を国に納付するという仕組みで、昭和17年から23年までの間、導入されていました。配当金を所得税非課税とした上で、これを導入すれば還元率は下がります。
【じゃい】宝くじやサッカーくじは、1等が当たってなんぼで、1回当たればほぼプラスになるという感じの、もっともギャンブル性の高いものです。つまりはずれるのが当たり前で、当たる人がほぼいないと分かった上で皆、購入しています。一方、競馬の場合、予想が堅いときも荒れるときもあり、それによって当たる確率が変わります。そういうギャンブルで、配当金からそこまで引かれると、回収率100%を上回る人なんてほとんどいなくなってしまう。ただでさえ競馬でプラス収支を出すのは至難の技なのに、これでは真の意味で「勝つ」のはほぼ不可能です。それじゃあ、夢がありません。だから還元率のバランスについてはさまざまな意見があるでしょうが、僕は非課税にした場合も、還元率を下げてはならないと思います。
誰もが安心して競馬を楽しめるように
【中谷】いずれにせよ、誰もが納得いくような制度内容に整える必要があります。
【じゃい】少なくとも、いまの制度のままでは、「高い税金を課せられるのが怖いので、馬券を買うのを控える」というファンは、さらに増えていくと思います。「当たるのが怖い」って変な話です。僕が追徴課税の件をYouTubeで公表した際、「いつも損しているのに、当たると高額の税金を課せられるのではたまったもんじゃない。もう競馬をやめる」という人が結構いました。
【中谷】税制が競馬振興を妨げているとすれば、大きな問題ですね。
【じゃい】しかもそういうのは、だいたいが大口です。大口の的中者をやり玉に上げて萎縮させるようないまの税制の仕組みだと、そうした人たちはノミ屋を利用したり紙の馬券を買って、当たっても申告しないといった抜け穴を使うようになります。結果として税収がさらに下がります。しかし、非課税にすれば、普通の競馬ファンが安心して遊べるのはもちろん、大口の人たちも思い切って馬券を買えるので、JRAの売り上げ増につながり競馬界は盛り上がり、そして国庫納付金も増えるので、国にとってもプラスなのではないでしょうか。
【中谷】たとえば国会で提案する場合、「これなら競馬振興につながる」「国や地方自治体の財源が確保される」「配当金をめぐり追徴課税を受けて困ってる人たちがたくさんいるという問題が解決される」など、多くの人にとってウィンウィンとなるトータルパッケージの提案であれば、政府や行政も動いていく可能性があると思います。
【じゃい】同感です。税制が変われば競馬界も盛り上がり、国や地方も潤う、すると結果として競馬ファン以外の人たちへも恩恵がもたらされます。言い方を変えれば、競馬が社会全体に貢献できるようになるのです。
【中谷】さきほどの話にもありましたが、いま競馬は、自宅のパソコンや携帯電話等を用いたネットを介した馬券購入が可能となっており、購入手続きのデジタル化により、配当金額や的中馬券購入者の情報を捕捉・把握する環境が整いつつあります。さらなるデジタル化で「見える化」を進展させることによって解決できる問題がいくらでもあります。この点を踏まえ、租税の大原則である簡素性や公平性に鑑み、ギャンブル依存症などの懸念点も考慮しながら、現状の課税関係の制度を見直す時期にあるのではないでしょうか。
【じゃい】いまの競馬税制は、相当古い法律ですから、デジタル時代に即してアップデートしていかなくてはならないことは間違いありません。このままでは競馬界がしぼんでいきます。そうならないよう、競馬ファンが安心して馬券を買えるようなシステムにしたいのです。
僕は、この活動で利益を得たいなどとはまったく考えていません。ただ、この競馬の税制改革という「人生最大のギャンブル」に、なんとしても勝ちたいと思っています。
【中谷】是非、ともに研究を重ねてより良い制度を作りましょう。
■じゃい
1972年生まれ。97年、お笑いトリオ「インスタントジョンソン」を結成、ボケ及びネタ作りを担当する。2003年に第1回お笑いホープ大賞を受賞。「おつかれちゃ~ん」が一世を風靡する。パチプロだった祖父の遺伝かギャンブル全般に強く、09年にはギャンブルで貯めた5000万円でマンションを購入。競馬、麻雀、ポーカーなどに造詣が深く、とくに競馬では2022年8月にWIN5で9370万円の配当金を得るなど数々の伝説を持つ。チャンネル登録者数が24万人を超えるYouTubeチャンネル「じゃいちゅ~ぶ」や、ニコニコチャンネル「じゃいチューブ(笑)」で競馬や麻雀などの話題を中心に発信している。23年に競馬税制の改正をめざし、本名の「渡辺隆広」で一般社団法人「未来の競馬税制を考える会」を設立した。著書に、『稼ぐギャンブル[完全版]』(太田出版)、『勝ち方がわかる 馬券の教科書』(池田書店)、『勝てる馬券の買い方』(ガイドワークス)など。
■中谷一馬(なかたに・かずま)衆議院議員
1983年生まれ。貧しい母子家庭で育ったことから経済的に自立するため、日吉中学卒業後、社会に出る。のちに、一念発起して横浜平沼高校(通信制)に入学し、21歳で卒業。その後、働きながら、呉竹鍼灸柔整専門学校に通い、柔道整復師の資格を取得。慶應義塾大学(通信制)に進学。デジタルハリウッド大学大学院ではMVPを受賞し首席で修了。DCM(デジタルコンテンツマネジメント)修士号の学位を取得。
その傍ら、東証プライムに上場したIT企業gumiの創業に役員として参画後、のちに内閣総理大臣となる衆議院議員・菅直人氏の秘書を務め、27歳で神奈川県議会における県政史上最年少議員として当選。在職中に世界経済フォーラム(ダボス会議)のGlobal Shapers(U33日本代表)に地方議員として初選出。
2017年、立憲民主党 神奈川7区(横浜市港北区) 衆議院議員に当選。(現在3期目)
2020年&2023年には、咢堂ブックオブザイヤーにて大賞を受賞。2024年には、国会で最も活動した議員として「三ツ星議員」(709名中12名)に選出。
現在は、立憲民主党 野田「次の内閣」ネクストデジタル・行政改革・公務員改革担当大臣、幹事長特別補佐、神奈川県連幹事長などを務めながら妻と共に6歳と3歳の娘たちの子育て中。趣味は、”ラーメン”の食べ歩き。
- 関連記事
- 未成熟な社会への警笛-藤井浩人美濃加茂市長×中谷一馬衆院議員
- 2026年“デジタル円”始まるか―黒田日銀総裁の見解から見える近未来
- 【専門家LIVE】インターネット投票はどうすれば実現できるのか!?
- 法務省矯正支援官のゴルゴ松本氏が登壇-職親プロジェクト東京支部の発足式が開催