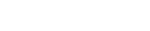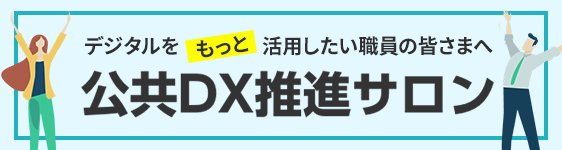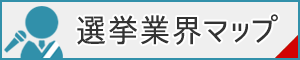【早大マニフェスト研究所連載/マニフェストで実現する『地方政府』のカタチ】
第75回 「圏域マネジメント」を担う職員の人材育成~「五所川原圏域未来志向型人財育成塾」の取り組み (2018/7/25 早大マニフェスト研究所)
早稲田大学マニフェスト研究所によるコラム「マニフェストで実現する『地方政府』のカタチ」の第75回です。地方行政、地方自治のあり方を“マニフェスト”という切り口で見ていきます。
「自治体戦略2040構想研究会」報告書
2018年7月、有識者による総務省の「自治体戦略2040構想研究会」は、最終報告書をまとめた(総務省ホームページ)。今後、地方行財政制度を検討する第32次「地方制度調査会」で、人口減少が深刻化し、高齢者人口がピークに達する2040年頃の自治体行政のあり方が、地方議員のなり手不足問題(第73回「なり手不足の問題から地方議会のあり方を考える」)などと共に、具体的に議論されることとなる。
報告書では、2040年頃にかけて迫り来る我が国の内政上の危機として、次の3つをあげている。1つは、若者を吸収しながら老いていく東京圏と支え手を失う地方圏。2つ目は、標準的な人生設計の消滅による雇用・教育の機能不全。3つ目が、スポンジ化する都市と朽ち果てるインフラである。
また、この危機を乗り越えるには、人口縮減時代のパラダイムへの転換が必要として、以下の4つの新たな自治体行政の基本的考え方を提示している。(1)AIやロボティクスなどを使いこなし、また自治体行政の標準化・共通化を図る「スマート自治体への転換」、(2)シェアリングエコノミーなどの活用や、暮らしを支える多様な担い手の確保を目指す「公共私による暮らしの維持」、(3)圏域単位の行政をスタンダードとし、都道府県、市町村の既存の役割に囚われない「圏域マネジメントと二層制の柔軟化」、(4)東京圏での医療・介護のサービス供給体制の確保や、首都直下型地震発生時の広域避難体制など「東京圏のプラットフォーム」、の4つである。
今回は、その中の「圏域マネジメント」に関連して、青森県五所川原市が中心となって、五所川原圏域定住自立圏の枠組で取り組んでいる「五所川原圏域未来志向型人財育成塾(以下、人財育成塾)」の取り組みから、圏域での人材育成の可能性とその効果について考える。

2017年度第1回人財育成塾の様子
「五所川原圏域未来志向型人財育成塾」
「定住自立圏」「連携中枢都市圏」など、これまでも圏域による行政運営は目指されてきているが、総論賛成、各論反対。観光など利害衝突が少なく連携しやすい分野は取り組みの実績が多いものの、子育て、医療、介護など財政負担が伴う分野では、利害調整が難しく効果を上げていないのが現状だ。
2016年3月、五所川原市と圏域1市4町(つがる市、鰺ヶ沢町、深浦町、鶴田町、中泊町)は、定住自立圏の形成に関する協定書を締結。2016年度から2020年度までの5年間の期間の「定住自立圏共生ビジョン」を作成した。
その中で、圏域マネジメント能力の強化に関わる政策分野として、圏域自治体職員の人材育成、具体的には、共通課題・取り組み事例などについて研究会・合同研修を実施することが書き込まれている。それに基づき、2017年度から実施されているのが人財育成塾である。人財育成塾自体は、2016年度より五所川原市職員の人材育成事業としてスタートし、筆者がアドバイザーとして関わってきたが、その対象を圏域自治体職員に拡大したものである。

アドバイザーによる個別コーチング
人財育成塾では、地域課題を解決するために一歩踏み出せる職員、住民ニーズを捉えた政策提案のできる職員を目指す職員像としている。進め方として、五所川原圏域の「ありたい姿」を「未来志向」で描き、それに対する圏域の現状を正確に把握し、このギャップを埋めるための実効性の高い政策を自ら考え、具体的な政策提言を行うこととしている。「未来志向」とは、過去の経験から考えるのではなく、視野を広げ、ありたい未来、みんなで創りたい未来から考える思考の方法論である。
2017年度は、6月から12月まで全5回で開催。圏域内2市4町から若手職員18人が参加、共生ビジョンに謳われた3つの政策課題(1.子育てネットワークの強化、2.広域観光の推進、3.交流・移住の推進)に分かれて、政策研究を行った。
第1回は「20年後の五所川原圏域の未来を考える」をテーマに、参加者の関係性の構築を目指し、ワールドカフェ(第74回「ポジテイブ発想と当事者意識で実践につなげる」)で思いを共有し合った。第2回は「20年後のありたい姿を考える」をテーマに、各政策課題の担当職員から、現状の取り組みの情報提供を受け、各グループで、それぞれの課題のありたい姿と具体的に取り組みたい事業のアイデア出しを行った。第3回、4回は、アドバイザーである筆者による個別コーチング。各グループが考えてきた政策アイデアについて、1時間1本勝負で対話を行いながら、政策のブラッシュアップを行った。
それぞれの回の間には、各グループが業務内に集まり話し合いができるように、参加自治体の人事担当者は配慮した。それぞれの自治体を知る意味からも、打ち合わせの会場を持ち周りにしたグループもあった。また、筆者との間の経過報告を義務付け、メールによるコーチングも行った。

2017年度政策プレゼン
第5回は、半年間練り上げた政策を、五所川原市の企画課長、総務課長、財政課長の3人向けにプレゼンテーション。それぞれの自治体の人事担当者もその発表を聞いた。具体的な政策提案としては、子育てネットワーク強化を担当したグループは、圏域内には塾の無い地域も存在することから、圏域内の子どもの学習環境の改善に注目、ICT技術などを活用した、中学生を対象とした子どもの学習支援の提案を行った。
参加した自治体職員からは、政策力の向上の他、顔が分かる圏域内のネットワークが構築され、自治体を超えた連携へのコミュニケーションコストを下げる効果を挙げる参加者が多かった。
「未来の兆し」を感じながら政策を考える
2018年度の人財育成塾では、報告書の中にも示されている「スマート自治体」を意識して、課題をあえて特定せずに、共生ビジョンに掲げられた政策分野と、ICT、IoT、AI、ロボティクス、ドローンなどの新しい技術を結びつけて考えられる政策提案に取り組むこととした。前年度と同じ全5回のプログラムで、圏域自治体職員18人が3グループに分かれて6月からスタート。

2018年度第1回のワールドカフェ
第1回は「地方創生時代に求められる自治体職員とは」をテーマに、関係構築とチームビルデイングのためのワールドカフェを行った。第2回は「未来の兆しを感じ、新しい政策アイデアを考えよう」のテーマで、政策作りの基礎を学び合った。
行政を取り巻く技術的な「未来の兆し」はたくさんある。AIによる問い合わせ対応サービス、文書要約による会議録作成。IoTの農業分野での活用。人型ロボットによる観光案内、学習支援。ドローンによる配送、救急医療分野での利用。中山間地域による自動運転車の可能性。交通弱者対策としての、Uberなどのシェアリングエコノミー。PCを使った定型作業を自動化する「RAP(ロボティック・プロセス・オートメーション)」。オンラインWEB会議システムを活用した遠隔会議、遠隔授業。枚挙に暇がない。
「スマート自治体」になれるか否かは、職員の「未来の兆し」を感じ取る感度にかかっている。今後の政策研究でどの様なイノベーティブなアイデアが出てくるかが楽しみだ。

グループワークの様子
職員の人材育成を圏域で担う
「自治体戦略2040構想研究会」の最終報告書が示した2040年頃にかけて迫り来る我が国の内政上の危機は、「成りゆきの未来」である。つまり、我々が手をこまねいて何もしなかった時の未来である。「成りゆきの未来」を、「ありたい未来」に変えることができるのは人材だ。各地域で、その中心的な役割を担うのは自治体職員だ。報告書が提示する「圏域マネジメント」を実践するのも職員である。
小規模町村では、財政状況から単独での人材育成は、残念ながら厳しいのが現実である。ならば、圏域で職員の人材育成を担う。今後圏域行政を進めるには、圏域内の自治体の利害が対立する問題の合意形成が必要になってくる。その際には、研修を通してできた職員同士のネットワークが生きる。首長同士が笑顔で手を握り合っても、話は具体的には進まない。「圏域マネジメント」を本気で定着させるには、「五所川原圏域未来志向型人材育成塾」のような、圏域での人財育成プログラムが鍵を握っているように思う。
◇ ◇ ◇
 青森中央学院大学 経営法学部 准教授
青森中央学院大学 経営法学部 准教授
早稲田大学マニフェスト研究所 招聘研究員
佐藤 淳
1968年青森県十和田市生まれ。早稲田大学商学部卒業。三井住友銀行での12年間の銀行員生活後、早稲田大学大学院公共経営研究科修了。現在、青森中央学院大学 経営法学部 准教授(政治学・行政学・社会福祉論)。早稲田大学マニフェスト研究所招聘研究員として、マニフェスト型の選挙、政治、行政経営の定着のため活動中。
- 関連記事
- [福島・郡山市]若手職員が広域課題を研究する塾が開講
- ポジティブ発想と当事者意識で実践へつなげる~地域でのワールドカフェ活用法
- 大阪府枚方市「ワークプレイス改革」による働き方改革の推進
- [山形・新庄市]事業組合の決算情報
- なぜ地方創生は「目標」から遠ざかるばかりなのか
- ■早大マニフェスト研究所とは
- 早稲田大学マニフェスト研究所(略称:マニ研、まにけん)。早稲田大学のプロジェクト研究機関として、2004年4月1日に設立。北川正恭(元三重県知事)が顧問を務める。ローカル・マニフェストによって地域から新しい民主主義を創造することを目的とし、マニフェスト、議会改革、選挙事務改革、自治体人材マネジメントなどの調査・研究を行っている。