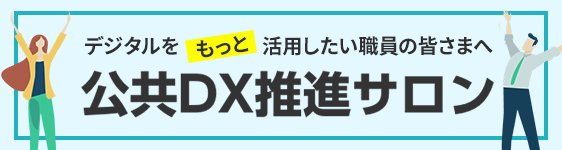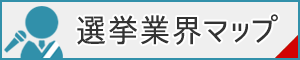高知ファンの増殖が止まらない 「好き」が生まれる場所づくりとは (2018/11/29 70seeds)
昨日まで興味がなかったものに対して、急に心惹かれるようになる。「好き」という気持ちは、偶発的な経験を通して生まれる奇跡だ。
高知県高知市に、そんな奇跡を次々に生み出すゲストハウスがある。その名は「かつおゲストハウス」。
ここに訪れた人は皆、魔法にかかったように高知の魅力に取り憑かれてしまう。この、まるで高知ファン製造工場のような空間には、どんな秘密が隠されているのだろうか。

「高知」のモチーフで満たされた空間
高知駅から北へ徒歩12分。
のどかな住宅街を進んでいくと、目の前に突然、大きなかつおが現れる。
今年7月にオープンした「かつおゲストハウス」の新館に飾られたロールスクリーンアートだ。かつおのモチーフづくしのアプローチを進み、入り口の扉を開くと、真新しい木の香りが鼻腔を満たす。
「Oh! Really!? Have a fun!!」
跳ねるようなトーンで外国人観光客と話しているのは、オーナーの前田真希さんだ。
高知生まれ高知育ちの前田さんがこのゲストハウスを立ち上げたのは、まだ「ゲストハウス」という言葉が世間に浸透する前の2012年のこと。祖父母から引き継いだ一軒家を改装して作り上げたのは、故郷の魅力が凝縮された空間だった。
「ゆずルーム」や「かつおルーム」など高知の名産品の名がつけられ、それぞれをイメージした内装のゲストルーム。「桂浜の湯」「おおつきキッチン」など、高知の地名を冠した水回り。部屋や共有スペースの各所には、かつおや鳴子など高知モチーフの装飾や、高知出身アーティストによるアート作品、そのほか高知ゆかりの品がところせましと並んでいる。
そこは、いるだけで高知の魅力や見所を空気のように吸収できる空間。見方を変えれば、オーナーである前田さんの「高知愛」がビシバシ伝わってくる空間とも言える。

バックパッカーから地元タウン誌の副編集長へ
「もともと高知には、大した思い入れも何もなかったんですよ」
意外にも、そう語る前田さん。彼女に「高知愛」が芽生えたのは、その地に生まれて20年が経過したあとのことだった。
きっかけは、旅。大学生のときにはバックパックひとつ背負って、日本中、世界中を飛び回った。在学中には、旅好きが高じて観光バス添乗員の職についた。しかし、各地の名所を訪ね、美味しいものを食べ、感動的な体験をするごとに、彼女の中には、あるひとつの想いが浮かび上がってきたという。
「高知には、海も川も山もある。こんなにも自然が豊かなのに、治安はいいし、快適な滞在に必要な生活水準は満たしているし、食べ物は美味しいし、人も気さくであたたかい。高知って、いろんな土地の「いいところの寄せ集め」だなって思ったんです」
「もっともっと、高知のことを知りたい!」その想いを結実させるため、前田さんは、地元タウン誌の編集部に就職。県内のあちこちをかけずり回り、いろいろな人から話を聞く仕事はやりがいがあった。
「思っちょった通り、知れば知るほど高知は面白かったがです。だからこそ、だんだん「この素晴らしさを県外の人にも知ってもらいたい」と思うようになっていきました」
でも、自分が手がけているのはあくまで県内で暮らす人のためのメディアだ。もしかして、私がやりたいことは全国誌にあるのだろうか? いや、それもまた違う気がする―。

気づけばタウン誌の編集職についてから8年半が経過し、前田さんは副編集長となっていた。そのときの年齢、30歳手前。もともと「30代になったら過去の経験をつないでひとつの形にする」と心に決めていた。何か新しいことを始めたい。それなら……、
「高知の文化や情報が集まるゲストハウスを作ろう、と思いました。長くタウン誌で働いていたから、ゲストに高知の情報をたくさん教えてあげられるし、対面なら、相手の反応を目の前で感じられる魅力がある、と思ったんです。さらにありがたいことに手元には、亡くなった祖父母が遺した家がありました」
こうして、かつおゲストハウスは誕生した。コンセプトは「高知大使館」。バックパッカー時代、困ったとき、情報がほしいとき、駆け込み寺的存在だった日本大使館。あの安心感を、高知に訪れる旅人たちに提供したいという想いを込めた。
人との関わりこそが「好き」を生み出す秘訣

空間作りにおいて意識した点をあえてひとつあげるならば、「テーブルの形を掘りごたつにしたこと」だという。たしかに、かつおゲストハウスの団欒スペースには、旧館・新館共に大きな掘りごたつがある。
高知出身アーティストの作品でもなく、高知の素材を使った建具でもなく、高知の情報コーナーでもなく、「掘りごたつ」を一番にあげたのには、こんな理由があった。
「この形って人が集まりやすいんです。外国人ゲストも座りやすいし、座る位置も人数も決まっていないから、自由に座れるでしょう?」
掘りごたつの形にすることで、コミュニケーションを生むことを意識しているのだ。前田さんは、交流こそが旅に深みを増し、その土地を「好き」になる強力なブースターになると信じている。
その背景は、バックパッカー時代に彼女が訪れた、エジプトの日本人宿での経験がある。たくさんの日本人が集まるその宿では、宿泊者同士でこんな情報交換が行われていた。「あの観光地の未公開ゾーンに入れる裏ルートがあるらしい」「深夜、某看守に賄賂を渡すと入れるらしい」―。
「そういう情報って、メディアでは絶対に出ないじゃないですか。でも、そのウソとも本当ともつかない情報のほうが、旅を面白くしてくれたりする。しかもゲストハウスなら、その旅や人生を共にする仲間も見つけられるかもしれない。私は、それこそがゲストハウスの醍醐味だと思っているんです」
だからかつおゲストハウスでは、意識してコミュニケーションを起こすようにしているという。スタートは、スタッフがゲストに「お茶でもいかが?」と声をかけるところから。高知産のお茶菓子をつまみながらお喋りしていると、ひとりふたりと人数が増えてくる。時にはゲスト同士話が盛り上がって「これから飲みに行こう!」となることもあるそうだ。
こうして必要な情報や仲間をこの空間で仕入れることで、高知を楽しみ尽くしてもらう。それがひいては、高知への「好き」を生み出すことにつながっているのだ。
「好き」は連鎖する

この空間で生まれた「好き」はまた、前田さん自身の「好き」も増幅させている。
というのも、飲みに出かけていたゲストから「1軒目のお店で隣に座ってたおじさんがおごってくれて、2軒目、3軒目も一緒にはしごして、最後スナックまで行ってきたんですよ~」という話を聞いたり、地元屋台が集まり昼間からお酒を飲む人でにぎわう高知の名所・ひろめ市場に行ったゲストからは「全然知らない人の結婚式の二次会に行ってきました」と報告を受けたり、ゲストと一緒に飲んでいる高知の人から「酔っ払っちゃったみたいなので、送っていきます」と電話がかかってきたり……、
「どれだけ高知の民が、勝手におせっかいしゆうがやろう(してるんだろう)って! 高知県民全体で観光客をもてなしゆうんやなあって」
ゲストハウスを開いてからますます高知愛に拍車がかかった前田さん。現在では、高知の観光にも関わっている。その熱の入れようは「まだまだ知ってもらえていない魅力がたくさんある、くやしい」とこぼすほど。
「高知から愛媛に行くとき、高速バスで行ってしまうお客さんが多いんです。でも、時間があるなら、土讃線で窪川に行って、窪川から予土線(トロッコ列車)で四万十川の雄大な景色を見ながら途中下車し、四万十の幸を食べてから宇和島経由で松山に向かったほうが、旅がずっとドラマティックになるんですよ」
交通の便の悪さや、宿泊施設の少なさなどから、まだまだ高知市内がメインとなっている高知観光。歯がゆさを覚えた前田さんは、交通はさすがに手をつけられないが、宿泊施設のことなら、ということで、2018年5月、四万十川の近くに、かつおゲストハウスの姉妹店となる「かっぱバックパッカーズ」をオープンさせた。この場所からきっとまた、新たな高知ファンが生まれていくのだろう。
今、あなたが好きな趣味も、仕事も、人も、ひとつでも条件が揃わなかったら好きにならなかったかもしれない。だけど、誰かの「好き」という気持ちは、そんな奇跡を増やすことができるのではないだろうか。
地元・高知への「好き」を追いかけ、さらに周りへ広げる存在となった前田さんの姿は、そんなことを感じさせてくれた。
坂口ナオ
東京都在住のフリーライター。2013年より「旅」や「ローカル」をメインテーマに、webと紙面での執筆活動を開始。2015年に編集者として企業に所属したのち、2018年に再びライターとして独立。日本各地のユニークな取り組みや伝統などの取材を手がけている。
- 関連記事
- 元ナースが農業で看取る最期 組織をぬけてつくり続ける「冬のスイカ」
- 『高知家』って何? 人と人との繋がりでひとつの大家族を目指す
- 生まれ育った高知へ。「自分らしい人生」を生きられる地元に12年ぶりにUターン
- 曖昧な場所としての「庭」へ 泊まれる古本屋「庭文庫」からの手紙
- 院内学級と普通学級を繋ぐ分身ロボ「オリヒメ」―米子市立就将小学校 上村校長に聞く