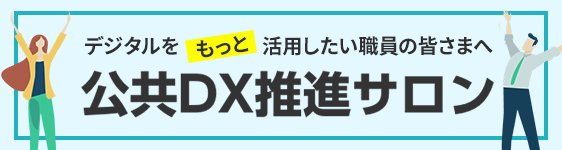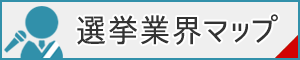英文契約書から考える予防法務 (2018/8/20 企業法務ナビ)
はじめに
これから海外企業とビジネスを開始したいと考えている起業家・事業者の方も多いと思います。しかし、アメリカをはじめとして契約社会といわれる国は少なくありません。契約は「当事者同士の法」ともいわれるほど強い拘束力を持つものです。したがって日本でビジネスをするよりも、一段と強く「法務」の観点を持って取引する必要があります。

国際取引・海外ビジネスに必要な法的観点
海外企業と取引する場合、契約書の内容に留意する必要があります。何故なら、契約書には損害賠償の規定や目的物滅失の場合の処理、どこの国の法律が適用されるか、どこの国に裁判管轄があるか等が定められていることが大多数だからです。全く留意せずに海外企業と取引をしてトラブルがあると、甚大な損失を被る危険性があるばかりか海外で裁判を受けることとなり大きな手間となります。
そこで、予防のためにも契約書のチェックが必要です。契約には、ライセンス契約、売買契約、秘密保持契約など様々あり、各企業の戦略に従って様々な条項が契約書に書かれますが、契約の基本的なリスクに焦点を当てて、注意すべき条項を紹介したいと思います。
英文契約書でチェックしたいこと
1.紛争解決の前提となる条項
(1)準拠法条項(Governing Law)
準拠法は、異なる国の企業同士で法的トラブルが生じた場合にどの国・地域の法律が適用されるかという問題において、様々な要素を考慮して最終的に適用される法律のことです。どの国・地域の法律によって契約が解釈されるかについては当事者の合意で決定できますが、準拠法条項は合意を具体化した規定と言えます。準拠法を知ることで、現地の法律を調査するか、現地の弁護士と事前にコンタクトを取るなどしてリスクに備えられます。
(2)裁判管轄合意(Jurisdiction)
「管轄合意」は国内の取引でも頻繁に行われますが、海外の取引においては「紛争解決条項(Settlement of Dispute)」という条項の中において、裁判管轄が記載されることがあります。したがってまずは見落としに注意すべきでしょう。仲裁条項(Arbitration)が併せて規定されることもあります。
予防法務の観点からすれば裁判沙汰にならないことが望ましいといえます。しかし、海外企業と紛争が起こらないとは限りません。準拠法と同じく、裁判管轄地を知ることで、現地の弁護士と事前にコンタクトを取るなどしてリスクに備えることができます。
2.責任に関する条項
(3)不可抗力条項(Force majeure)
契約締結後に当事者の帰責事由なく履行遅滞・履行不能が生じた場合、債務不履行責任を問われないとする内容です。なお、「majeure」は元々フランス語ですが、英語圏の契約書でもこの単語が使われるシーンが見受けられます。
不可抗力事由として、海外では天災以外にも戦争(war)・テロ(terro)・疫病(epidemic)などがあります。近年では先進国ですらテロの脅威にさらされ、取引を始めた先方の会社が現地から撤退するもしくは全く事業ができない状態ということも考えられます。「不可抗力事由」をしっかり把握する必要があるでしょう。
(4)危険負担条項(Risk / Risk of Loss)
同じ不可抗力による履行不能でも、売買契約の場合は危険負担として別途規定されることがあります。目的物を海外へ売ったり、海外から仕入れようとしたところ、貨物航空機・船舶等が事故を起こし、目的物が滅失するケースも珍しくありません。2009年にFedExの貨物航空便が成田空港で着陸失敗炎上した事故が思い出されるでしょう。
危険は「荷物が航空機・船舶に積まれた時(On Borad)」に売主から買主に移るケースが多く(FOB)、危険が自社にある場合は、危険を予め軽減・除去する措置が別途必要になります。特に代金に関しては保険で補填する方法があります。なお、保険費用が売買代金に含まれる取引形態もあります(CIF)。
(5)補償・損害賠償条項
リスクの核心とも言える条項です。帰責事由に基づき代金支払いや物品引渡しが遅れた場合、契約違反として債務不履行責任を負うことになりますが、難しいのはどこまでが相当因果関係(民法416条)のある損害か、すなわち「損害額」や「損害賠償の範囲」を確定することです。ましてや海外にまで及ぶと複雑化し算出は困難です。
そこで、契約書ではあらかじめ契約違反の場合の「損害額」や「範囲」を確定することがあります。国内取引と同じように(民法420条)、定められた額からリスクの度合いを把握する必要があると言えます。
補償条項は、当事者の一方が負担した損失・費用等の償還を相手方に請求することを認める条項のことです。損害賠償と異なり、発生原因が契約違反に限られず、当事者で定めることができます。海外でよく見られる例は製造物責任がある場合などです。
契約違反は債務不履行の規定で処理できますが、補償はどの国にも準拠法がありません。したがって、補償当事者、補償原因、補填されるべき損失、補償額の制限等につき、具体的に定め、既に定められている場合は具体的に精査する必要があると言えます。また、補償条項があれば、損害賠償条項が排斥されないかなど、条項が競合するような文言になっていないかチェックする必要があります。
(6)変更条項(Amendments)
契約締結時に想定していなかった事態が生じた場合、事後的に契約内容を変更できるという内容です。いわゆる日本民法における「事情変更の法理」を具体化した規定と言えます。日本国内の取引では事情変更の法理が適用されたケースは多くありませんが、英語圏企業との取引では、「約因(consideraion)」という相手企業への対価さえ支払えば、容易に契約を変更できてしまうケースが見られます。
リーマンショック、アラブ諸国の混乱に伴う石油価格の変動など様々な原因で海外の経済状況は変動し、中には予測できないものもあります。契約内容が自社に不利に変更される危険性を常に意識し、その予防を心掛ける必要があると言えます。
3.通則法
準拠法について両者で合意できず契約書に指定されないケースもあります。その場合どの国・地域の法律が適用されるのでしょうか。
これについては法の適用に関する通則法(通称「通則法」)が定めています。当事者が準拠法を指定していない場合、準拠法は「最密接関係地法」によると定めています(8条1項)。契約の時点において当該契約に最も関係の深い地つまり「最密接関係地」を準拠法とするという規定です。最密接関係地を決める方法として以下の方法があります。
(1)特徴的な給付
契約では「特徴的な給付」を当事者の一方のみが行うものであるときは、その給付を行う当事者の常居所地が「最密接関係地」と推定されます(8条2項)。
この「特徴的な給付」とは、ある法律行為を他の種類の法律行為から区別する基準となる給付のことを言います。具体例として、売買契約においては物品の引渡し、リース契約においてはリース物の引渡しが挙げられます。金銭はどの契約でも共通して支払われるので特徴的な給付とは言えません。
したがって物品給付を行う売主の常居所地が「最密接関係地」と推定されるということになります。
(2)不動産取引の場合
不動産を目的物とする法律行為の場合は、不動産の所在地が最密接関係地と推定されます(8条3項)。
コメント
世界の市場はライバルも多く、国際情勢に影響されて変動が激しいという特徴があります。その中で法的なリスクマネジメントを怠ったことによって損害を被ると、事業展開の継続にとって大きな痛手となります。したがって、海外企業とリスクなく取引をしていくためには、契約書の内容を精査することでリスクマネジメントを徹底し、予期しない損害を被らないようにすることが重要であると言えます。
- 関連記事
- 日本で国際仲裁2割、国際仲裁のメリットと注意点
- 米WDが東芝メモリ事業売却差止請求、合弁契約での注意点について
- 地方銀行がサポートする中小企業の海外支援
- 電子委任状と契約実務
- AIが変える業務のかたち