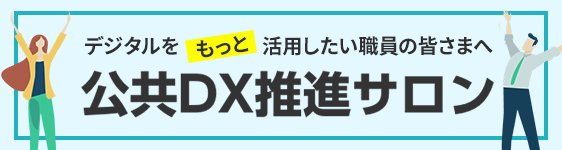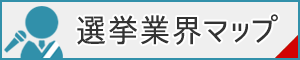平和の対価ってなんだろう? 少女の自分探しは自然体の「継承」に (2018/8/9 70seeds)
「戦争が経済を支えるなら、平和がそんな存在になってもいいはず」。
そう語るのは松永瑠衣子(まつなが・るいこ)さん。高校時代から学生を集めたイベントを開催したり、原発のリアルをめぐる映画『アトムとピース』(http://atomtopeace.com/)の主演も務めたりと、「活動」し続けてきた彼女はこの春、ひとつの決断をした。
「大好きな仕事だった」という教師を辞め、「平和」の価値を世に問うための道を歩き始めたのだ。その第一歩として、自分にとって身近な被爆者のことを「ひとりの人間」として、後世に残すための書籍を出すことから取り組む。
「デモも座り込みもできなかった」という彼女が見つめる、誰もが平和に「目に見える価値」を認める未来とは。

教師を辞めて「平和」を仕事に
――いきなりなんですが、「平和」を仕事にするってどういうことなんでしょう。
戦争に価値があると思ってお金を出したりそれで稼ぐ人がいるように、平和に価値があると思っている人がいてもいいと思うんです。
それは「平和を使ってお金を稼ぐ」ということじゃなくて、平和そのものに価値があるということ。
戦争産業があるんだったら、同じように平和に価値を認める人が増えていく、ということが起きる結果、そこに対価が発生していくというイメージです。
――小学校の先生のままでもできそうな気がしますが、学校の先生を辞めてまでやろうというのは?
私にはずっと私を探し続けている感覚があって。小学校の先生が果たして本当に自分に合っているのかがずっと疑問でした。
たしかに、子どもたちの人生に関われることは本当に幸せでした。
だけど、私の先生としての力が追いつかなくて、子どもたちや他の先生方に迷惑をかけてしまっているんじゃないかって気持ちもあって…。
――先生という仕事が嫌だったわけではないんですね。
そうですね。
もちろん、松永先生に続けて欲しいと言ってくださった先生方も多かったのですけど、「松永先生って本当にこのままでいいのかなぁ」と言われることもよくあったんです。
私も心の中では、きっかけがあれば辞めるんじゃないかと思っていて、それは他の先生には言えませんでしたね。

――その辞めるきっかけがあった?
自分が高校生の時からずっと目の前でお話しされていた被爆語り部の山口仙二さんや谷口稜曄さんが次々と亡くなっていったことです。
「あなたたちは私たちの戦争体験が聞ける最後の世代なんだよ」と言われたことがまさに今、目の前に来たんだって。
――ただ、学校の先生として平和を教えていく、という選択肢もあったのでは、と思います。
実は、子供の頃から受けていた平和教育にずっと疑問を持っていた、ということもあって。
――疑問というと。
私が子どもの頃受けた平和教育って、被爆者1人に対して何百人という生徒が被爆の話を聞くスタイルで被爆のことを教えられていたんですけど、あまりにも実感がなくて…。
被爆者の人がなんだか「超特別な存在」みたいに思えてしまうんです。
――たしかに、身近には感じづらいし、小学生の頃に受けた平和教育ってちょっと怖かったですよね。
今の平和教育だと、戦争ってかわいそう、その時代に生きていた人はかわいそうだから、戦争はいけないんだみたいな。
教科書に書かれていることをそのまま読みましたみたいな感想文しか出てこないんですよね。
でもそれってすごくもったいないことで、本当はもっと奥深いし、その人たちの人生を知ることができたら、自分の人生ももっと輝かしいものになると思うんです。
――これまでの「平和教育」とは少し違う視点のように感じます。そう考えるきっかけがあったんですか?
私が以前主演を務めた『アトムとピース』という、原発をテーマにした映画があったのですが、その時に出会ったある女性から受けた気づきがとても大きいんです。

「大間の敦子さん」との出会い
――映画の主演?女優もやっているんですか?
いえ、まったく笑。小学校の先生になって1年目のときに「映画に出ませんか?」って言われたんです。
高校のときに始めた環境活動のことや被爆三世であることだとか、いろんな条件が重なって声をかけていただいて。
――映画のオファーを受けたとき、どんな気持ちでしたか?
正直びびってました。テーマが原爆と原発ってめちゃめちゃ重たいし、絶対どちらかに寄っちゃうし。
政治的に、そうなることをすごく恐れていて、そうなるとやっぱり先生って公的に平等でいなきゃいけない立場だから、原発は反対だとか賛成だとか絶対言えない。
もちろん、私はそういうことを押し付けようとしてないけど、受け取り方によっては、そう思われても仕方がないかもしれない。
――そんな映画の出演で出会った、松永さんの価値観に影響を与えた女性ってどんな方だったんですか。
映画の中で、青森県の大間原発建設予定地(編集部注:2018年8月現在)にたった一人で暮らし続ける「あさこハウス」の敦子さんという方です。
それまでは、そこに住んでて、そこで困っている人たちの声ってなかなか聞くことができなかった。でも映画では伝えなきゃいけない。聞きにくいことも聞かなきゃいけない。
そんな中出会った彼女は、「(原発建設に)賛成している人の中にもやむを得ず家族を守るために賛成してる人だっている」って言ってたんです。

――反対運動をしている人なのに、賛成派を擁護する視点も持っていたんですね。
そう。その人たちを裏切り者とせずに「しょうがなくそうするしかなかったんだ」って誰よりもわかっていて。
だけど彼女は、反対活動を続けるんです。
自分たちが暮らし、大間と言う街を守るために1回原発が出来ちゃったら、生態系は崩れるし、放射能も海水とかに出ちゃったりするから、絶対影響がゼロなんてことはない。
――度できちゃったら誰も止められなくなるから、今自分たちが反対しておかないと、ほんとに一生取り返しがつかないことになる。
それを何百万とかお金を積まれても、何億も積まれても、金で買える話じゃないって。
――お金で環境は戻りませんからね…。
そして、敦子さんが言っていたことで印象に残っているのが次の言葉なんです。
「自分がデモとか参加するのすごく苦手。だけど私はここで暮らすことができる。ここで自分は目の前にあるおまけに原発がいつか事故になっていつか人の命を蝕む場所になったとしても、その敷地内で命のある暮らしをしていきたい。そこで畑を耕したいし、いろんな動物たちと一緒に住みたい」
私もデモとか座り込みとかすごく苦手で、高校生のときにもそういうことだけは絶対できませんて言って逃げ続けてきた。
そういう風に言ってくれる敦子さんの言葉がすごく入ってきて、「私は私にできることをやればいいんだ」って。

――松永さんにできること。
賛成とか反対っていうのを声を大にして言うことじゃなくても、事実を伝える。自分が見てきたものをちゃんと伝えるって言うこと。
それをただ自分が反対するんじゃなくて、現地の人が苦しい思いをしている今でもそうやって暮らしているというところをやっぱり伝えなきゃいけないって。
私は私のやり方で、被爆者の人たちが喜ぶことを。
――それがさっきの「被爆者の方の人生を知る」っていうことなんですね。
はい、それが簡単だけど目の前にいる人を大切にすることとか、子どもたちにそういう幸せに生きられる力を育てていくみたいなこと。
自分の教え子たちにもそうやって接してきたし、未来に自分の子どもができたとして、その子が幸せに生きられる方法を探し続けることがたぶん本当に被爆者の人たちが望んでいる世界だと思っていて。
――聞けば聞くほど、松永さんの感覚って「普通」なんですよね。「活動家」っぽくない。
だからこそ「自分らしくできること」っていうのを探しているのかもしれません。
私、小中学校時代は本当に学校がつまらなかったんですよ。中学三年のときにいじめにあったのもあって。

原点は中学時代、怖かったはずの姉の言葉
――いじめ、ですか。
中学三年生の時に、突然それで学校に行くのがつらくなってしまって…。
当時の私は家と学校にしか世界がなかったから、とても苦しくて、ご飯も毎日吐きだしてしまうほどでした。
――どうやって乗り越えたんですか?
お姉ちゃんが「学校、行かなくていいよ」って言ってくれたんです。当時お姉ちゃんはカンボジアのスタディーツアーから帰ってきたばかりで、そのときによく山や川に連れていってくれて。
――お姉さんとは仲が良かったんですか?
全然!喧嘩するし!お姉ちゃん自身も中学の頃いじめられていて、家族に対する態度とかもすごく怖かったんです(笑)。
こんなお姉ちゃん嫌だと思っていたくらい。しゃべってくれないし。

――それが妹を励ます側になったって不思議ですね笑。
お姉ちゃん自身がすごく変わったんだと思います。カンボジアで見たもの、得られたものとか、そこから学んだものがすごく大きかったんだろうなと。
――お姉さんはどんな話をしてくれたんですか?
「私たちはカンボジアに住んでいるゴミ山に暮らしている人たちをかわいそうだと思っていた。けど、その人たちにとってはそれが日常で、その暮らしの中で、面白いことや幸せを見つけているから、彼らにとって今の生活は幸せなんだ」
「私たちがそう思うのはほんとにかわいそうの押し売りみたい」って。
その話を聞いて、そういう風にしか感じられない自分たちの方が幸せではないのかな、不幸なんじゃないのかなと思いました。
――なるほど。
それで「あー、、自分が生きている世界ってほんとに狭いんだな」「学校じゃなくていいんだ。自分の家じゃなくてもいいんだ」って気づいて。
――その先に、今回の「平和を仕事にする」という決断があって…。
はい。ずっと探し続けてきた「自分にできること」のひとつの答えが、「被爆者の人生を伝える」ことだったんです。
そのことに気づくきっかけになったのが映画「この世界の片隅に」でした。

継承は「他の誰かの人生を知ること」でいい
――『この世界の片隅に』は原爆のことを扱っていながら、決してメインではないですよね。
被爆の継承って難しいんですよ。
その人に成り代わって原爆の話を話すことができるけれども、やっぱりその人の経験っていうのはその人の経験でしかなくて、私が谷口さんの話をしたとしても、人々に伝わるの1/1000くらい。
その生きてる人、目の前で話している人にしか伝えられないことなんだって。
かといって、その人が死んでしまったら被爆の継承がなくなってしまうのか、いや他にも方法があるはずと思っていたときに出会ったのが『この世界の片隅に』でした。

――たしかに、『この世界の片隅に』のすずさんは普通に暮らしていましたよね。
そう!あの映画を見た時に「これ、私のおばあちゃんだ!」って思ったんです。片淵監督が大切にしていたのはありふれた日常。
すずさんが主人公なんだけれども、監督が描きたかったものはすずさんという1人の人間だけじゃなくて、その時代に、その世界に生きていたい人たち一人ひとりを描きたかったんだっていうことに気づいたんです。
原爆が落ちる直前まで生きていた人たちが、命からがら生きてくれて、命を繋いでくれた…。
だから、あの中に私のおばあちゃんがいたんだって自己解釈したんです笑
――それが監督が描きたかったものなんですね。
一度、片渕監督にお会いする機会があって聞いてみたんです。「監督はあのとき、あの世界に住んでいる一人一人の人生を描きたいと思ったんですか」って。
そしたら、監督が「そう!そうなんです!」って大きく頷いてくれました。
――そこが通じ合うのはうれしいですね!
私はさらにそこから一歩踏み込んで、監督の描きたかったその時代に生きていた人たち、私たち一人一人が命をつないでもらった人たちを知るきっかけを作りたいと思ったんですよね。
私にとって戦争があったのは8月9日だけど、東京には東京大空襲があったし、佐世保にも福岡にも空襲があったりしてて、それぞれの街の戦争体験者がいて、その人たち一人ひとりの人生がある。それを知ることが本当の被爆の継承になるかなって。
戦争体験者の命を自分たちが受け取ることが必要なんだと思います。

――それが、今度出版する書籍のことにもつながっていくんですね。
本当はいろいろな被爆者の方の人生を知って欲しいんだけれども、物語の趣旨がいろいろずれてきちゃうから、あえて私のおばあちゃんのスエ子さんと、被爆語り部の下平作江さんの二人の人生に絞ってお伝えしようと思っています。
自分と同じ性別の女性で自分の本当に命をつないでくれたおばあちゃんであるスエ子さんと、自分の人生を変えてくれた存在でもある、初めて対面で被爆者として語ってくれた下平作江さん。
――どうして、その二人に決めたのですか?
2人はある意味とても対照的で。
スエ子さんはずっと被爆者であることを隠していました。商売人として差別を受けることを恐れて、被爆者手帳もとらなかったそうです。
私のお父さん、スエ子さんの息子にも、差別が及ばないようにするために、結婚するまで自分が被爆者であることを隠していたんです。
作江さんは原爆で家族を失い、妹の自殺を乗り越えながらも生き延びて、被爆者として自分たちの経験を語り継いでいかないとまた同じことが起きるかもしれないという使命感を持って自分が被爆者であることを発信し続けていたんです。
――それぞれ本当に対照的な生き方をされてきたんですね。
私のおばあちゃんは自分の家族を守るために被爆のことを伝えることができなかった。
そういう声なき声があるっていうのも伝えなきゃいけなかったし、伝える一歩を踏み出す人がいたから、被爆者手帳が発行されるようになった。
原爆の恐ろしさを伝え続けることも、私たちの暮らしを守ってくれることも、どっちも大事で、その2人を、本当に対極にいる2人を描くことに意味があると思うんです。作江さんは戦争孤児だけど、うちのおばあちゃんの両親は生きてたし、子供も生きてましたし。
――書籍ができてからが次のスタートになると思うんですが、松永さんはこれからどんなことに取り組んでいくんですか。
もちろん出版はゴールじゃなくて、その本を使って小学校だけじゃなくて、企業とかいろんな人に本を読んでもらうとか。
戦争体験の継承ということを重く捉えずに、「おばあちゃんの人生を知る」とか、自分ではない他の人生を知るときの1つのツールになればと。

――その活動は続けていくのですか?
ずっとやっていきたいと思っています。高校生もそうだし、中学生にも小学生にも大学生にも、いろんな人たちに使って欲しいなと思っています。
それが、自分が今までやってきた平和のことを1つの形にするということだと思います。
それに「価値がある」と思ってくれる人が増えたら1番いいのかもしれないですね。
――最初にあった、「平和が産業になる」ことですね。
そう思っているし、それをできる人になりたいと思っています。
例えば、ここでピースフェスを開くとか、価値を感じてもらえるなら、その入り口は何でもいいと思ってて。
別に「イケメンが平和のことやってる、私もやろう!」みたいな(笑)そういう関係ないようない入り口でも良いと思ってて。
でもそこから考えるきっかけになれば、これからの社会を作っていく若い人たちに届けばいいな、若い人たちが自分の意思で未来を選択していくためのツールを作っていきたいなと思っています。
北 祐介
和洋折衷を愛するハットとハッピがトレードマークの男。気になったことにはまっしぐら。全国ウロウロしつつ、和光の自室を解放して同じく全国ウロウロしている民と暮らす。 1995年、福岡出身。パインアメが通貨です。
岡山 史興
70Seeds編集長。「できごとのじぶんごと化」をミッションに、世の中のさまざまな「編集」に取り組んでいます。
- 関連記事
- 武器からアクセサリーを作る カンボジアで蒔く「心の復興」の種
- “思い出したくない日”を語る生き様に触れて―25歳の被爆3世を突き動かすもの
- 戦争が祖父に与えたもの―夢を抱き満州へ旅立った少年の記憶を辿る
- 沖縄にわかりやすい「敵」はいない―テレビ的映像から離れて描くドキュメンタリー「風かたか」
- [新潟・長岡市]1人でも多くの人に読んでほしい…文さんの体験