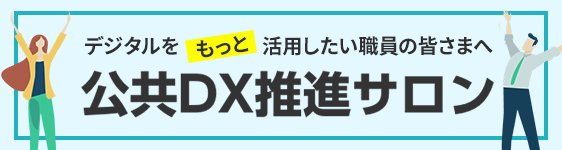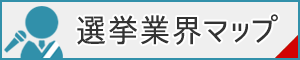「独身税」という意見で波紋 結婚が重負担という現状の打開策は? (2017/9/24 JIJICO)
独身税の議論が話題に
北國新聞が配信した記事がネットで話題になっています(参考:かほく市ママ課「独身税」提案 財務省主計官と懇談)。
実際には、石川県かほく市で8月末に開かれた「かほく市ママ課」と財務省主計官阿久澤氏の意見交換会で、参加した女性メンバーから「結婚し子を育てると生活水準が下がる。独身者に負担をお願いできないか」という質問があり、阿久澤氏は「確かに独身税の議論はあるが、進んでいない」と述べるやり取りが行われただけのようです。
ところが、まるで既婚で子育て中の女性が、自らの生活水準を維持するために独身税の導入を提案したかのように受け取る人が後を絶たず、「独身者に対する逆差別だ」という非難が出ています。

この意見交換会で本当に「独身税」の導入が議論されたかどうかは別として、「独身税」という聞き慣れない言葉が出てきている背景には、税負担、未婚率の上昇、少子化そして過疎化など現代社会が抱える問題点が隠されています。そこで、「独身税」を入口にして、こうした諸問題の解決のために、本質的にどのような視点を持つ必要があるのかについて、3つの視点からアプローチしていきたいと思います。
税制から見た「独身税」の是非
一つ目は、税制の視点です。「子育て中の夫婦世帯への経済的支援」として独身税を新設するという新たな政策を実現するためには、同時に新たな財源が必要になるという考え方で、旧態依然とした役所的発想と言えます。もし本当に「子育て中の夫婦世帯への経済的支援」をしたいのならば、税金を徴収して給付するという面倒な手続きを踏まず、該当する世帯へ「減税措置」をとる方が、行政コストも安上がりですし、実質的な効果も変わらないはずです。
独身税は、今回新たに出てきた税金ではなく、日本では2004年に自民党の子育て小委員会が提案したことで広く知れ渡りました。世界的に見ると、ブルガリアで1968~1989年まで導入されていた実績があります。ただし、ブルガリアが独身税を導入した目的は、独身者から徴収した税金を子育て中の世帯へ再配分して、子持ち家庭の生活水準を維持するためではありません。ブルガリアでは、1960年代から少子化が進行していたために、将来的に労働力人口が不足することが懸念されていました。
そこで、独身者に収入の5~10%という高率な独身税を課し、早期に結婚に踏み切ることを促すことが目的でした。そういう意味では、今回話題にあがっている独身税とは目指すところが異なります。しかも、ブルガリアの場合、出生率は上がらずむしろ下がりました。高率な独身税が、独身者の可処分所得を下げ、結婚への準備にマイナスになったことが原因と言われています。
税金というものは、基本的に受益者負担という要素がなければ、支払う側にインセンティブが働きません。ブルガリアで導入した独身税は、インセンティブが働かないペナルティとしての税金ですから、その点においても独身税が意図した成果が上げられなかった可能性があります。同様に、今回日本で話題となっている独身税にも受益者負担という要素がまったくなく、独身者に対してペナルティとしてしか機能しないため、おそらく期待する導入効果は得られないと思われます。
首都と地方 安易なばらまき行政での部分最適は本当に有効か?
二つ目は、首都と地方という視点です。今回、話題の舞台となった石川県かほく市は、住宅取得、家賃、子育て支援などの面で補助金や行政サービスが手厚い街で、東洋経済新報社が2017年6月20日に公表した「住みよさランキング2017」で全国4位にランクしています。
しかし同時に、2014年民間シンクタンクの日本創成会議がまとめた全国の「消滅可能性都市」896市町村に、かほく市はリストされています。そのため、同市は少子高齢化が進む将来を見越し、住民の減少が大きくなると市そのものの存続が危ぶまれることから、「日本一ママにやさしい街」というスローガンを掲げて、住民の誘致に力を入れています。「ママ課プロジェクト」も、そうした一連の動きの中で創設されました。
ここで考えなければならないことは、各地方自治体が税金をかけ街の魅力度をアピールする住民の誘致合戦に、どれだけ意味があるかということです。少子高齢化が進めば、現在の行政サービスを維持するために必要な住民数を維持できなくなる地方自治体が現れるのは、残念ながら当然のことです。しかしながら、こうした部分最適を目指す活動が、全体最適で考えればマイナスになる可能性に目を向けるべきでしょう。自分の街だけ存続できれば良いという話ではないということです。
日本全体では、この先少子高齢化に伴い労働生産人口が減少し、GDPが伸び悩むどころか減少する可能性があります。その解決策のために、人口を増やすだけではなく、労働生産性を上げることが重要な課題になっています。労働生産性を向上させるために着目すべき要素は複数ありますが、首都と地方という視点があります。
現在の安倍政権は、「地方創生」を掲げ、東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけ、日本全体の活力を上げるというストーリーを描いています。一方で、デービット・アトキンソン氏は『新・所得倍増論』の中で、ドイツを除くEU諸国では、「その国の首都の生産性が、国全体の生産性を引き上げている」という相関関係を主張しています。
EU最高の生産性を誇るロンドンでは、一人当たり1000万円の生産性を上げていますが、これは英国全体の平均値の約3倍に相当します。一方で、東京はどうかというと、700万円で、全国平均の約1.75倍に過ぎません。一極集中と言われている首都の生産性を上げることに鍵があるとするなら、地方を生かすためにも、地方自治体がそれぞれ部分最適を考えて活動する以上に、国全体として首都の生産性を倍増する方が、急がば回れで効果的である可能性が高いのです。
地方自治体が独自に部分最適を図ると、必ず結果としての勝ち負けが生じます。つまり、税金を使って各種施策を打っても、住民が増える街と増えない街に二極化するということです。そうなると、使われた税金の中で意味があった金とそうでなかった金が出てきてしまいまい、限られた税金の効果的な使用という面から無駄が生じることになります。
そうならないために、地方創生を考えるときに、東京の生産性向上によって、結果的に地方の生産性が底上げされ、住民が減少しながらも地方自治体が存続できる道もあることを認識し、政府も与党の選挙対策に繋がりかねない安易なばらまき行政を控える必要があります。
世帯収入を増加させるために本来やるべきこととは?
三つ目は、世帯収入の増加という視点です。そもそも、かほく市の意見交換会で「結婚し子を育てると生活水準が下がる」ことを理由に、独身税が話題となったと報じられています。問題は、その解決を独身税で行うことが妥当なのか、それ以外にも適切な方法があるのかということです。
たしかに、日本の未婚率の高さや結婚後の出生率の低さの根底には、経済的な不安があります。内閣府が行った平成25年度版『家族と地域における子育てに関する意識調査』を見ても、結婚の希望を持ちながら実際に結婚していない理由のうち最も多いものは、男性の場合「経済的な余裕がない」女性の場合「希望の条件に合う人がいない」になっています。女性の場合、「希望の条件」の中で年収が占める割合が多いので、総じて男女ともに経済的な問題が未婚率を高めている可能性が否めません。
少子高齢化が進行し総人口が減少し始めている日本において、婚姻率を高め、出生率を高めていくことが、国家的に重要なテーマであることは間違いありません。ただし、その方法として、かほく市のように育児を女性の役割として特別視して「日本一ママにやさしい街」を標榜し、「ママ課プロジェクト」を起ち上げることには疑問があります。
たとえば日本では、通勤電車に「女性専用車」を設けることに象徴されるように、「女性を特別視して大切にしなければならない」という思想が強いのですが、それは本当の意味での男女平等の実現を妨げています。先日、イギリスでも電車内の性犯罪対策として女性専用車の復活が話題になりましたが、日本とは異なり多くの批判の声があがりました。「性犯罪に対する抜本的対策を諦めたことになる」「むしろ、犯罪を常態化することに繋がる」「男性には自分自身を抑制できないという発想にもとづいており、逆差別だ」といった声です。
では、具体的に事の発端となった生活水準について見ていきましょう。日本の場合、「男は外で働いて、女は家庭を守る」という長年に渡り無意識に刷り込まれた家族内のロールモデルが根強いために、男性が家事や育児に協力的ではありません。その結果、女性は結婚して子供を産むと、一時的に仕事を辞め、復職時もフルタイムの正社員の仕事は避け、家事の負担に耐えながらできる非正規社員の仕事に就く女性が多いために、夫婦間で妻の収入が大幅に減少することで、「生活水準が下がる」という不満に繋がってくるのです。
実際のところ、女性の就労率は低くありません。『男女共同参画白書平成27年度版』のよると、平成26年は20代から50代前半までの各世代の就労率が70%を越えています。しかし、女性の収入レベルはというと、20代までは男性の8割程度の水準ですが、30歳を過ぎると急激に格差が広がり、50代後半では男性の4割程度まで下がってしまうことが、国税庁のデータを見るとわかります。ただし、女性の収入が低い理由は、同一労働をしているのに同一賃金が貰えていないのではなく、最初から賃金水準に見合った仕事しかしていない女性が多いところに問題の本質があります。
日本の女性労働者の多くが、付加価値が高い仕事をしていない状況があることが分かりました。なぜ、このような事態になっているかと言うと、日本人女性の能力が低いからではありません。日本社会が持っている家族内のロールモデルに原因があるのです。具体的には、中心的な働き手は現役世代の男性を基本として、その男性は家庭持ちで世帯主であることを想定しています。それ以外の労働力、例えば女性や高齢者については、パートや嘱託といった周辺的な労働力に位置付けられ、家計においても重要な収入源ではなく、あくまでも補完的収入であることも想定されています。しかし、男性の収入が伸び悩む状況になると、もはや女性の収入を周辺的かつ補完的に位置付けていては、世帯全体の収入を増やすことが難しくなってきたのです。
この問題の解決のためには、同一労働同一賃金の先進国であるスウェーデンの例が参考になります。スウェーデンは労働力不足解消のために、保育支援策を積極的に推進することで、女性の社会進出に成功した国の一つです。そのとき重要なポイントになったことは、家族内のロールモデルを変化させることです。同国も男性は外で仕事、女性家庭を守るという考え方が強かったのですが、積極的にその因習を変えていった結果、現在では掃除や食事の支度が妻の仕事であるとする割合が50%を切るまでになっています。ちなみに、日本では、掃除85.5%食事の支度89.7%が妻の仕事だと考えている状況のままです。
以上のことから、家族内のロールモデルを変え、同一労働同一賃金を女性の仕事においても実現することが、結婚している世帯の経済的不安を軽減するために必要であることが、お分かりいただけたと思います。しかし、それを実現するためには、税制についても考えなければなりません。
日本の女性が、周辺的労働力に留まっているその他の原因に、「配偶者控除」があります。これは、1961年池田内閣の時に創設されましたが、夫が正社員として働き、妻は専業主婦として家事に努めるという従来型の家族モデルから導き出された制度です。夫の扶養に留まりながら103万円の範囲内で仕事をするという妻の就労スタイルが、女性と男性が同一労働をしていないことに繋がっています。
2018年から配偶者控除のボーダーラインが103万円から150万円に引き上げられ、配偶者特別控除についても適用基準が引き上げられることが決定していますが、これによって根本的に問題が解決するわけではありません。あくまでも過渡的措置とすべきです。
もし本気で女性をその能力に見合った仕事の担い手として期待するならば、最終的に配偶者控除を廃止することが望ましく、その分で増加した税収を子育て支援に振り替えれば、女性就労を質と量の両面で促進する効果が期待できるはずです。
- 著者プロフィール
-

清水 泰志/経営コンサルタント
黒字企業の高みへ!極みと未来シナリオで競争しない企業に導く
競争優位を目指す経営から、独占優位を確立する経営への転換をサポート。業種を問わず、さらに経営が安定するとともに、次の経営戦略を自ら生み出す力もつく。会社経営の経験があるため経営者の気持ちに寄り添える。
- 関連記事
- かほく市ママ課「独身税」提案 財務省主計官と懇談
- 独身アラフォー女性の40%は非正規!老後はどうなる?
- 「女性議員の妊娠」が問いかけること―地方議員が本音で語るWOMAN SHIFT座談会(前編)
- 女性の残業時間が少ない業界1位は「病院」 では有休消化率が高い業界は?
- 東京から「消滅可能性都市」に移住したけど、意外と不便じゃなかった件