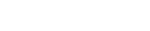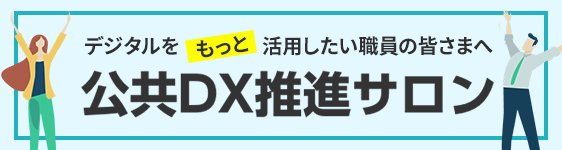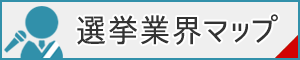再犯者の7割は無職―職親プロジェクトで再犯者率の上昇に歯止めを (2018/7/3 政治山)
7月は「再犯防止啓発月間」、法務省は企業や団体と連携しながらPRイベントや情報発信を行っています。一般刑法犯の検挙人員数は減少傾向にあるものの、検挙人員に占める再犯者の割合=再犯者率は上昇を続けており、再犯防止は喫緊の課題と言えます。
そこで、2013年に「日本財団職親プロジェクト」を発足させ、再犯防止に取り組んできた日本財団ソーシャルイノベーション本部公益事業部の廣瀬正典氏にお話をうかがいました。
――はじめに、職親プロジェクト設立の背景をお聞かせください。
日本の検挙人員数は2004年の389,027件から減少し続けている一方で、再犯者率(1年間の逮捕者のうち、犯罪件数が2回目以上の者)が1996年27.7%から2016年48.7%まで下がることなく上昇を続け、罪を犯した人のうち、約2人に1人が再犯をしている計算となります。
また、再犯者の70%が無職で、再犯時の有職者に対する無職者の数は約4倍の人数となっていることから、再犯の防止には「職」が重要であること明らかでした。
そこで、刑務所出所者や少年院出院者の再犯防止を目指して、2013年2月に「日本財団職親プロジェクト」を発足させ、官と民が連携し、矯正施設在所中における更生支援のためのプログラムや、出所・出院後の就労体験および教育を提供することで、円滑な社会復帰を支援しています。
――具体的には、どのような支援を行っているのでしょうか。
勤労意欲の高い初犯者(一部の犯罪を除く)を対象に、矯正施設内で採用活動を行い、就労体験の機会を提供するとともに、当初は対象者を受け入れた企業に対して月8万円×6カ月、48万円を支援金として支給しました。
当初は5年で100人の雇用を目標としていましたが4年目で達成したため、現在は職場定着率の引き上げと受け入れ企業の増加、職種の多様化を目指しています。
――確かに、せっかく就労の機会を得ても、定着しないと無職になってしまいます。
はい、そして犯罪件数として、無職の方が罪を犯す割合は有職の方の約4倍にまで及ぶ、という統計があります。日本財団職親プロジェクトでは、再犯防止のためには職場に定着することが重要だと考えており、その視点として2点説明いたします。
1つ目に、職親プロジェクト参加企業(以下、「職親企業」)が、対象者の公私に渡り、自立更正に向けて見守っていく姿勢です。職親企業は、まさに「職の親」となり、時間や私財を投じて、対象者と向き合っています。対象者に裏切られることも少なくないですが、受け入れ企業が我慢強く耐え、それを乗り越えて築かれた関係性は固く、対象者からの信頼も強くなることから、再犯防止において非常に重要なポイントとなっていると思います。
2つ目に、対象者の社会人としての素養を育成する、教育の提供です。少年院等でも教育は提供されておりますが、日本財団職親プロジェクトで提供する教育は、社会人としての職場定着の視点に特化している点が特色です。現在、大阪拠点、福岡拠点にて、職親企業に就職した対象者の一部に対し教育提供を実施していますが、教育を受けていない対象者の平均継続期間は3.81カ月、一方で教育支援を受けた者の平均は9.24カ月と大きな差が表れました。教育提供を行った対象者の母数が少ないため、未だ検証が必要ではありますが、教育支援の効果を測っていきたいと考えています。
――目標数値やその他の展開について、どのようにお考えでしょうか。
これからの目標として、就労6カ月以降の職場定着率を65%から80%に、東京・大阪・福岡拠点の参加企業を合計90社にすることを目指しています。また、女性も就業しやすい職種を増やすなどの環境整備、矯正施設内での教育プログラム構築や職親企業と連携した新たな就労支援プログラム構築、再犯防止を目的とした職親プロジェクト参加企業間での転職サポートなど、切れ目のない支援を展開する予定です。

日本財団ソーシャルイノベーション本部公益事業部の廣瀬正典さん
――官民が連携して取り組むとのことですが、国はどのような役割を果たしているのでしょうか。
国は、刑務所出所者等を積極的に雇用する「協力雇用主制度」を整備し、雇用した企業への様々な補助を実施しています。職親プロジェクト発足以来、法務省をはじめとした各方面への働きかけは継続して行っており、2015年4月には法務省が「刑務所出所者等就労奨励金制度」を構築し、協力雇用主への支援を開始しました。
この制度では雇用開始から6カ月間は月額最大8万円、7カ月目から12カ月目の間は3カ月ごとに12万円、年間最大72万円を雇用主に支給しています。
――職親プロジェクトの支援金制度によく似ていますね。
私たちの取り組みが国の施策のモデルとなって施行されており、とても意義深いことだと思います。この制度発足に伴い、日本財団が実施していた支援金は終了と致しました。また、谷垣禎一氏や上川陽子氏ら歴代の法務大臣にも面会して要望書を提出してきましたが、現在も以下のような要望を行っています。
- イメージギャップによる離職→インターンや職場体験の拡充
- 就労意識と技術の低さ→矯正施設内での職業訓練の充実
- 就労後に依存症が発覚することによる離職→個人情報の一部開示
- コミュニケーション能力、金銭管理→継続的な教育支援
――このような支援が拡大していくためには、今後どのような取り組みが必要とお考えですか。
まずはモデルとなる矯正施設で、新たなプログラムを実証したいと考えています。すでに東京多摩少年院、大阪加古川刑務所、福岡佐賀少年刑務所で取り組んでおり、実社会のニーズに繋がる訓練を出所前に実施し、出院・出所後に職親企業が親代わりとなって引き受ける、という一連の流れをつくっていきたいと考えています。また教育提供においては、さらに量・質ともに向上させるため、教育機関との連携も検討しています。
2016年に制定された再犯防止推進法では、地方自治自体の再犯防止活動の推進について言及があり、これらの施設の立地自治体や周辺自治体ならではの支援として、帰住先に悩む刑務所出所者等に向けた公営住宅の活用も考えていきたいです。また、入札時の加点や税制面で優遇したり、表彰制度や認定制度を活用することで、協力企業を増やしていけるのではないかと考えています。
このプロジェクトを続けていると、なぜ被害者ではなく加害者を支援するのか、という指摘を受けることがあります。私たちの目標は罪を再び繰り返さない再チャレンジできる社会づくりですが、これは新たな被害者を生み出さないことにも繋がります。もちろん未然に犯罪を防ぐ取り組みも大事ですが、罪を犯してしまう人の中に再犯者が多いという現実があります。再犯者を減らすことが犯罪被害者を減らすことに繋がると信じて、出院者・出所者の支援を拡大していきたいと思います。
- 関連記事
- 再犯防止を目指す職親プロジェクト、初の全国幹事会を大阪で開催
- 上川法務大臣、官民連携を強調―職親企業との意見交換にて
- 再犯防止を目指す職親プロジェクト―新潟県上越市に5番目の拠点
- 再犯防止を目指す職親プロジェクト4番目の拠点、和歌山に
- ソーシャルイノベーション関連記事一覧