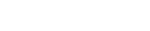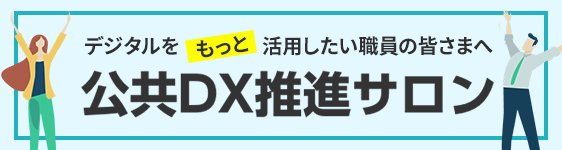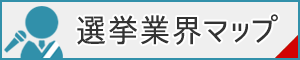安愚楽牧場に賠償命令、特定商品預託法について (2016/10/27 企業法務ナビ)
はじめに
和牛オーナー制度で全国から資金を集め、2011年に経営破綻した安愚楽牧場の元会員達が元社長ら3人を訴えた裁判で、東京地方裁判所は、20日、1億円余りの賠償を命じる判決を言い渡しました。また、元社長らは既に特定商品預託法違反(不実告知の禁止違反)の罪で実刑判決を受け確定しています。
そこで、今回は特定商品預託法とはどのような法律なのかみていきたいと思います。

事案の概要
安愚楽牧場は、「繁殖母牛に出資すれば毎年生まれる子牛の売却代金で多額のリターンが望める」という触れ込みで、全国の7万人以上の出資者から金を集める和牛オーナー制度の最大手でした。しかし、2011年におよそ4200億円の負債を抱えて経営破綻してしまいました。
元社長と元専務は、実際には保有する繁殖牛が少ないのにもかかわらず、1頭につき複数の番号を取り付けて頭数を水増しし、パンフレットにも「牛は本当にいます」と虚偽の記載や説明を行っていたことが特定商品預託法上の「不実の告知」違反の罪で実刑判決が確定しました。
今回の訴訟では、不起訴となった元役員を含める3名に対して賠償請求が行われ、20日の判決では、「保有する牛の数が不足していたにもかかわらず、会員には虚偽の説明をして、勧誘や契約の締結など組織的な違法行為を行った」等指摘し、原告が求めたとおり元社長ら3人に1億900万円余りの賠償を命じました。
特定商品預託法とは
特定商品や施設利用券の預託等取引契約に関する法律(通称:特定商品預託法)は、商品を販売しても顧客に現物を渡さず、その商品の運用、管理、保管などを行うと称して、一定期間預かり証等しか交付しない現物まがい商法を行った豊田商事事件を契機に1986年に制定されました。
貴金属など特定の商品を3カ月以上預かって利子などを支払う預託取引について、取引契約の締結及びその履行を公正にし、預託者が受けることのある損害の防止を図ることによって、預託者の利益の保護を図ることを目的としています(1条)。和牛を含む家畜類は97年に対象商品に追加されました。
契約にあたっては、契約内容を記した書面の交付、契約の締結又は更新についての勧誘の制限、不当な行為等の禁止、預託等取引契約の解除(クーリングオフ)などが明記され、預託等取引業者に対しては書類の閲覧、経済産業大臣による業務停止命令、報告及び立入検査などを定めています。また、書面の不交付など違反行為に対しては罰則を規定しています。
不実告知の禁止について
安愚楽牧場事件で問題となったのは、特定商品預託法4条1項「不実告知」違反です。不実告知とは、事実と異なることを認識しながら取引相手に対して真実とは異なる事実を告げることです。具体例としては、クーリングオフ期間を短く伝える、預託によって必ず儲かると断定的判断の提供を行う、預託対象商品の品質を偽る等が挙げられます。不実告知の禁止に違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられます。
不実告知の禁止については、他に消費者契約法、特定商取引法、宅建業法などでも定められています。
コメント
特定商品預託法は現物まがい商法対策として制定された法律ですので、個人を取引相手に預託対象物を扱う際には不実告知の禁止だけでなく、クーリングオフ期間等も遵守しなくてはなりません。実際に契約締結を行うのは担当部署ですので、企業法務としてはコンプライアンスの観点から、預託法上事業者に課せられる義務を担当者に周知させることが重要でしょう。
また、企業間取引においては、預託法をはじめ特商法などの法律は適用されず自己責任の下契約締結を行わなければなりません。従って、消費者同様契約締結前に事実確認等を行って検討する必要もあります。
- 関連記事
- 回答拒否に対する賠償責任を否定、弁護士会照会制度について
- 山陽自動車道トンネル事故で会社役員を起訴、「過労運転下命」とは
- 再雇用を巡りトヨタに賠償命令、継続雇用制度について
- 東芝の会計不祥事で株主が提訴、会計監査人の責任について
- 債務者の口座を裁判所が特定、民事執行法改正への動き