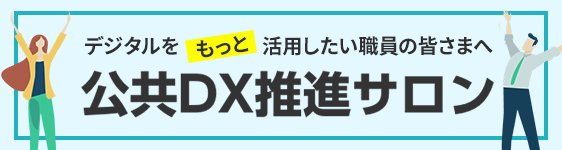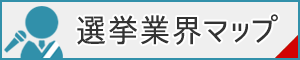「名こそ惜しけれ」の精神。日本人の倫理観はどこへ行ったのか。 (2016/5/30 co-media)
ちかごろは、日本人による、不名誉極まりない事件や不祥事が絶えません。
先日(2016年3月5日)、ウェブプロモーション事業を手掛ける某日本企業の社員など約20名が、社員研修先のタイの高級リゾート地・ホヒアンで全裸になって狂乱する騒ぎがありました。ホヒアンは王室ゆかりの神聖な場所でもあり、ホテルの従業員が狂乱を諌めたところ、社員たちは暴言を吐くなどして狂躁を続けたといいます。また同社はWebサービス事業者へ脅迫に近い高圧的な連絡をするなどして、事件による悪評の隠蔽を図ったともいいます。これをどのように見ても、まともな神経の振る舞いではありません。
この事件に限らず、近ごろは著名人による恥ずべき言動や、政治家の汚職の連続がニュースを賑わせています。これほどありがたみのない賑わいは他にありませんが、以下は嫌味ではなく、(むろん全員ではないが)我々日本人に、本来機能するべきであるはずのリミッターが外れてしまっているような印象を受けます。高いはずであった日本人の倫理観は、どこへ消えてしまったのでしょう。今回は、その“リミッター”を日本の歴史の中に見ていこうと思います。
坂東武者の精神
倫理というのは、人間が健全な社会生活を営むうえで不可欠なものでありながらも、必ずしも本能として備わっているものではありません。ゆえに私たちは訓練をしてこれを獲得し、門番のように使役して常に自分の言動を監視させねばなりません。
ただ、そのようにして個々人に任せきってしまうわけにもいかないため、どこの国でも法律と刑罰というものを運用し、個人の倫理というリミッターが外れた場合に備えています。また国や地域によっては、信仰が倫理として機能している場合もあります。
日本も、その長い歴史を通して独自の倫理観を育んできました。
「名こそ惜しけれ」という精神です。
日本史が、中国や朝鮮の歴史とまったく似ない歴史をたどりはじめるのは、鎌倉幕府という、素朴なリアリズムをよりどころにする“百姓”の政権が誕生してからである。私どもは、これを誇りにしたい。
かれらは、京の公家や寺社とはちがい、土着の倫理をもっていた。
「名こそ惜しけれ」
はずかしいことをするな、という坂東武者の精神は、その後の日本の非貴族階級につよい影響をあたえ、いまも一部のすがすがしい日本人の中で生きている。(『この国のかたち』)
坂東武士とは、箱根の坂より東、つまり関東地方に根を下ろした武士たちをおもに指します。
――自分の名を汚すような、恥ずかしいことはするな。
という、この極めて単純明快な思想は、平安の中頃、のちに“武士”と呼ばれる開墾農民たちの間に生まれました。この思想の起こりを説明するためには“武士”発生の起源から説き起こさねばなりませんが、要点を押さえつつもできるだけ簡潔に済むように努めるので、読者の皆さんにはいましばらくのお付き合いを願います。
武士の発生
武士の世が始まる前は、平安朝の国家も、奈良朝の国家も、ともに律令体制の世でした。
律令制とは、日本国の農地がみな公地であり日本国の民がみな公民であるという意味で、公民である農民は国家によって所有され、配分された公地を耕し、国の規定どおりの税としての稲を納めねばなりません。一種の一国社会主義であったと言っていいでしょう。
しかしこの体制では、国家として耕地面積が増えにくいので、奈良朝の八世紀半ばごろ、墾田という特例が設けられました。これにより、自ら開発した新田を国家のものとせずに個人で所有することができるようになりました。この墾田という例外的な私有田が、平安朝になって社会をかえてゆく契機となります。
後の世に「武士」と呼ばれる人たちは、もとはこの墾田という制度のもとで開墾した農地を私有した開発領主たちでした。
しかし、“私有”と言ってもあくまで律令体制下であるため、私有権を合法化するには京の公家や寺社勢力の名義が必要でした。もし公家や寺社が出来心をおこせば所有権はたちまち取り上げられてしまうため、開発領主たちは公家たちの機嫌を取り結ぶため、京に上って公家の番犬として無償で奉公しました。
また私有が公的なものでないため、仮に開発領地を奪い取ろうとするものが現れた場合や相続で揉めた場合、行政による介入や制止は期待できず、自力で土地を守るしかありませんでした。
坂東にあっては、血で血を洗うという。
理由は土地である。原因は、勃興してきた武士という新興階級の土地私有権が、国法のうえで認められていないところにある。さらにこの階級が若すぎるために、その相続法が私法として確立せず、多分にあいまいである点にも原因がある。(『義経』)
墾田の私有はこのようなきわどさの中でかろうじて成り立っており、このため開発領主たちは、自分の“一所”に対する私有権を“懸命”に主張しつづけねばなりませんでした。
この“私権の主張”は、様々な形で具象化しました。
たとえば、武士たちの甲冑です。
お国自慢ということではなく、中世以降の日本の甲冑は世界的に見てもその美しさは際立っています。小さな鉄板が色鮮やかな糸で縅(おど)され、色遣いのバリエーションも豊かで、赤糸縅、紫裾濃縅、萌黄匂縅など、そのいちいちが非常に華麗です。

この甲冑の華麗さは、私権の主張と無関係ではありません。「自分は他と違う」ということを、装飾でもって示したのです。『平家物語』は、武将が登場すると必ずそのいでたちを述べます。たとえば1184年に源義経が上洛し、後白河法皇に拝謁するときの様子を、以下のように描写しています。
九郎義経其の日の装束には、赤地錦の直垂(ひたたれ)に、紫裾濃(すそご)の鎧きて、鍬形うつたる甲の緒をしめ、こがねづくりの太刀をはき…
七五調の歯切れのよい文章から、匂い立つような凛々しい若武者の姿が目の前にありありと浮かんでくるようです。“私”の主張である装束は、何にも勝る人物描写になるのです。
名字と名田
“私権の主張”が強く現れているいまひとつの例が、かれらの“名”です。
現代では姓のことを指して「名字」と言いますが、姓と名字はもとはと言えば別物であり、名字とは本来、住所や名田などから付けられた名前を言います。たとえば足利尊氏は源氏の傍流であるため姓は源であるが、下野国足利庄を領したために足利という名字を名乗っている、というような具合です。
同じように、「敦盛最期」で有名な熊谷次郎直実は、現在の埼玉県熊谷市に名田を持っていました。猛暑のニュースで岐阜の多治見、群馬の館林とともにしばしば登場する、あの熊谷です。熊谷郷の田の主であるため、熊谷という名字を名乗りました。
鎌倉武士たちが合戦の最初に必ず名乗り合うのも、田の所有権を主張するためでした。熊谷の名字を名乗ることじたいが、熊谷郷の田園の所有者であることを顕示することになるのです。

須磨寺 源平の庭 海上へ去る平敦盛とそれを負う熊谷直実 posted by (C)メカ光
開発領主たちは ——くどいですが—— 私有田の地名を名字とし、その所有権をつねに主張している必要がありました。所領への私的執着というなまぐさい主張を、自分の名を公に晒しながら叫び続けねばなりませんでした。律令体制下における私田の所有というこのきわどい事情が、開発領主たちをして世間体に敏ならしめ、「名こそ惜しけれ」という独自の倫理観を生むに至ったことは想像に難くありません。
そして、この名誉希求の究極の表現が、戦場での「死への潔さ」でした。自分の名を声高に宣伝して戦う以上、敵に背を向けるような不名誉な振る舞いはできません。名を背負って戦う武士たちの脳裏には、つねに、
「命惜しむな、名こそ惜しめ」
という言葉が刻まれていました。先に述べた華麗な甲冑は、単なる防御の目的を越えて、自分の潔い死に様を美しく飾るための装飾でもあったのです。
ついでながら、源頼朝は「田をつくり、管理する者がその土地を所有する」という権利を認め、その権利を保障してやることで、所有権のあいまいさに怯え続けてきた開発領主たちの心を掴みました。やがて頼朝はこの開発領主 ——武士たち—— を鎌倉の地に結集させ、御恩と奉公の関係を結んで日本最初の武家政権を開きました。この場合の御恩とは領地を貰うことではなく、土地の所有権を公的に承認してもらうことでした。鎌倉幕府の成立が封建体制の幕開けとなり日本史の中で革命的であったことは、「開墾主に土地の所有を認める」というただこの一点によると言っても過言ではありません。
源平合戦にみえる潔さ
やや前後しますが、平安末期になると、こうした開発領主たちを束ねる存在として源氏と平氏が台頭し、熾烈で華麗な合戦が繰り広げられました。
源平合戦には、この「名こそ惜しけれ」の精神がそのまま結晶化したような見事な人物像が次々に登場し、読むたびに心が洗われるような清々しい気分になります。
鎌倉で語るべきものの第一は、武士たちの節義というものだろう。ついでかれらの死についてのいさぎよさといっていい。こればかりは、古今東西の歴史のなかできわだっている。(『街道をゆく』)
たとえば現在の神戸市須磨区でおこなわれた一ノ谷の合戦は「鵯越の逆落し」や、先の熊谷直実が登場する「敦盛最期」などの様々な逸話で有名ですが、文武に秀でた平家の公達・平忠度(ただのり)が命を散らせたのもこの戦いでした。
六野太はよい大将を討ち取ったとは思ったものの、名を誰とも知らなかったため、箙(えびら。矢を入れて右腰につける武具)に結び付けられている紙を取って見てみると「旅宿の花」という題の歌が詠まれていた。
ゆき暮れて 木の下かげを 宿とせば
花や今宵の あるじならまし
(旅路をゆくうちに日が暮れてきたので桜の木陰を宿とすることになってしまったが、心細くはない。花が今夜の主人となって私をもてなしてくれるであろうから。)
忠度と書き付けられていたので、この大将は薩摩守忠度だとわかった。六野太はおおいに喜び、首を高く差し上げて
「かの高名な薩摩守殿を、武蔵国の住人、岡辺六野太忠純が討ち取った」
と名乗りを上げた。敵も味方もこれを聞いて
「ああ、気の毒だ。武芸にも歌道にも優れた惜しむべき将軍を」
と、みな鎧の袖を涙で濡らした。(『平家物語』巻九より「忠度最期」を口語訳)
旅の情景を詠んだ美しい歌ですが、いますこし勘ぐれば、戦場で死を迎えてしまうかもしれないことを「ゆき暮れて木の下かげを宿とせば」と比喩し、そのような不意の戦死でも潔く受け入れる覚悟を「花や今宵のあるじならまし」と表しているとも読み取れます。忠度の辞世の句であると言っていいでしょう。
かれは箙に辞世の句を結びつけて戦場に赴き、勇ましく戦い、自らの死を華々しく飾りました。むろん最初から死ぬつもりで出陣したわけではありません。忠度の武人としての誇りが、いつ最期を迎えてもそれを受け入れる潔さと、後世まで語り継がれる華々しい死に様を憧憬する名誉心を与えているのでしょう。
また平忠度の潔さだけではなく、源平両軍が惜しい名将を失ったことを嘆き悲しむ様子にも非常な感銘を受けます。敵味方の域を越えて賞賛し合うすがすがしい光景は今日のスポーツなどでも時折見られますが、800年前の生死をかけた血なまぐさい戦場にすでにその光景が存在したというのは誇るべきことであると言えます。
また翌年の屋島の戦いにおいても、有名な「扇の的」など坂東武士たちの華々しい活躍が数多くありました。以下の「義経の弓流し」の話は知っておられる読者も少なくないのではないでしょうか。
源氏は勝ちに乗じて、馬の腹が浸かるほど海に乗り入れて平家軍を攻めた。源氏の兵たちが平家の舟から繰り出される熊手を太刀や薙刀で払い除けながら戦っていると、義経はどうしたことか弓を海に落としてしまった。義経はうつ伏して鞭でかき寄せながら、命を危険にさらしてまで拾おうとするので、味方の兵たちは
「お捨てなされ、お捨てなされ」
と言ったが、ついに拾い上げると、義経は笑いながら帰ってきた。
源氏の兵はみな呆れて、
「たとえ高価な武具であろうと、命には代えられません」
と言うと、義経は、
「弓が惜しくて拾ったのではない。私の弱い弓を敵が拾って、『これが源氏の総大将・九郎義経の弓か』などと嘲笑されるのが悔しいからこそ、命を賭けてでも拾ったのだ」
と言うと、皆またこれに感動した。(『平家物語』巻十一より「弓流」を口語訳)

源義経の作戦家・軍事指揮官としての能力は世界戦史の中でも際立っていますが、体格に恵まれなかったために個人的な武芸はさほど優れず、弓も張りの弱いものを用いていました。
弱弓が敵に知られれば、義経自身だけでなく率いている源氏軍をも辱めることになります。源氏の武者たちは、命を懸けて自分たちの名誉を守ろうとした大将の姿勢に感動し、義経のためならば命も惜しくはないと一層奮起しました。
「命惜しむな、名こそ惜しめ」という鎌倉武士の思想をまさに象徴する逸話です。
源平合戦における武将たちの潔さは、平家物語や義経記などを通して後世に語り継がれ、目指すべき理想の人間像として人々の意識に強く根付きました。
室町、戦国期になると名字と名田の関連性はほとんど失われ、さらに江戸期に入ると武士は土地の代わりに俸禄米をもらう知行制による支配体制に移行したため、武士たちは私有地への所有権を主張する必要はなくなりました。
しかし、海水が干上がって塩が残るように、「名こそ惜しけれ」の精神は武士の本質として残り、かれらの倫理観や美意識となって江戸期の武士たちに受け継がれました。
人間の芸術品
先に私は、倫理というリミッターが外れた際の備えとして刑法があると述べました。日本のある時期のある地域では、ひとびとの倫理的意識が高すぎるために刑法すら必要なくなるという信じがたい状況が発生しました。
薩摩の島津氏は鎌倉以来の古い家柄で、伝承では頼朝の時代に九州に下向したといいます。
島津家というのは非常に魅力的な家で、どの時代にあってもめざましい活躍をしています。たとえば戦国期には島津忠良(日新斎)が出て中興の祖となり、子の貴久、孫の義久と3代名君が続き、圧倒的な武威でもって九州を席捲しました。
関ヶ原では敗戦国となったものの依然として薩摩大隅76万石を領し、幕末には島津斉彬という伝説的な名君を輩出しました。維新における薩摩藩の活躍の基礎はすべてこの人物が築いたと言ってよく、かれの偉業を西郷隆盛をはじめとする優秀な藩士たちが引き継いだことで薩摩藩は一躍時代の立役者になりました。
薩摩島津家は、きわめて独特の家風を持っていました。
島津家は、とくに鎌倉の風を慕った。とくに戦国から江戸期にかけ、意識して家士を教育し、鎌倉風に仕立てた。
たとえば、島津の家中にあっては捕吏は無用といわれた。罪をえた者が、捕吏が向かうより早く、縄目の恥を避けて自刃した、というのである。(『この国のかたち』)
捕まる前に恥を嫌って腹を切ってしまうというのは今日の感覚からすればやり過ぎな気もしますが、当時の武士たちの名誉希求のすさまじさを偲ぶことができます。
また明治時代は極端な官僚主義国家でありながら、汚職が極めて少なかったといいます。700年の武士というものがつくり上げた清々しい倫理観は、明治への最大の遺産となり、いまも一部の気持ちの良い日本人たちに引き継がれています。
人はどう行動すれば美しいか。
人はどう行動すれば公益のためになるか。
この2つが、幕末人をつくりだしている。
幕末期に完成した武士という人間像は、日本人がうみだした、多少奇形であるにしても、その結晶のみごとさにおいて、人間の芸術品とまでいえるように思える。(『峠』あとがき)
このことは、日本人の公益意識について述べた「『日本人』を脱ぎ去り『地球人』へ。我々の共同体意識が向かうべき未来」という記事の内容とも交差します。良ければあわせてお読みください。
これからの日本人の倫理観
司馬氏は以下のように言います。
今後の日本は世界に対して、いろいろなアクションを起こしたり、リアクションを受けたりすることになる。
そのとき、
「名こそ惜しけれ」
とさえ思えばよい。ヨーロッパで成立したキリスト教的な倫理体系に、このひとことで対抗できる。(『司馬遼太郎全講演』)
私たち日本社会は、武士道を基本にして、高い倫理観をつくりあげてきたつもりでいました。しかし、冒頭で述べたタイでの事件が象徴するように、この誇るべき倫理観は近ごろ忘れ去られてきているように思えます。
いまこそ「名こそ惜しけれ」の精神をもっとつよく持ち直して、さらに豊かな倫理に仕上げ、世界に対する日本人の姿勢の基本にすべきではないでしょうか。
「いま取ろうとしている言動は、名誉を汚すものではないか」
そのようなリミッターがつねに正常に働いてさえいれば、冒頭で述べたような恥ずべき行動など、取れるはずもありません。自分の名誉だけでなく、家族や会社、国の名誉なども思えば、死んでも悔やみきれない醜態であろうことは容易に想像がつくでしょう。
福澤諭吉は著書『丁丑公論』で、
「一身の品行相集まりて一国の品行と為る」
と述べました。
一人一人の品性が国家の品性をつくり、それが日本という国の、世界に対しての態度となります。日本がふたたび世界から敬意と信頼を得られる国になるためには、私たち一人一人のたしかな倫理とつよい精神が必要なのです。
誇れる日本、誇れる21世紀をつくりあげてゆくためには、まずは私たち一人一人が「誇れる自分」にならねばなりません。
なお、記事の中で武士たちの「死への潔さ」を肯定的に捉えたり、縄目の恥辱を避けて自刃する話を取り上げたりしましたが、無論のことながら死それ自体や自殺などを賞賛・奨励する意図で書いたわけではないということは明言しておきます。
賢明な読者の皆さんには言うまでもないことですが、中には言葉尻をとらえ、内容を極大解釈してやかましく騒ぎ立てる人たちが一部おられるかもしれず、このようにあらかじめ自衛措置を講じておかねばならないのは残念なことですが、ご理解頂ければ幸いに思います。
(出典)
紫裾濃:http://item.rakuten.co.jp/kobo-tensho/12kt-3yosi-maru/
萌黄匂:http://www.kingyo-ya.com/gogatsuningyo/gkt-04.html
赤糸縅:http://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/84970
- 関連記事
- 舛添都知事の進退、辞任を望む声が7割
- 百条委員会、不信任決議…舛添知事を待つ都議会の追及
- 公金流用は永田町の常識?―舛添知事疑惑
- 収支報告書に「家族旅行」と記載していたら法的にはOK?―舛添知事疑惑
- “舛添問題”に一石、政務活動費274万円を返還した水野県議からの寄稿


 Kazunori Wakao
Kazunori Wakao