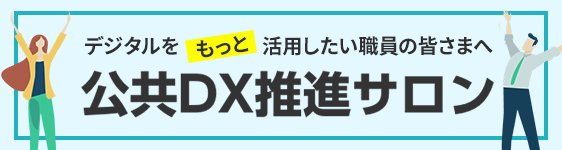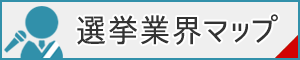独房からお伊勢さん、裁判長からヤクザまで―東海テレビが迫る「ドキュメンタリーの役割」 (2016/10/27 70seeds)
「テレビ離れ」が叫ばれるようになって久しい現代。その中でも特にドキュメンタリー番組は「数字が獲れない」と言われています。
そんな時代に、挑戦的な作品を作り続ける人物がいます。それが東海テレビの阿武野勝彦プロデューサー。これまでに手掛けた作品を見ても、戸塚ヨットスクール戸塚宏校長の現在を描いた『平成ジレンマ』(2010)に始まり、林真須美死刑囚や松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚らの弁護人を務めた安田好弘弁護士に密着した『死刑弁護人』(2012年)、ヤクザの日常に迫る『ヤクザと憲法』(2015)など、その対象はディープ。
一般的に「終わったこと」「決まりきっていること」と思われるテーマにあえて目を向け、その「リアル」に迫り続けるスタイルはなぜ生まれたのか。最新作『人生フルーツ』公開を記念し、10月29日から東中野で開かれるイベントに先立ち、阿武野プロデューサーに話を聞いた。

「終わってしまったもの」のふたを開けると
――今回、取材にあたって『平成ジレンマ』などいくつか拝見したんですが、ものすごい衝撃を受けました。
おお、そうですか。どんなところでしたか?
――戸塚ヨットスクールの戸塚宏校長をはじめ、世間的にはネガティブな印象を持たれている方が多いと思うんですが、作品を見て「この人(取材対象者)と話をしてみたい、直接考えを聞いてみたい」と強く思わされたんです。実際はどんな意図で制作しているのかな、と。
ドキュメンタリーを企画するときに、私たちは東海3県(愛知、岐阜、三重)の1200万人の方を対象にしているんですね。同じ地域に住んでいる皆さんに「今、この時代にこんなことが起きていますよ」ということを伝えるのが仕事だと思っています。そのうえで、「こんな生き方」「こんな考え方」が豊かな社会を作るのに必要なんじゃないか、と考える材料を提供できたらと思っているんです。
『平成ジレンマ』であれば、「戸塚ヨットスクール」というみんな知っているもの、実は、あるときは教育の救世主のように持ち上げ、そして、ひとたび事件が起きたら、一斉に叩いて社会的に葬った。そういう題材ですが、その後、どうなっているのかを時間をかけて取材してみると、過去のものじゃなくって今のテーマとして考えられるんじゃないのと。

――掘り返してみるような。
そう。ふたをして終わらせてしまうだけでは、永遠に解決の出口がなくなってしまうように思うので、あえて、もう一度「今はどうなっているの」って取材してみる。だから「話をしてみたくなった」っていうのも、ある種の現代性を持って戸塚ヨットスクールを捉え直したんだと思うんですよ。それは、決めつけや過去の言説にとらわれないで、『平成ジレンマ』というドキュメンタリーからお探しになった、ということなんじゃないかと。
――逆に言うと、ふたをしっ放しで終わっていることや過去の言説にとらわれてしまっていることが多いっていうことなんですかね。
ほとんどがそうなんじゃないですか。ある色に塗り固めて、みんなでふたを閉めて安心する、しかし、敢えてふたを開けて光を当ててみると、私たちにとって有用なことがあるんじゃないでしょうか。徹底的に排除された人たちの生きざまが、社会のありようを照らすということがあると思うんです。
ただし、ディレクターが是非とも取り上げたいと思う題材に、取り組むということであって、閉められたふたをすべて開けていくことは、物理的に不可能です。
――その開けるべきふたって、阿武野さんの中でどんな基準があるんですか?
開けるべきふた、じゃなくって「開けたいふた」なんじゃないでしょうか。例えば四日市の公害を扱った『青空どろぼう』という作品があります。公害の代表格だった四日市ぜんそくですが、四日市公害は本当に終わったと言えるのか。もしかしたら誰も興味がないですよね。

――はい。
私たちは、東日本大震災の前にこの題材に取り組み、原発事故前に放送したんですが、その時は、何となく反応がよくない。しかし、震災後に映画として上映したら、(原発事故のあった)福島の未来をはからずも予言している、警鐘を鳴らしていると作品評価が高まったんです。私たちは普遍性を求めて制作しているつもりですが、時代状況にぶつかって、作品の見方が劇的に変わるっていうことがあるんだなと思いました。
ドキュメンタリーは、状況を映し撮って「過去」が映像作品に盛り込まれるんだけど、それが、未来という状況を変えることができるかもしれないし、人のもの見方を変える可能性を持っているのではないかと思うんです。
映画館でやるのは、ドキュメンタリーの土壌づくり
――ドキュメンタリーの制作を行っていく中で、樹木希林さんを起用したり、笑福亭鶴瓶さんや箭内道彦さんを起用するなど、メッセージの届け方、「入口」の広げ方にも工夫を凝らしていますが、特に「うまくいった!」という手応えがあったことってありますか?
あんまりないですね。今は、ドキュメンタリーが力を失っている時代だと思っているんですね。民放ではあまり作れないし、作ってもゴールデンタイムでは放送されない。それはやっぱり視聴率が獲れないし、スポンサーもつきにくい、そういうものだからです。中身についても、どこかで観たことのあるようなドキュメンタリーが乱発されたりすると、飽きられますしね。
――うーん…。
だけども、私は大切な表現方法だと思っています。何かを伝えようとするときに、丁寧に取材をし、気持ちを込めて構成して、同時代を生きる同地域の人に手渡そうとする時、ドキュメンタリーは有効だと。今は、まだそういう土壌になっていないけど、ドキュメンタリーを積極的に観たがる文化になるよう、土を耕しているところだと思っているんです。
――土を耕すというのは?
映画館で上映すると、今は1万人入ればドキュメンタリーとしてはヒットなんです。でもテレビの世界では、東海テレビのエリアなら1200万人の1%の視聴率で12万人でしょ。そういう数字に慣れちゃうと、全国公開して1万人と言っても、通用しないんです。だから、1万人に届くことの意味について説明していかなくちゃいけならないんですね。
――それが伝わらないときはどうするんですか?
困りますね。諦めずにいい作品を作り続けるだけですね。そうして理解者を増やしていくことです。継続してやることです。私たちは、ようやく5年で、10作品になったという感じですが、作品のファンを増やすことが土を耕すということかもしれませんね。
私たちスタッフは作品が映画館で上映されるとき、会場の後ろで見ていたりするんですが、スクリーンに向かって同じ時間を共有しているっていうことが、とてもいいですね。みんなここでグッときていたとか、ここで会場の空気が変わったとか、表現が生きていることを実感するんです。映画館で、スタッフが生き返るような気がするんです。
――なるほど。
「放送」って「送りっ放し」って書きますよね。放送したら、はい終わりと。でも映画館に行くと、自分の表現がどのように受け取られているのか、どんな風に拒絶されるか、直に感じられる。ドキドキするんです。ある意味ではスタッフのハートに火をつがつく、そうことかもしれません。すると作品がよくなる。作品がよくなると観てくれる人が増える、そうすると土が肥えてくる。5年やって、まだ手応えは余りないですけど(笑)。
――これまでお客さんはどのくらい増えてきているんですか?
作品によりますね。『ヤクザと憲法』は40,000人、『約束』は自主上映合わせて45,000人~50,000人くらい。作品によっては2~3,000人くらいのものもあります。ただはっきりしているのは、残念ながら東京でお客さんが入らないと地方の映画館に波及していかないので、どれだけ入ってもらえるか、東京に力を注がざるを得ないですね。

――地方の単館系の映画館なんかで「ぜひ取り上げたい」というところもありそうですが、そういうわけでもないんですか?
メジャーの映画館と違って、数人で運営を頑張っている地方の単館系の映画館で、膨大な映画の中からチョイスするのは不可能だと思います。だから、東京のいくつかある単館の実績を元に上映する映画を決めていくことになるでしょうから、結局映画も東京一極集中なわけです。東京の映画館が私たちの映画をチョイスしてくれるところから始めないといけない。今回で10作目ですが、本当は難儀な作業の繰り返しでしたね、本当は…(笑)。
――実は相当難しいことなんですね。
私たちが一年2作ペースで続けているのもあるんでしょうが、結構簡単に上映できると思われているようです。で、「どうやったら上映できますか」って僕のところに問い合わせてくるテレビマンがたくさんいます。で、みんな聞きたがるのが「どのくらい儲かりますか」なんです。で、僕は「儲からない」ってきっぱり言ってます。
――(笑)。
「儲けるなんてこと考えるよりも、制作者なら、まず多くの人に見てもらいたいという強い気持ちが大事。儲けようと思うとお金に絡めとられてとんでもないことになるよ」って。ドキュメンタリー映画は劇映画とは違って、多くの人が積極的に観たいと足を運んでくれる分野じゃないと知らなくちゃ。
――そうですね。
そんな見放された世界から、ドキュメンタリーをもう一度魅力のある世界にするには、マイナスから始まっていることを知ってほしい、そんなことをお話しします。自分たちの置かれている状況をちゃんと認識することが大事で、映画は、それでも参入したい人が頑張る世界なんだと。
リスクがつきもののドキュメンタリー

――そんなドキュメンタリーの世界で、本気でやりたい人って、今とても少なそうです。
少ないですね。僕は絶滅危惧種と呼んでますけど、とりわけ民放は特に少ないですね。やっぱりメインストリームじゃないということがあって。それに今の時代みんなリスクを抱えるが大嫌いですからね。
――リスクというのは?
昔は生身をさらして取材対象とやり合いました。特に携帯電話のない時代は、自宅の電話番号も相手に知らせるわけです。だからちょっとした行き違いがあるだけで、何年も自宅や職場に嫌がらせの電話がかかってきたということもありましたね。実に因果な商売です。しかし、人間ってそういうものなのかもしれませんね。今も、ドキュメンタリーはリスクだらけの制作環境ですね。むしろ個人情報、プライバシーと個人の権利意識が増大する中で、リスクは溢れんばかりという感じですね。取材対象も、ネットの中で槍玉に遭う恐れもあるわけで、露出されることについて、いろいろ考えますよね。
それでもドキュメンタリーは、やりきっていくとよかった、ということになるケースが多いです。逆に、そこまで行かずにトラブルが組織的な問題となってつぶれてしまうこともあると思います。不寛容な時代ですから、何が起こるか分からないです。でも本当は、大きなトラブルや取材の過程、編集作業の迷いを越えていくと、力がつきます。そして「またやりたい」と思うようになる。ドキュメンタリーは、簡単にできちゃだめなんじゃないですかね、きっと。
――今のドキュメンタリーの現場は簡単にできてしまっている、ということですか?
よそがどうやって取り組んでいるかわからないんですが、私たちは大晦日や正月とか、イベントはあまり撮りに行かないで、日常を撮りに行くことを大事にしています。今のドキュメンタリー制作現場は、決められた予算の中でカメラを持っていける回数が限られているのだと思います。しかし、私たちは、可能な限り何もない日常を撮影しに行きなさいと。多いもので40分テープで4~500本くらいに回ることがあります。ロケ日数もかさみます。
そういう非効率な集大成が一本の作品になるわけで、1本1本の撮影テープがその素になると思うんです。芳醇な映像は非効率の賜物なのかもしれませんね…。
――そういった「非効率的」な作業を、東海テレビは会社として応援してくれる風土なんですか?
応援してくれてますね。それはいいドキュメンタリーができているっていう実感があるからだと思います。ある意味、ドキュメンタリーは放送局としての原点であり、お金にはならないが一番大事な仕事だとわかっているのだと思いますね。
――局としてもドキュメンタリーに肯定的だったんですね。
私が入社した35年前、「ドキュメンタリーの東海テレビ」と言われていたんですよ。でも、それは狭い業界の中での話で、いわば自称だったと思います。今もまだ「ドキュメンタリーの東海テレビ」は自称のレベルです。自称を繰り返すことでその気になって、勘違いをしてはいけないと思うんです。
――今東海テレビでやっていることは、阿武野さんにとってプラスになっていますか?
どうでしょう。環境をつくるのは自分の仕事だと思います。よくよその局の人が、私たちのドキュメンタリーを観て、「うちではできない」って言うんですけど、「できなくしてるのは誰なんだろう」って思いますね。それなりの立場なのに、それじゃ誰も何もできないままだと思うんです。できないのを組織のせいにするのは簡単です。個人と組織がどうせめぎ合い、どう折り合っていくか、私たちはもっと奮闘しないといけませんね。
…なんて偉そうなこと言っちゃいましたけど(笑)。
地域の人が潰さないテレビ局になりたい

――ある意味で、これまでの「奮闘」の集大成が10月29日からのイベントだと思います。
うれしいですね。作品が22本あるんですけど、これをチラシに並べてもらうと、眺めるだけでうれしい。テレビマンはきっとみんなこんなことを夢見ているんじゃないかなと。言い方は悪いですけど、「どうだい?」ってちょっと自慢したい気持ちですね(笑)。でもこれでお客さんが足を運んでくれないと、「なんだよ」って話になるので自重しないと(苦笑)。
――そうですね(笑)。
やっぱりたくさんの人に見てもらいたいですから。まだ土は耕されていなけど、実り始めているものもありますよって。丁寧に作ってきた一本一本のドキュメンタリーを、今回観てもらって、今後、どう作って、どう広めていくにか考えていきたいですね。
――はい。
もう1つは、テレビの姿ですね。ふるさとのテレビでありたいって一人で言い続けてきたんです。同時代を同地域で生きる人のためのテレビでありたい、だからまずはそのために素晴らしいドキュメンタリーをつくって放送するんだと。もっと言えば全国、さらに世界に東海テレビエリアの人が出て行った時、名古屋はおもしろいドキュメンタリーがあるねって話になって、「そうそう、私のふるさとのテレビ局なんだよ」って言って、自慢げに言ってもらえるような。
そうなったら、地域の人たちが支えて、どんなことがあっても東海テレビはつぶさないんじゃないですかね。
独りより、みんなで感じてほしい
一時期、「モノとココロ」というのを制作のテーマにしてたんですよ。
――「モノとココロ」?
モノは、それだけではただのモノ。しかし、モノにココロ、つまり物語が付与されることで価値が生まれる。実は、ただのモノなんて一つもない。小さきものにも人の息づかいを感じられるような世の中であってほしいなと。よく思うのは、お金には変えられないものがあるんだということ、そして、それを大事するということかもしれませんね。一色に染まりやすい私たちですけど、多様なものの考え方が尊重されるようにしたいと思いますね。
――なるほど。
私たちもドキュメンタリーをつくっていくときに、「ポーン」と受け止めてもらえることがあって、「よかったよ!わかりやすくて」という感想を言われことがあります。でも、「わかりやすくちゃ困る」って思うんです。「わかりやすい」が一番大事だとは思っていないんです。「なんかよくわからないものが残った」という感想の方が尊いような気がします。作品を、簡単に対象化したから、「わかりやすい」っていうことになったんだろうと思うんですよ。心に刺さらなかったのか、テレビ局員の病気か…。
――ああー、わかるような気がします。
みんなプロなんで、伝えたいと思うあまり、わかりやすくしてしまうんです。表現を刈り込んで単純化してしまうというか。でもそれが本当にいいのか、って。これも、モノとココロですかね。作品を作り出した人にある種の敬意のような気持ちを持てるくらいの、関係性というか、表現や受け渡しはできないものかと。
――とにかくわかりやすく、ということがもてはやされる風潮とは逆ですよね。
このパンフレットもありがたくて仕方ないですよ。構成してもらって、みんなで誤字脱字がないか確認したのに、さっき脱字が一か所指摘されて(笑)。そういう傷が残るのも含めてまたいいじゃないですか。これをこういう風に受け取ったよ、という気持ちが残るのが。そういう関係性でやる仕事が、素敵だし、面白いんですよ。
――いい話ですね。
たとえば、もうちょっとメジャーな配給会社に任せた方が、とか大きな映画館でやった方が、とか言われることもありますよ。でも、そうじゃなくて温もりの感じられる、そして手渡しで組めるのが何よりもいい。いつか大きく広がるところまで一緒にやりたいですよね。だって、いまのところ全然、儲からないですもん(笑)。
そうそう、自分で協賛してくれるスポンサーを見つけたいと歩くこともあります。それも、この映画化という仕事を赤字にして後輩ができなくならないようにするためです。手間暇をかけてやっていると、不思議と人が人とつながり、いわば関係が芋づる式に広がっていくことがあります。文化に支援してくれる尊い会社、経営者もいるんですよ。
――芋づる式、わかりやすいたとえですね。
例えば、今度の連続上映で一度だけ公開する『人生フルーツ』は、衛星放送に広がっていく仕組みです。たくさんの人に見てもらうことが主眼で動いているうちに呼応してくれる人が現れたんです。うれしいことです。日本映画専門チャンネルが12月1月で9本の映画作品を放送し、秋には『人生フルーツ』などを、また特集放送する予定です。
…本当は、失敗ばかりなのに、上手く行っていることばかり述べ立てているみたいでいやになっちゃいますけど(笑)。
――阿武野さんは、いわゆるテレビ業界のメインの動きとは違うところで可能性に挑戦し続けていますよね。
今、テレビマンはスマホに向かってますね。マスメディアが小さい世界に。iTunesとか、要するに合理的に儲けようと。みんなそれですね。でも僕はあまり面白いと思わない。家族でテレビを観ていた時代に憧れがあるから。キスシーンなんか流れると親父がなんか変なこと言い出したり、お母さんがいきなり立って「お茶を入れなきゃ」なんて。そんな家族の視聴環境があった頃が大好きだから。同じものを観ていても違う受け取り方が目の前で展開する。大事な体験でした。だから、これ(小さい世界)には何の夢も見ていないんです。いろいろ方向性があった方が楽しいと思うんですけどね。僕はたまたま、逆へ行ってしまうだけですね。そこに活路があるかはわかりませんけどね(笑)。
◇ ◇
阿武野プロデューサーも登場するイベント『東海テレビ ドキュメンタリーの世界』は、2016年10月29日(土)~11月18日(金)、ポレポレ東中野で開催予定。
これまで発表された全22作品が公開されるほか、映画監督の森達也氏、女優の樹木希林氏らも登場します。
詳細はこちらから。
http://www.mmjp.or.jp/pole2/
- 関連記事
- 【短編ドキュメンタリー】辺境で見た「ミャンマー総選挙」 日本で育った元難民の出馬
- 震災から5年、福島はどう変わったのか。アニメで見る東北の「光と影」
- 地方の本気に全国が驚いた。今年話題を呼んだ全国PR動画まとめ2015
- 日本の児童養護は施設偏重? 国際人権NGOが問題指摘、海外メディア注目
- イルカの「虐殺」…太地町の追い込み漁解禁で、海外メディアが一斉非難