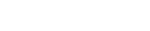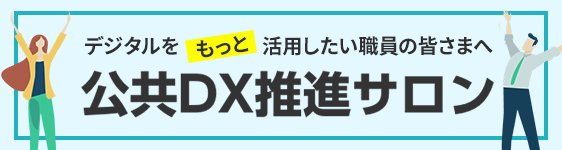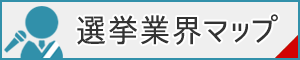民法改正~定型約款条項の新設について (2017/8/29 企業法務ナビ)
はじめに
2017年5月に成立した改正民法では、新たに定型約款に関する規定が設けられました。約款を用いた契約は現行民法下でも広く行われており、特に古くからある鉄道や運送といった業界では、個別の業法による規制がなされていますので本改正によって新たに影響が生じることはなさそうです。
一方で、現代ではインターネットを用いた新しいサービスも登場しており、そうした業界ではサービスの変化が速く激しい傾向にあります。したがって、今後このような業界では、約款を新規に作り、あるいは変更する機会が頻繁に生じるものと予想されます。
そこで、この記事では、法務担当者が約款を扱うに当たって、注意すべき点を見ていきたいと思います。

定型約款条項 ―新設の経緯と定型約款の定義―
現在ではオンラインショッピングのように、特定の者が不特定多数の相手方に対して同一内容の契約を締結するような取引が多く存在します。このような取引においては「約款」が用いられてきましたが、現行民法には約款に関する規定が存在しないことから、「約款」中の条項に当事者が拘束される要件が不明確であるばかりでなく、契約を締結する者が約款の詳細について認識しないまま合意に至ることもあり、「約款」の効力が争われることも少なくありませんでした。
このような状況を受けて、改正民法では約款を用いる取引の安定を図るために「定型約款」についての条文が新設されることとなりました。
改正民法は、「ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの」を「定型取引」と定義し、当該定型取引において「契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」と定義しています。
たとえば、パソコンにソフトウェアをインストールするときに表示される使用許諾書などがこれに該当するでしょう。
改正民法での定型約款の運用
改正民法で新設される定型約款に関する規定の数は、実は3条に過ぎません。定型約款が当事者間の合意に組み入れられるための条件についての規定(改正民法548条の2)、定型約款の内容の開示義務に関する規定(同548条の3)、定型約款の変更要件(同548条の4)が、これに該当します。
以下、個別に検討していきたいと思います。
1.定型約款が当事者間の合意に組み入れられるための条件
定型約款については、(1)当該約款を契約の内容とする旨の合意をした場合、または、(2)定型約款を準備した当事者が、あらかじめその約款を契約の内容とする旨の表示をしていたときに当事者を拘束するものとされています(改正民法548条の2)。
通常の取引の場合、当事者が契約内容に拘束されるには各条項に当事者が合意することが必要です。
これに対して、「定型取引」で利用される「定型約款」とは「準備された条項の総体」を指しますから上記の(1)(2)いずれかを満たせば、個別の条項の内容について合意をしていなかったとしても合意したものとみなされる点に特徴があります。
具体例としては、パソコンのソフトウェアインストール時に「利用規約」がポップアップ表示される場合が(2)に、加えて、それに「同意する」ボタンをクリックしなければインストールできないようになっている場合などが(1)に該当すると考えられます。
2.定型約款の内容の開示義務
定型取引を行う場合、定型取引の合意前、または合意後相当の期間内に相手方から請求があった場合、遅滞なく相当な方法で定型約款の内容を示さなければなりません(改正民法548条の3 1項本文)。改正民法要綱案(p.48)では、約款の表示の方法として「定型約款を記載した書面を交付」する方法と「(定型約款)を記録した電磁的記録を提供」する方法を予定していました。これを参考すると、インターネットサービスの場合などでは、利用希望者が申込み画面上で利用規約を読めるようにしておくか、少なくとも利用規約ページへの見易いリンクを貼ることが必要といえそうです。
また、定型取引合意の前に、定型約款の表示請求を拒んだ場合には、定型約款の個別の条項に合意したものとはみなされないことになります(同2項本文)。
3.定型約款の変更
定型約款の変更が(1)相手方の一般の利益に適合するとき、または(2)契約した目的に反せず、合理的な内容であるときは、変更につき相手方と合意をしなくても、定型約款を変更すること自体によって変更後の定型約款について合意したものとみなされます(改正民法548条の4 第1項)。特に(2)の場合、効力発生時期、変更する旨と変更後の内容等を周知徹底することが効力発生要件となっています(同条3項)。インターネットサービス事業の場合であれば、サービスの変更通知に併せて、変更後のサービスを利用した場合には変更後の利用規約にも同意したものとみなす旨を画面上に表示させる方法が考えられます。
定型約款は上記のとおり定型取引に適用される規約ですが、定型取引自体が不特定多数を相手とする画一的な取引であり、特定当事者間での契約締結後にサービスの内容が変更されることもあります。そのような場合に、他人数の契約当事者と個別に変更の合意をすることは極めて煩雑であることから、このような条項が新設されました。
4.まとめ
冒頭に記したとおり、約款を用いた契約方法は、実務上、様々な業界で従来から広く行われてきました。今回の改正民法もそうした実務の慣行を踏襲したものとなっていますので、実務上、大きな変化を引き起こす可能性は低そうです。
一方で、務担当者にとって特に注意が必要なのが、自社が従来から約款として利用してきたものが、必ずしも「定型約款」に該当しないことです。例えば、約款が特定の企業間の取引に用いられてきた場合、当該約款は「不特定多数の者を相手方として行う取引」に用いられるものとはいえませんから、改正民法における「定型約款」に該当しないことは明らかです。
改正民法は2020年までに施行される予定です。自社が「約款」として利用してきたものが「定型約款」に該当しない場合には上記改正民法の548条の2~4の適用を受けることができません。契約当事者間での紛争を未然に防ぐためにも、法務担当者は、自社の「約款」が定型約款の要件である(1)不特定多数の者を対象としているか、(2)取引内容が画一的であるか、といった点をいま一度確認する必要があるといえそうです。
- 関連記事
- 働き方用語の正しい読み方【解雇の金銭的解決制度】
- デート商法などが取消対象へ、消費者契約法改正への動き
- 成人18歳、臨時国会提出へ 民法改正案、法相が検討
- パワハラの現状と企業の法的義務
- 新成人マルチ商法の標的 18歳引き下げで被害拡大?