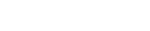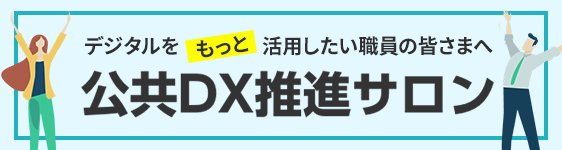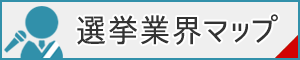週刊ダイヤモンド今週号より~日本の魚が危ない、資源枯渇と買い負けが深刻化 株式会社フィスコ 2013年11月5日
世界で最も豊かな漁場を持つ“水産大国ニッポン”が揺らいでいます。漁業資源の枯渇が、一般消費者にも影響を及ぼし始め、その危機はマグロ、ウナギのみならず、多く魚種に広がっています。今週号の特集では、日本人なら誰もが人ごとではいられない「今そこにある魚の危機」に迫っています。
国連食糧農業機関(FAO)の調べによると、かつて世界トップだった日本の漁獲量は2011年現在でインドネシアを下回る世界6位。12年はそれをさらに下回り、史上最低の373万トン(水産庁統計)に落ち込みました。漁獲量の低下は、海の生態系環境の変化に加えて、人間による乱獲が背景。例えば下関のトラフグは、フグが回遊する地域の自治体で資源管理ができておらず、専門家は「種の絶滅の危機」にあると指摘します。
また、漁獲量の減少を補うために国内需要の40%を依存してきた輸入も、危機的な状況が目前まで迫っています。円安などによって輸入量は減っているのに、輸入額は増加。日本はもはや買い付けの上得意ではなくなり、買い付け価格が高騰しているのです。そうした状況の中、はごろもフーズはシーチキンを、味の素は「ほんだし」の値上げに踏み切りました。「買い負け」は消費者の生活にも影響を及ぼしています。
このほかにもダイヤモンド誌では、苦境の続く福島沿岸漁業の現状を紹介。福島第1原子力発電所事故以来の漁業自粛に加えて、今年春からは汚染水の漏洩問題が重くのしかかっています。実際は、港での海水や大気の放射能検査の数値は事故後一貫して下がり続けているといいますが、上がったのは“消費者の理解を得る”というハードル。地元の漁業関係者は、「安全性を訴えつつ、後戻りせず前に出ていく」と意気込みを語っています。<NT>
-

- 株式会社フィスコは、投資支援サービス等を提供するプロフェッショナル集団です。2013年4月19日に、インターネットを使った選挙活動を解禁する公職選挙法の改正に伴う新たなコンテンツ提供を発表し、各政治家の発言要約や影響分析のコンテンツ提供を開始しており、その付加価値向上に取り組んでいます。