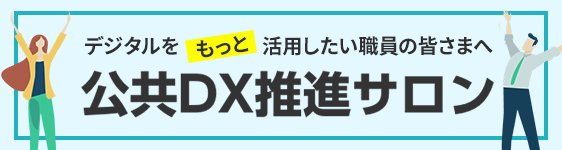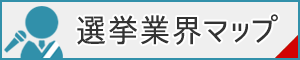「プロねぶた師」は存在しないって本当ですか?―華やかなまつりの影に挑む異端児 (2018/5/1 70seeds)
複雑な多面体から浮かび上がるリアルな人面、ギョロッとした“眼”。紙で形成されたとは思えない大迫力で、祭を盛り上げる。
東北三大祭のひとつに数えられる「ねぶた」は青森県民だけでなく、日本人に広く知られた夏の風物詩だ。

しかしそのルーツが、“庶民”が憂き世を忘れどんちゃん騒ぎするための、単なる“行事”にすぎなかったことを知る者は少ない。「祇園祭といえば八坂神社」、「天神祭といえば天満宮」のような、神社や藩の支援もなく、庶民の支えのみで数百年も受け継がれて来たのだ。
後ろ盾がないということは、作り手や祭そのものが続いていくための保証がないということ。そんな課題を前に、今のねぶたには変革が必要だと気を吐くのが竹浪比呂央ねぶた研究所の所長・竹浪比呂央(たけなみ・ひろお)さん。
ねぶた師の生活基盤の確保と、後進の育成に力を入れる異端のねぶた師が描く、「ねぶた文化」の青写真を聞いた。
青森の子どもはウルトラマンよりもねぶたが好き、だけど…
竹浪さんの出身は青森県西津軽郡木造町(現つがる市)。ものごころついた頃から、ねぶたに親しんできた。
「青森の子供達は、ねぶた小屋(注1)を遊び場にして大きくなります。夏休みの宿題はねぶたの絵を書いたり、工作ではねぶたを作ったり。なので、ほかの子どもが怪獣やウルトラマンに熱中するように、キャラクターとしてのねぶたに熱中するんです」
注1: 毎年春から夏にかけて青森ねぶた祭に出陣する大型ねぶた22台を制作するために建てられる大型の建物
いつか僕も、街を練り歩く大型のねぶたを作りたい。「青森の子ども」として、竹浪さんも自然にそう思うようになった。
だが、そんな「青森の子ども」たちも大人になるにつれ、ねぶたが“仕事ではない”という現実に出会う。それは、ねぶたが「庶民の行事」だったことに始まる根深い問題だ。
「ねぶたというのは夏の単なる“行事”から派生した非日常の空間。一生懸命作ったねぶたも“単なる灯篭”という認識で、祭りが終われば保存されることもなく解体してしまいます。そのため、制作者を“プロの作家”と認識するような素地がなかったんです。ねぶたを出すのは絵の得意な人や、左官屋さん、看板屋さんや、お寺の和尚さん。学園祭のノリですよね」

竹浪比呂央さん
「地元の子どもたちも高校生までは興味を持って関わってくれますが、ねぶた師としてのキャリアを選択する子は極めて少ない。食っていけない現実を見たら、ほかの選択をするのは妥当でしょう。東京で役者やお笑いを目指している人たちは成功すれば食える。しかし、大型ねぶた師は10年修行してやっとの思いで作品を発表しても、ねぶたで食っていくことはできません」
日本の夏の風物詩と呼べるほどに知名度も高く、経済効果も莫大。しかし、その制作者が食っていけないジレンマに問題意識を感じていた。
「“ねぶたを残したい”と声高に叫んだところで、時代とともに淘汰されていく可能性はあります。ある意味で、ねぶたが廃れてしまうことも歴史の摂理なのかもしれない。しかしこれだけワクワクできて、日本中の老若男女が盛り上がれる文化があるのに、その屋台骨を支えている制作者の経済的な裏付けが取れないとなると、将来ねぶたの制作者になろうという若者がいなくなってしまう」
自分と同じようにねぶたに憧れを持った子どもたちが、冷たい現実を目の当たりにして夢を諦めるのはあまりにも悲しい。ねぶたで食っていける世界をつくりたい。
そう考えた竹浪さんは2010年、ねぶた師としての活動の可能性を探るべく、「竹浪比呂央ねぶた研究所」を設立、2015年には「ネブタ・スタイル有限責任事業組合」を設立した。ねぶたの技術を応用したプロダクトの開発を中心に、ねぶた師が“食っていける”世界を目指している。

「それまでねぶた師には“食えないまま死ぬ”ことへの美徳がありました。否定はしませんが、それでは後進は育ちません。“ねぶた”を1つのジャンルとして作家を名乗れるような世界を実現したいと思ったんです」

閉ざしていたのは地元民だった―“アート”として新しい側面を見せる理由
竹浪さんは「ねぶた研究所」「ネブタ・スタイル」だけでなく、ねぶたの素晴らしさを伝える記事の執筆や、講演活動など、普及活動にも力を入れている。
「いままで講演をおこなうねぶた師なんていませんでした。“背中で語る”職人タイプの多い同業者からは、批判ややっかみを受けることもありましたね」
それでも竹浪さんが講演を続けるのには理由がある。きっかけは、海外でねぶたを展示したときのことだ。
「これまでにハンガリーやアメリカでで制作したことがありました。そこで意外だったのが、海外の反応が日本以上にいいんです。ロサンゼルスでは「紙の彫刻」と呼ばれるほど、ねぶたの技法を評価していただきました」
「これだけの反応があることを地元の人たちは知らない。さらに、評価してくださる人がいるのに評価に応えるだけの活動をしようとしない。閉ざしていたのは青森のほうだったんです。地元の人は地元のすごさを感じることができない。評価されているとを知らしめたいですし、ねぶたの輪を広げていきたい思いがありました」
さらに、単なる“行事の出し物“にすぎなかったねぶたの芸術的な価値を訴えていきたいと、竹浪さんは語る。
「ねぶたのファンが増えていく中で、津軽三味線が音楽のジャンルを確立したように“NEBUTA”としてアートの1つにすることも可能だと思っています」

「青森がアートの香りのする街として元気が出れば、スポンサーが文化支援としてねぶたに協賛してくれるかもしれません。これから若い人たちが活躍できるよう柔軟にアイデアを取り入れ、青森にしかないねぶたの造形を作っていきたいですね」
何者でもない“庶民”の思いを、現代に残したい
ねぶたを残したい。竹浪さんがそう思う背景には、ねぶたが辿ってきた歴史があった。寺社や藩の支援を受けないねぶたは、数百年間“庶民の手”によって守られて来た。
現代において、そのことが経済的にはマイナスに働いているのは事実。だが、一方で“庶民のもの”だからこそ守られてきたプライドも、そこには確かに存在する。
「名もなき庶民が年の1回の楽しみとして、ねぶたは祭りに参加するための“道具”にすぎませんでした。なので、戦前はねぶたを作るものは定職につかない道楽者、お調子者、みたいな存在で、蔑まれていたんです。いまでも仕事終わりに「ねぶた小屋に行く」と言うと、「お酒飲むための口実でしょう」と思われたり。創作活動だと思う人が少ない。ねぶたを“文化”として伝えていくには、マイナスからのスタートと言わざるをえません」

「しかし、昔の人もねぶたが好きで、ねぶたにプライドを持って打ち込んでいたのは紛れも無い事実。ただひたすら、一筆に魂を込める。そのマインドはいまも忘れずに作り続けていきたいと思っています」
今の時代にあった形で、先人たちの思いを形にしていく。最後に、ねぶたへの原動力はどこから来るのかという質問に、竹浪さんは微笑みながら答えた。
「子どもの頃に夢見た“大きいねぶたが作りたい”という思いが、いまも私を動かしています。子どもの頃が夢が叶ってこうして仕事をしているわけですから、幸せですよね。いまはとにかく、大好きなねぶたを青森から無くしたくない。先人の思いを未来に伝えていきたいと思っています」
- WRITER
-

岡山史興
70seeds編集長
1984年、長崎県生まれ。ストーリーをデザインしています。Twitterはこちら→https://twitter.com/230okym
- 関連記事
- お客が掃除しに来る古本屋「庭文庫」は、小さな町に人が集まる理由をつくる
- お寺は劇場、法要は演劇―よそもの住職が救った廃寺の危機
- 「月給3000円」の息子へ―銀行マン、チョコレート工房をつくる
- 日本茶だって多様でいい 茶畑とNYを往復して見つけた「本物」
- ムスリム女子学生が「自撮り」で見つめる信仰と自由