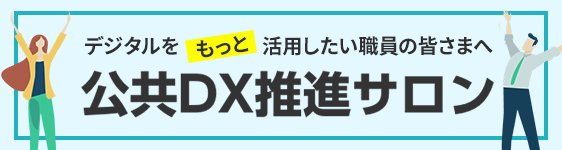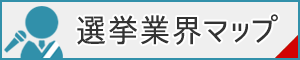「5秒後」を切り取る写真家、楠本涼―人生の「ど真ん中」に写真を置いた元会社員 (2017/12/4 70seeds)
年に一度、ドキュメンタリー分野の若手写真家に贈られる「名取洋之助写真賞」。2017年度第13回の同賞にて、奨励賞を受賞した写真家の楠本涼さん(35)は、かつて会社員だった。安泰だった企業勤めの生活を絶ち、独立。理系頭脳とコミュニケーション力を生かし、独学で写真を学んだ。写真家として生きていくと決意してから6年、受賞の背景には楠本さんならではの魅力があった。

おじいさんのフィルムカメラを借りて
生まれは徳島県海部郡。大学院を卒業するまで、徳島県で育った。カメラに初めて触れたのは、大学院1年生のときだ。漁師だった祖父の持っていたフィルムカメラ「コニカC35」を興味本位で借り、長期休暇のお供に使い始めた。最初は「なんとなくピントを合わせて撮っているだけ」だったが、徐々に面白くなっていったという。
「頭の中でイメージしていた画像と、実際に現像した写真が合致していたり、していなかったり。それがなぜなのかを考えるのが好きでした」
大学院修了後、2007年に医薬品開発職として就職し、大阪で働くことになった。

テーマをもって撮影すること
写真好きが高じて、ボーナスが出ると一眼レフを購入。興味ある写真展には足しげく通い、話を聞きたいと思った人に積極的に話しかけた。元来人が好きで、人見知りはしない性格だ。そうして、徐々に写真つながりのコミュニティーの輪が広がっていった。
仲間と会話をしていく中で「テーマを持って撮ることが大切」ということを意識するようになる。身近な先輩写真家のアドバイスであったのが一つ。もう一つは、写真集を読み漁る中で、どの作品にも撮影方法や被写体の並び方を通して、”何を表現したいか”というのが大前提にあることに気づいた。そこで、テーマに選んだのは「サラウンド」だった。
「説明が難しいのですが、例えば僕たち2人が話していてる中で、実はビルの上から大きな恐竜が僕らを覗き込んでいるというような構図。アート的な発想を持っていました」
そして、07年に“surrounding”という作品を制作。その後も個人でも撮りためた写真を国内外のコンクールや写真祭などに応募し、入賞する機会も増えていった。さらに、「マグナム・フォト(MAGNUM PHOTOS)」という国際的に有名な写真家集団に直接レクチャーを受けるチャンスを得たことも追い風となり、徐々に生活の中で写真が占める比重が大きくなっていった。

ある朝起きて、「会社を辞めよう」
大阪での生活も4年目を迎えた頃、写真家になることを決めた。
「ある日、朝起きたら『会社辞めよう』って思って。会社員として仕事もやりがいがあったし、給料もそこそこもらっていたし、楽しかった。だけど、写真を人生の『ど真ん中』に置いた人生にしたいと思いました」
2011年、楠本さんは写真家に転身した。家族からは相当反対された中、写真関連の仕事への就職も決まり、ひとり東京へと拠点を移した。
心機一転、腰を据えて東京で暮らし始めた矢先、東日本大震災が起きた。何かのパワーに流されるように、東京から東北へ行くことを決めた。カメラとパソコン以外は売り払い、東北に乗り込んだ。向かったのは岩手県陸前高田市。海辺の小さな集落に滞在し、町や人の変化を追った。避難所では幅広い年代の人から直接津波の話を聞いた。現在進行形で進む様々な感情に触れながら、10日間ほど滞在して撮影を行った。
当時、収入はゼロだったため、収入と住まいを確保するために、いったん地元の徳島へ戻ることに。アルバイト先に選んだのはユニクロだった。徳島県内では時給がある程度高かったからだ。
「サラリーマン時代、BtoBの仕事しかしていませんでした。医師と話すことはあっても、実際に薬を使っている人には会っていなかった。個人事業主として、BtoCの経験は今でも糧になっています」

理系頭脳を撮影時に生かす
徳島で約1年生活し、次に働く場所として選んだのは京都だった。何のゆかりもない街だったが、伝統文化など自分が撮りたいものがあった町だった。東京からの仕事の受注が来る場所という予想も当たり、順調に写真家としての道を歩み始めた。理系の頭脳も役に立っている。例えば、限られた時間の中で撮影する場合、どのカットが何枚必要で、それにどのくらいの時間が必要なのかを頭の中で計算して判断できるのだ。
経済的に余裕ができた14年に結婚。現在は1児の父になった。
「ライフイベントの変化は写真にも影響を与えます。例えば、独身と結婚して子どもを持ったときとでは、妊婦さんを見かけた時の反応が変わった。相手のことをもっと考えるようになりましたね。それと同じように、僕の写真を見てくれた人がいつの日か、何か共感性を見つけてくれて、次のアクションを起こすきっかけになったらいいなと思います」

(名取洋之助賞奨励賞受賞作品『もうひとつの連獅子』より)楠本さん提供
被写体の内面部分に興味をもつ
今年、ドキュメンタリー分野で活躍する35歳までの写真家に送られる「名取洋之助写真賞」に応募した。その結果、75歳の舞踊家の女性やまとふみこさんと、その若き弟子を約2年半追った『もうひとつの連獅子』が奨励賞を受賞。「連獅子」とは舞踊演目の一つで、獅子が我が子を谷に突き落とし、自力で這い上がってくるのを見守るという内容だ。
出会いは偶然だった。打ち合わせで訪れた先で、たまたま演舞の練習をしていて、興味をもったのがきっかけだった。
楠本さんは、被写体に対していきなりシャッターを押したりはしない。1カ月ほどかけて、自分はどういう者で、何をしていて、あなたのここに惹かれたから撮らせくださいということを真摯にアプローチし、相手との距離を縮める。その中で、師匠のふみこさんが個人的な経験に基づいて行う、20代の弟子への「継承」に関心を持つようになった。
「人は何かを他者に引き継ぐとき、自分の中にある『価値あるもの』を探して、大事に手渡していると思うんです。”AさんからBさんへ”という一般的な継承だけでなく、Aさんがなぜそれを伝えようとするのか。そこには個人の経験が関係しているはずなので、ふみこさんの昔の話や、踊りの先の内面部分も知りたい、見てみたいと思うようになりました」

(写真集作成のために、試行錯誤して撮った写真の数々)
5秒後の未来を予測
長く同行することで、現場にて“あうんの呼吸”がわかってくると、次に何が起こりそうか予測できるようになるという。
「5秒後に何か動きがあると思ったら、僕の場合は『引き』ます。全体を俯瞰して、客観的に師匠と弟子の関係を捉えたいと思いました」
今回賞をとり、良い報告ができたと同時に、一つの区切りができたと振り返る。しかし、受賞は通過点に過ぎない。現在『連獅子』の写真集制作に取り組んでいる。
「ふみこさんと出会って3年。残りの72年間をどう写真集に反映していくかが課題です。今、昔の写真などを見せてもらっています。ゴールは見えないですね。見えないところにいるだけかもしれないですけど(笑)」
写真1枚1枚は完成されているものの、それが集合体になる場合はストーリー性がポイントになる。
「良い写真を右から左に流すのではなく、なぜこの綴じ方で、なぜこの順番で、なぜこの写真なのか、全てを含んでストーリーの位置づけにしたいと思っています」
写真という媒体が楠本さんの表現方法なのだ。
「写真集だけど、本としても深みがあるものを作れたらと思います」
- WRITER
-

小野ヒデコ
フリーランスライター
1984年東京生まれ。同志社大学文学部英文学科卒業。自動車メーカで生産管理、アパレルメーカーで店舗マネジメントを経験後、2015年にライターに転身。週刊誌AERAをはじめ、PRESIDENT、ウェブメディアTHE PAGEなどで執筆中。