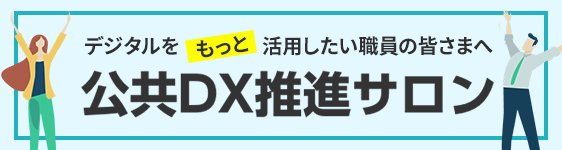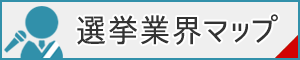「国に帰れ!」EU離脱派勝利でさらに火が付く外国人嫌悪 その背景と残留派の失敗 ニュースフィア 2016年6月29日
6月23日に英国のEU離脱が決まって以来、世界中のメディアで議論が行われており、経済への影響がその要点となっている。即ち、離脱派の勝利が経済的な理由に基づいていること、またその影響が英国及びEU諸国の経済で見られるであろうことがしばしば指摘されている。
しかし、離脱派の勝利の最も強い動機が英国における外国人嫌悪だったのではないかという声もある。その影響は既に英国在住の外国人の日常生活に及んでおり、投票以降、英国で差別事件が相次いでいる。なぜ外国人嫌悪がそこまでエスカレートしているのであろうか。
◆英国における移民の歴史
英国のEU離脱派勝利と外国人嫌悪との関係を理解するためには英国における移民の歴史を遡る必要があるだろう。1993年にEUが誕生するまでは英国において移民は重大な問題ではなかったが、1993年から2014年までに英国に在住する外国人の数が200万人から500万人へ増加した。依然としてインドないしパキスタンからの移民が最も多いが、徐々にEU諸国からの移民も増えてきたのである。
特に2004年にポーランドをはじめとする東欧諸国がEUに加盟した結果、それらの国からの移民が増加し、2004年には25%だったEUから英国への移民の割合が2014年には50%にまで上昇した。また、2008年の経済危機の影響でスペインやイタリアなどからも英国に移住する人が多くなった。
英紙インデペンデントが指摘しているように、英国に在住しているEU移民が英国経済に好影響を与えており、今後、高齢化問題対策になり得るという研究成果がある。それにもかかわらず、「EU移民が英国人の仕事を奪っている」という偏見が市民の意識に根付いてしまい、外国人嫌悪がエスカレートし始めたのである。
上記のような偏見が広まっている中で離脱派が「英国の仕事を英国人に」(”British jobs for British workers”)というスローガンに基づいたキャンペーンを行った。それに対して、米メディアの『Vox』が指摘しているように、残留派のキャンペーンは移民が英国経済にもたらしている好影響に言及せず、主にEUから離脱するデメリットに論点をずらした。つまり、議論の核心が「移民を制限する」対「英国経済を守る」となり、その対立において残留派のキャンペーンがあまりにも説得力を欠いていたと思われる。最終的に投票にあたって国民を動かしたのは、離脱派が強調していた外国人嫌悪であったといえよう。
◆「国の経済」より先に「人の人生」に影響を及ぼしている英EU離脱
残留派と同様に世界中の各メディアは英EU離脱が英国および他国の経済に及ぼす変化に注目している。その一方で見落とされがちだが、英国に在住する外国人の日常生活にすでに憂慮すべき影響が出ている。国民投票の結果が発表されて以来、英国において差別事件が相次いでいることがSNS上で注目を浴びており、「荷造りしておまえらの国に帰れ!」「我々の国から出ていけ!」など、差別的発言がたびたび目撃されている。特に東欧や中東出身者に対する差別事件が増えており、いち早く対応できるようにそれらの事件を目撃した人の投稿を集めたFBページ「Worrying Signs」が26日に作成された。
当然、人種差別は英国に限った問題でもなく、国民投票の結果によって初めて生まれた現象でもない。しかし今まで抑えられていた外国人嫌悪の気持ちが離脱派勝利によって正当化されたかのように爆発し、現在の差別的事件の原因になっていると思われる。
◆不確実な状況に置かれている英国国籍の人も
英EU離脱の影響で英国在住の外国人はどうなるのであろうか?この問いに答えるにはまだ早すぎるであろう。差し当たり彼らの現状を定義するには「不確実性」より適切な言葉がない、とVoxは述べている。
しかも、英国国籍とEU圏外の国籍を持っている人からなる国際結婚カップルも同じ状況に置かれているのである。法律上で定められている条件としては、英国国籍を所有している人とEU圏外の国籍を所有している人が結婚する際、英国人が最低18,600ポンド(約250万円)(配偶者と子供が一人いる場合は22,400ポンド)以上の年間所得を持たない限り配偶者にビザが下りない。英国人の半数以上がこの厳しい条件を満たせないため、今までは英国を去りEU諸国に移住していた家族が少なくなかったが、英EU離脱が彼らの未来をも危うくする可能性がある。
英国のEU離脱は2年後に実行される予定であるが、それによって英国に残るためのビザ、あるいは他国へ移住するためのビザを取得する手続きが何月、場合によって何年もかかる。その間、英国に在住している外国人やEU諸国に在住している英国人は、不安定な状況に置かれたまま今後の進展を待つよりほかにないだろう。