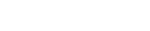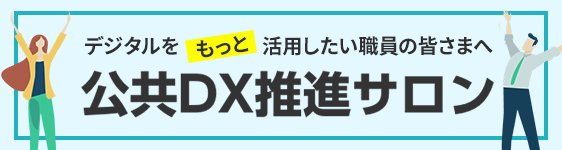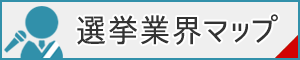円安なのになぜ貿易赤字?貿易赤字なのになぜ企業収益が改善? 株式会社フィスコ 2014年2月12日
財務省が7日発表した1月上中旬の貿易赤字は2兆150億円の赤字となり、前回12月上中旬の1兆3800億円から増加した。
原発停止による燃料輸入の増大など貿易赤字を膨らませる要因はあるものの、「なぜ円安なのに貿易赤字が継続するのか」という疑問の声がよく聞かれる。
大和総研はこの点について、(1)輸出先の設備稼働率が低いこと(2)日本企業のPricing to Market行動(3)日本企業によるマークアップ(粗利益率)の優先(4)為替レートの見通しに対する不透明感(5)海外生産移転に伴う輸出の減少——という5つの要因が考えられると指摘した。
このうち(1)と(4)は輸出数量増加のタイミングを後ずれさせる要因であり、円安と海外経済の拡大が続く限り、その効果はいずれ発現する。(2)と(3)は輸出数量の為替感応度の低下要因であり、円高局面における耐久力の上昇として評価できる。また、(3)については輸出数量が伸び悩む中でもマークアップの改善を通じて企業収益を改善させる要因、最後の(5)はトレンドとしての構造変化だと説明している。
ちなみにPricing to Marketとは企業が戦略的に国内販売と海外販売とで同一製品の相対価格を変化させること。別の言い方をすれば、日本企業は為替レートの変動を輸出価格にあまり転嫁しない傾向があるということだ。
こう考えてみると、かつて中国や韓国など近隣諸国から一斉に浴びた「円安推進は近隣窮乏化政策だ」との非難が的外れであることが鮮明になる。
経済評論家のピーター・タスカ氏は英フィナンシャル・タイムス(電子版、10日付)への寄稿で、アベノミクスは日本が1930年代に引き起こした近隣窮乏化政策ではなく、「みんなにとって良い成長の軌跡を追及する」政策だと主張。日本企業はかつて、円安局面では輸出価格を引き下げて競争力強化を図ってきたが、現在の経営者は株主の利益を尊重しながら「市場シェアよりもマージンを重視した」経営戦略を取っていると述べている。
タスカ氏はまた、自動車生産を例に挙げると2007年には海外生産比率が5割程度だったのが、現在は8割に達しているとも強調。こうした構造変化は輸出数量を増加させないものの、企業収益には跳ね返っていると分析し、TOPIX指数のコンセンサス予想PERが2013年から17年の間にほぼ100%上昇した点に言及している。 <RS>
-

- 株式会社フィスコは、投資支援サービス等を提供するプロフェッショナル集団です。2013年4月19日に、インターネットを使った選挙活動を解禁する公職選挙法の改正に伴う新たなコンテンツ提供を発表し、各政治家の発言要約や影響分析のコンテンツ提供を開始しており、その付加価値向上に取り組んでいます。