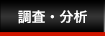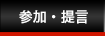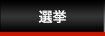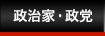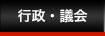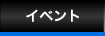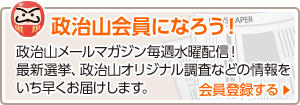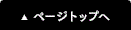「第1回日本創造熟議」開催(2012/12/18 政治山)
「このままでは日本が危ない」との危機感を持った若手地方議員集団・龍馬プロジェクトの会長である前大阪府吹田市議会議員・神谷宗幣氏と、震災以降、社会全体での対話が大切と考え行動してきた組織コンサルタントの石川英明氏が企画した「日本創造熟議」というイベントが11月17日、東京・港区の株式会社パイプドビッツ本社で行われた。当日の模様を、ファシリテーターを担当した石川氏のリポートでご紹介する。(政治山)
◇ ◇ ◇
 参加者を前に熱く語る神谷宗幣氏
参加者を前に熱く語る神谷宗幣氏
今回初開催となる「日本創造熟議」は、気軽に政治について語り合う場を持つ・増やすことを目的としたプロジェクトです。当日は、Facebookなどを通じて、経営者や会社員、NPO法人や自営業者、市議会議員の方など、さまざまなバックグラウンド持つ方が参加されました。気軽さを大切にしているので、途中参加や途中退出の方もいらっしゃり、のべ27名の方にご参加いただけました。当日は「私たちは社会に対して、どのように役割を果たしていきたいか」「国政選挙ではどのような政策・課題を取り上げ、論議してほしいか」などをテーマに議論しました。
“社会づくり”に対して、私たちはどのように役割を果たしていきたいか?
社会を良くするにはどうしたらいいか──。この漠然とした問いに対しグループごとに議論し、さまざまな意見が出されました。
あるグループは「今の社会には“あきらめ”が多い」と指摘。その原因として、マスコミの報道にあるのではないかという意見が出ました。「ニュースで伝えられるのは殺人や強盗など、ネガティブな事件ばかりだ。そんなニュースを目にしていたら、『だめな国だ。危ない国だ』と思ってしまう。悪い出来事だけでなく、ハッピーなニュースも流してくれれば、『日本はいい国だな』って思うのではないか」と提言。「そのように思うことができれば、1人ひとりに自信が出てくるだろう。その自信が源となって、自分たちで社会をつくっていける、動いていけるようになるのではないか」といった意見が出ました。
別のグループは、近所づきあいに対しての意見交換。「昔は地域ぐるみで支えあって生活をしていたが、今は、隣に住んでいる人を知らない。これは、住んでいる場所と働いている場所が違うからこそ起きていることだ。働いているところが生活の中心になっているのが現状。家は、ただの『寝るところ』。住んでいる地域でのコミュニケーションは少なくなってきている」との意見が出ました。
 「政治家に任せるだけでなく、市民主体の自治の時代を創りたい」との思いを強くした石川英明氏
「政治家に任せるだけでなく、市民主体の自治の時代を創りたい」との思いを強くした石川英明氏
「食」の視点から社会を考えるグループもありました。「食を通して、社会や平和に向き合うことが大切。また、一家団らんなど、かけがえのない時間や日常の大切さを見直したい」。また、日用品がどれくらい環境に負荷を与えているのかにも言及。「輸送コスト、輸送における環境負荷なども考えると、『地産地消』が重要だ」といった考えも出されました。
地方議員が参加したグループからは、政治家らしい意見も出てきました。「地域において、市民の意見をどう吸い上げるか。『声なき声』をどう吸い上げるか──。それが大切だ。例えば、1軒1軒を戸別訪問するのも効果的。ITツールを活用して、大勢の意見を吸い上げるような仕組みも必要だろう」と、具体案も示されました。
政治を会社に例えたグループからは、「会社でも、規模が大きくなればなるほど、無関心になっていく。全然知らない部署のことには、関心がない。政治に対しても似たようなことがあるだろう。大きすぎてよく分からない。『誰がどこで何をやっているのか』『どういう影響を与え合っているのか』を把握する場があることが重要だと思う」といった意見が出されました。
◇ ◇ ◇
後半は5グループに再編されて、国政選挙についてのディスカッション。そこで出された「国防・外交問題・領土問題」「税金・年金・社会保障」「統治システム・地方分権」「教育」「経済・景気対策・起業」の5つのテーマに沿って、参加者それぞれ参加テーマを選んで、議論が行われました。そこで話し合われたことの一部の意見を、以下にご紹介します。
国防・外交問題・領土問題について
- 日本は「アジアのリーダー」という立場を維持するために、背伸びをし過ぎなのではないか。リーダーは中国や韓国に任せたらいいのではないか
- 中国に任せるのは危ない。ほかの東南アジア諸国は、日本のODAにとても感謝している。日本に期待してくれているところも多い
- 他国から軍隊に攻められたらそれまで、という面も無視できない。そう考えると、日本も国防軍をしっかりと持つべきではないか。外交上で対等なテーブルに着くには、対等な軍事力を持っている必要があるように思える
- それを現行の法制度でやることはできないので、憲法改正についても検討が必要だ。米占領下で作られた現行憲法はご破算にして、私たちはもう一度憲法を作り直すことも考えてもいいのではないか
税金・年金・社会保障について
- 現在、国の税収は80兆円。実収入は40兆円くらいで、支出の38兆円は医療費となっている。対策が急務である
- 医療業界のあり方も考える時期に来ている
- 予防医療に注力したり、医療費の負担が少なすぎるとも思われるので、もう少しあげたりしてもてもいいのではないか。また、日本の医療技術は高いため、外国人で日本の医療を受けたい人もいる。そうやって外貨を稼ぐことも必要だろう
- また、終末医療には大変なコストがかかっている。これには慎重さを要するが、安楽死や尊厳死といったことにも向き合うことも大切だろう
- さらに、全世界の薬のうち、30%は日本で消費されている。それだけのお金がかかっている。このお金の流れをしっかりと確認していくことで、問題が明らかになるのではないか
- 年金に関しても、さまざまな問題が明らかになってきている。例えば、支給額の問題。収入が多く、たくさん払った人ほど、年金をたくさんもらうという仕組みになっているが、このままでいいのか
- 年金を払わないで生活保護を受けると、13万円もらえる。年金を払っている人が年金を受け取ると、6万円もらえる。ということは、現状は「年金を払わない者勝ち」になってしまっている。ベーシックインカム(基礎所得保障)の中から、自分で責任を持って払うということも大事かもしれない
統治システム・地方分権について
- 地方分権を推進していき、収支を各地方に任せ、権限も持たせる。そうすれば、行政の職員も責任感を持つし、当事者意識を持って、チャレンジしていく自治体になるのではないか
- 2011年に大震災が起きた。そのときに明らかになったのは、行政の対応スピードが遅い、ということである。国は「費用対効果をはっきりと検討して……」などと言っている。お金はあるのに、現場で活用されていない、などという事例もある。国の対応が遅いことに対しては、自治体に権限委譲して、自治体がもっと対応していくのがいいのではないか
- 企業を見てみても、小さい組織のほうが生き生きとしている割合が高いかもしれない。自治体という小さい単位で運営したほうが、職員の行政システムへの理解も進み、やりがいもあるのではないか
- 一方で分権化が進んだ場合、「金持ち地域」「貧乏人地域」のような格差が生じすぎるリスクもあるかもしれない。セーフティネットを同時に用意することも必要ではないか
- 今は行政ごとにデータがバラバラで、とても非効率。効率化するには行政のデータを1つにまとめることが重要だと思う
- 分権化は進めていくべきだと思うが、地方は実際的に人材不足もあり、権限委譲しても、いきなりは対応できないかもしれない。進めながら人材を育てていくということも必要だろう
教育について
- 教育には大きく2つある。「家庭での教育」と「学校教育」だ
- 昔の先生は尊敬される対象で、以前はみんながなりたい職業でもあっただろう。しかし、今はそうではなくなってしまった。なぜだろうか
- 現在の先生は、社会経験がない人が先生になっている
- 「自分で考える」ということを教えることが必要だと思う。アメリカやヨーロッパでは「自分で考える力」を伸ばす枠組みがあると聞いている。日本でもこのことが大事なのではないか
経済・景気対策・企業について
- 経済を循環させていくために、自給自足でまかなえるようなシステムが必要ではないか。今の社会は、さまざまな点で限界な気がする。医療や年金のシステムもそうだし、東京一極で、日本中の経済を回していくのもそうだ。このような状況を活性化するのに、起業を促すことが大切だ
- 今までのレールや、効率性、通貨といったものは必要だ。しかし、経済を回しているのは「人」である。私たちはGDPを最重視するのを続けていていいのだろうか。新しい価値観にチャレンジできるのが日本人ではないか
- 国内では研究などの「高付加価値な仕事」だけをすればいい
- 一方で、さまざまな人材を国内で雇用するには国内に工場があることなども条件、という意見も聞かれた
- しかし、高賃金で低付加価値の仕事をしていれば、国際競争力は犠牲になるだろう
◇ ◇ ◇
 グループディスカッションでは、さまざまな意見が交わされました
グループディスカッションでは、さまざまな意見が交わされました
日本社会が過渡期にあると感じられる今、市民1人ひとりが社会に対する姿勢を変化させていくことが重要と思っています。ネットを使った市民活動なども重要だと思います。
しかし、ネット上だけでは誹謗中傷が待っているかもしれず、1センテンスだけ抜き取られて、心ない批判を受けるかもしれません。ですから、実際に対面しながら安心して語り合えるという場があることが、民主主義にとっては非常に重要であると感じています。
今回の日本創造熟議の場では、結論は出ませんでした。また、知識不足で浅い議論になった面もあっただろうと思います。しかし「結論が出ない」のであっても「議論が浅い」のであっても、多様な意見が話し合われたということにとても意義があるように思います。知識がない人でも気軽に参加できる、ということもとても重要だと考えています。
民主主義が単なる多数決と違うのは、この「話し合うプロセス」を大切にするということだと思います。こういった「多様な意見が、安心して話し合われる場」が日本中に増えていくことで、日本社会は確実により良くなっていくものと信じています。
今回、20名以上の方にご参加いただき、多様な意見を話し合っていただいたことで、その価値を私自身は深く実感しました。今後もできる限りのことを尽くしていきたいと思っております。
(文:石川英明)