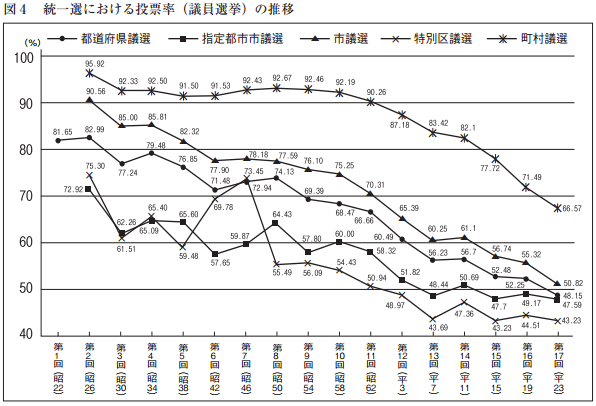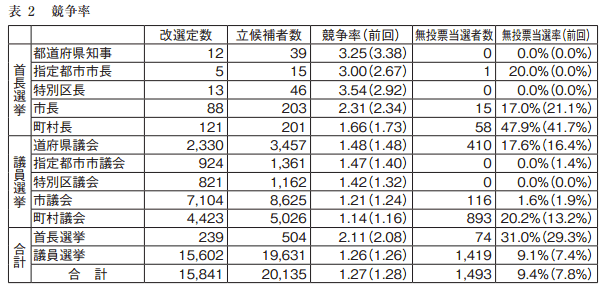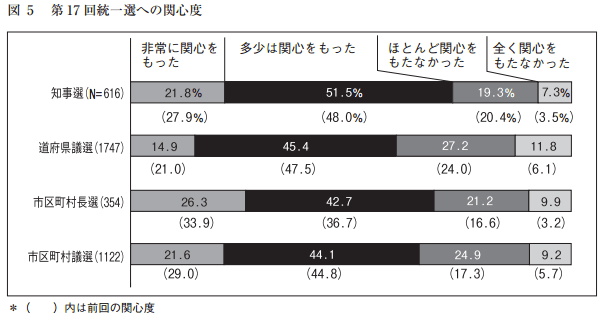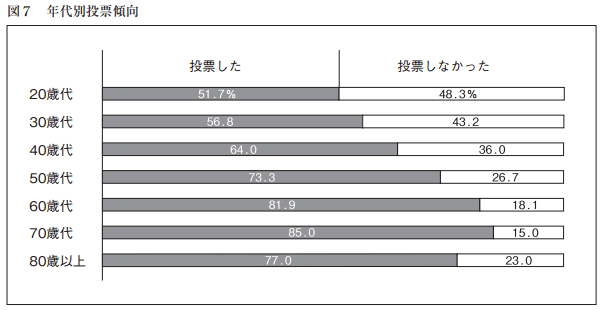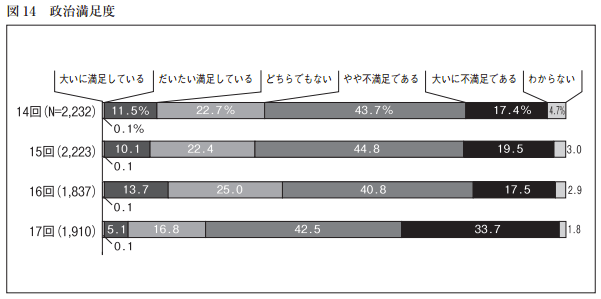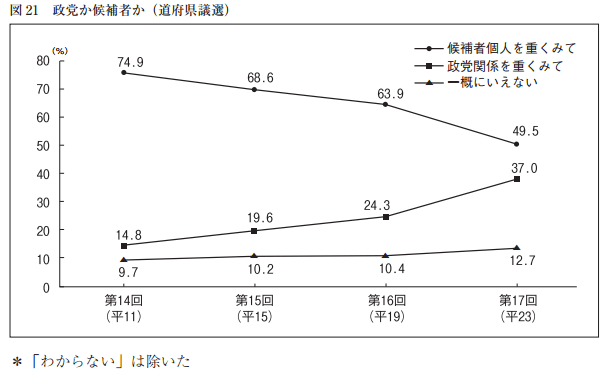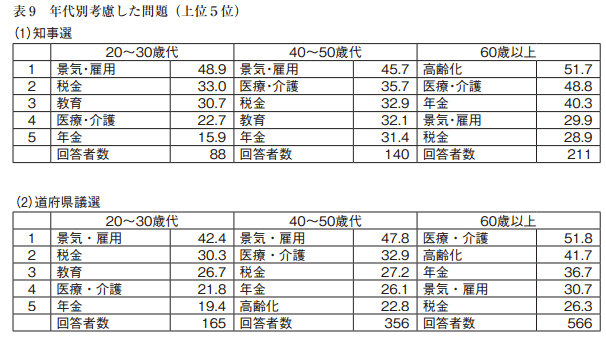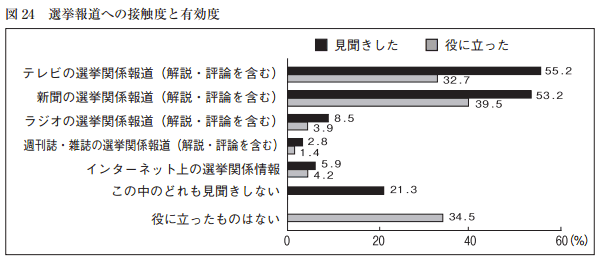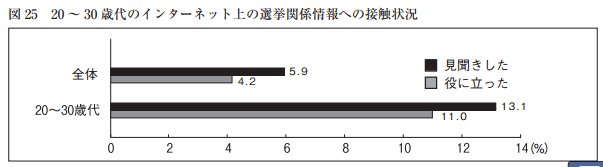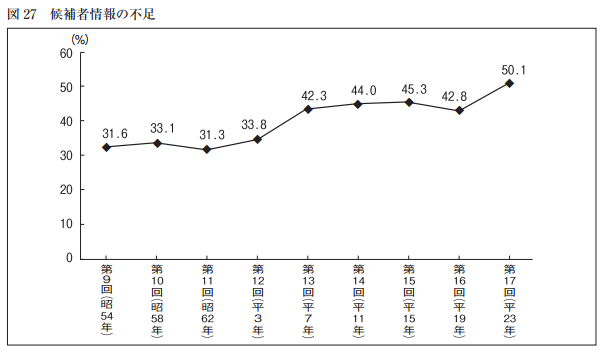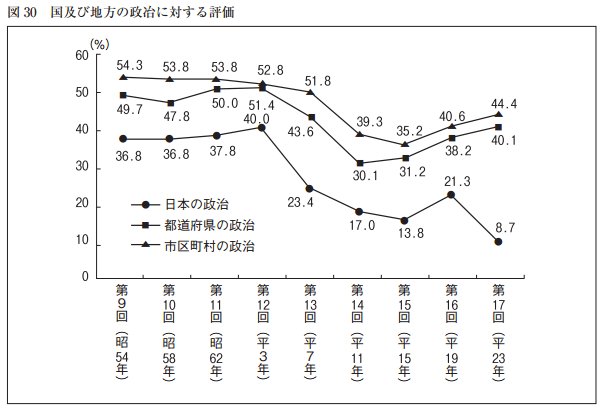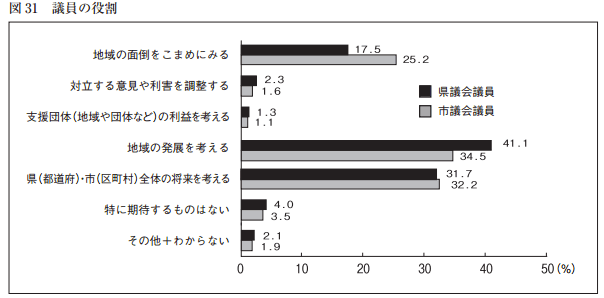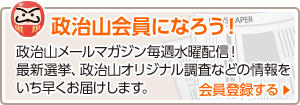選挙ピックアップ
統一地方選挙全国意識調査(明推協)
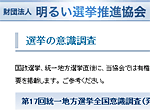
今年1月、財団法人明るい選挙推進協会(明推協)が、第17回統一地方選挙後に実施した全国意識調査の結果を公表しました。この調査は、国政選挙と4年ごとの統一地方選のたびに行われています。調査の目的は、「今後の選挙啓発活動のため」とされていますが、全国有権者が調査対象で、過去の結果と数字の移り変わりを比較して見られるなど、有権者が選挙に対して持つ態度を知るいい資料です。いくつか特徴的な結果について政治山編集部でピックアップし、報告資料を引用しながら紹介します。 (2012/2/22 政治山)
第17回 統一地方選挙全国意識調査
第17回統一地方選挙全国意識調査は、昨年4月に行われた統一地方選挙の後に、一部地域を除く全国20歳以上の有権者3,000人対象に面接を行い、(1)知事選挙の投票の経緯、(2)道府県議会議員選挙の投票の経緯、(3)市区町村長選挙の投票の経緯、(4)市区町村議会議員選挙の投票の経緯、(5)地方選挙に関する意向、(6)政治に対する関心と態度、の6項目について答えてもらったものです。調査の回収結果などは資料をご参照ください。
第17回統一地方選挙のあらまし
調査結果の概要「1 はじめに」で、今回の統一地方選の概観を記しています。統一選のときに行われる選挙の割合をあらわす「統一率」が前回29.8%から27.4%に下がっていること、また選挙の延期や投票時間の短縮、選挙活動自粛の風潮など東日本大震災の影響が各所で出たことについて触れています。
-
今回の統一選は、3月11日に起こった東日本大震災のため、当初統一選での実施が予定されていた選挙のうち、岩手県知事選、岩手県議選、宮城県議選、福島県議選をはじめ、岩手、宮城、福島及び茨城県内の市町村の首長選、議員選など計60件が延期された。この結果、全国1,794の地方公共団体のうち13.3%に当たる239団体で首長選挙が、41.5%に当たる744団体で議員選挙が実施され、統一選の執行件数(無投票を含む)は、前回の1,116件から983件になり、統一率は29.8%から27.4%に減少した。
日本大震災の影響により、一部地域では電力の安定供給のために計画停電が行われたため、当初の予定より期日前投票所数を減らしたり、投票時間を短縮する選管が相次いだ。
第17回統一地方選挙全国意識調査─調査結果の概要─ P.24(pdf)
計画していた啓発事業を取りやめたり、縮小した選管も多かった。啓発活動及び選挙運動を自粛する動きは、東北、関東地方だけでなく全国的に拡がり、投票率の低下、新人候補への逆風の一因となった。液状化被害に見舞われた千葉県浦安市は、投開票所の安全が確保できないと判断して、千葉県議会議員の選挙の投開票事務を拒否した。大震災の影響を色濃く受けた、これまでにない異例ずくめの選挙であった。
投票率と定数に対する候補者数について
投票率
調査結果の概要「2 選挙結果(総務省データから)の(1)投票率」では、今回の統一選の投票率の平均値をまとめています。都道府県知事選、都道府県議選、市区町村長選、市区町村議選それぞれの推移を表したグラフを紹介します。
-
過去の投票率と対比すると(図2~4)、全ての種類の選挙で前回を下回った。統一選の投票率はこれまでも長期低落傾向を続けてきたが、今回は、知事選・特別区長選以外の選挙は過去最低、知事選挙も過去2番目の低さであった。特に、指定都市市長選は前回から6.92ポイント下回り、最も減少幅が大きかった。
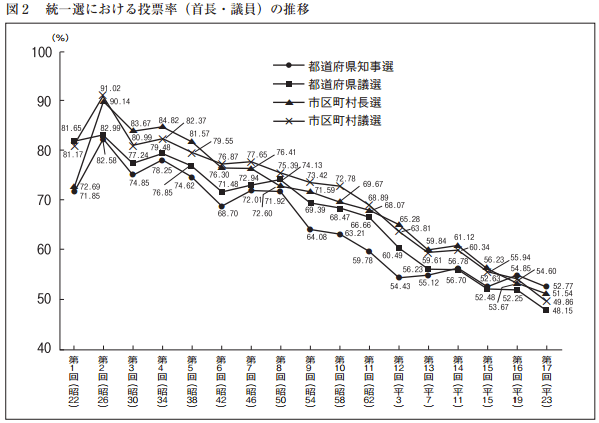
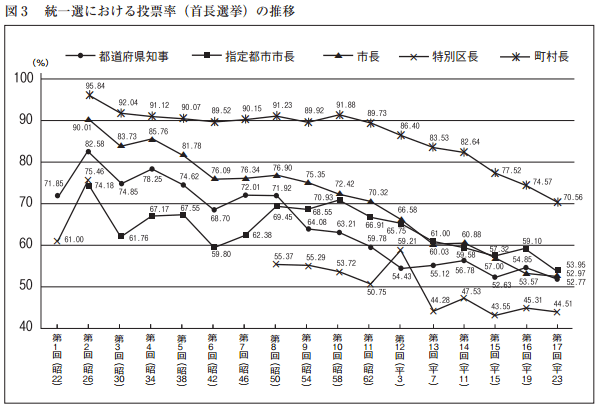
選挙競争率(定数に対する候補者数)
調査結果の概要「2 選挙結果(総務省データから)の(2)選挙競争率」では、選挙の立候補者数を当選者数をあらわす定数で割った「選挙競争率」について触れています。大都市では競争率は上昇傾向、一般市、町村部では低下傾向を見せています。また、町村部では無投票当選率が前回より上昇しました。
-
今回の統一選における平均競争率(立候補者数を改選定数で割った値)を選挙の種類別に見ると(表2参照)、前回との対比では、全体的には前回(1.28)とほぼ同じ競争率(1.27)であるが、指定都市や特別区といった大都市では競争率が上がった半面、一般市や町村では下がっている。
無投票当選率は、前回の7.8%より上昇しており、特に、町村長は41.7%から半数近い47.9%へ、町村議会議員は13.2%から20.2%へ上昇した。
選挙への関心度
調査結果の概要「3 選挙関心度」では、知事選挙、道府県議選挙、市区町村長選挙、市区町村議選挙に対して、その地域に住んでいる人がどれほど関心を持ったかを尋ねた結果についてまとめています。前回と比べ、全般的に選挙への関心が下がっています。
-
道府県議選に関しては、「非常に関心をもった」が14.9%(前回は21.0%)、「多少は関心をもった」が45.4%(前回は47.5%)、合計60.3%(前回は68.5%)で他の選挙に比べて低く、逆に「ほとんど関心を持たなかった」、「全く関心を持たなかった」という回答が他の選挙に比べて多い。前回に比べると、全般的に選挙への関心度は低下している。
投票と棄権の割合
社会的属性による相違
調査結果の概要「4 投票―棄権の選択 (1)社会的属性による相違」では、道府県議選を対象に、性年代、学歴、職業など社会的属性が投票・投票棄権にどれだけ影響があるかに触れており、男女や年代、職業ごとに、「投票した」「投票しなかった」の割合を出しています。 選挙のたびに指摘されているように、年代が上がるにつれ「投票した」と答える「投票傾向」が高くなっています。 なお、調査への回答で「投票した」と答えた割合は、実際の投票率と比較すると高く出る傾向があるため、この報告では「投票した」と答えた割合を「投票傾向」と呼んでいます。
-
①年代別
まず、年代別の投票傾向を見ると(図7)、20歳代の投票傾向が最も低く(51.7%)、年齢が上昇するに従って投票傾向も上昇し70歳代でピーク(85.0%)を迎える。
社会・政治意識の影響
調査結果の概要「4 投票―棄権の選択 (2)社会・政治意識の影響」では、生活満足度、政治への満足度、投票を義務と考えているかなどの社会・政治意識が、投票・棄権の選択にどれくらい影響しているかを表しています。前回と比べて、政治満足度が大きく下がっていることがグラフからよくわかります。
なお、政治満足度が高い人は投票傾向が強く、その次に不満足な人、もっとも投票傾向が低いのは「どちらでもない」を選んだ人でした。
-
②政治満足度
続いて、「あなたは、現在の政治に対してどの程度満足していますか」という政治満足度に関する質問をしている。これまでの回答に比べると、「だいたい満足している」、「どちらでもない」が大きく減少している。逆に「大いに不満足である」がこれまでの10%台から33.7%へと大きく増加しており、「やや不満足である」を含めると、政治への不満足派は76.2%に上る(図14)
支持政党の有無と投票行動
調査結果の概要「5 政党支持と投票行動」では、支持政党の有無がどれだけ投票行動に影響があったかについてまとめています。以下に引用したのは、「投票した」人に対して、「候補者個人」「政党関係」どちらを重視して投票したかを尋ねた結果です。投票の際に「政党関係」を重視する人の割合は年々増えていっています。
資料では、この前の設問で「各政党への支持」を聞いています。それによると、政党自体への支持率は減り、支持政党なしが増加しているにも関わらず、投票の際に「政党関係」を重視する割合が増えているのは興味深い傾向です。
-
「候補者個人を重くみて」と回答した人は回を重ねるごとに減少し、逆に「政党関係を重くみて」と回答した人は増加している。特に今回は増減の幅が大きく、「候補者個人を重くみて」は前回より14.4ポイント減少して49.5%となり初めて 5 割を切った。一方、「政党関係を重く見て」は前回より12.7ポイント増加して37.0%となった。
有権者が選挙時に考慮した政策課題
調査結果の概要「7 選挙で考慮した政策課題」は、投票の際に重視した政策課題についての項目です。以下は、年代別に見た政策課題の表です。20~30歳代は「景気・雇用」「税金」、60歳以上は「高齢化」「医療・介護」など、それぞれ自身の生活に直結する政策課題を選んでいる様子がうかがえます。
-
本調査では、知事選、道府県議選に投票した人に「○○選挙で、あなたはどのような問題を考慮しましたか」と質問し、21項目から当てはまるもの全てを選択してもらった。
これを20~30歳代、40~50歳代、60歳以上と年代別に見たのが表9の(1)及び(2)である。
(1)の知事選を見てみると、20~30歳代で最も選択率が高いのは「景気・雇用」、次いで「税金」、「教育」と続く。中年層である40~50歳代では同じく「景気・雇用」が最も高く、「医療・介護」、「税金」と続く。60歳以上の高年層ではこれらと異なり、「高齢化」が第1位で、次いで「医療・介護」「年金」と続いており、20~30歳代及び40~50歳代で第1位だった「景気・雇用」は第4位に後退している。
(2)の道府県議選においては、20~30歳代、40~50歳代の上位3位までは知事選と同じである。60歳以上は1位と2位が知事選と逆になっている。
見聞きした選挙情報と、役に立った情報
選挙報道とインターネット
調査結果の概要「8 選挙関連情報への接触度と有効度 (1)選挙報道等」では、今回の選挙で投票日以前に見聞きした報道について聞いています。テレビ、新聞の順に接触数が多いですが、同時に「役に立ったかどうか」も聞いており、その結果として新聞と答える割合のほうが多かったようです。20~30代のインターネットの選挙関係情報についても触れられています。
-
結果は、図24のとおりで、選挙報道への接触については、テレビの55.2%、次いで新聞の53.2%が多い。それ以外の媒体については、ラジオが8.5%、インターネットが5.9%、週刊誌・雑誌が2.8%で、テレビ、新聞に比べるとかなり少ない。
それらの媒体から得られた情報が役に立ったかどうかについては、新聞とテレビが逆転し、新聞が39.5%で最も高く、テレビの32.7%が続く。新聞、テレビ以外の媒体は接触度が低いので、「役に立った」という回答も少ない。
-
「インターネット上の選挙関係情報」について、インターネットという媒体が他の年代層に比して、若年層に多く利用されているため、20~30歳代に絞りその接触状況等をみた(図25)。 全体と比較すると倍以上の接触があり、かつ「役に立った」という回答が多い。
候補者の人物や政見がよくわからない
調査結果の概要「8 選挙関連情報への接触度と有効度 (5)候補者情報の不足」は、「地方選挙で『候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る』という声があります。最近の地方選挙で、あなたは、そうお感じになったことがありますか」と尋ねた結果です。 候補者の情報不足を感じている有権者の割合は増加傾向にあり、今回初めて50%を超えました。
-
本調査では、過去の調査と同様に、候補者に関する情報が不足していると感じているかどうかについて「地方選挙で『候補者の人物や政見がよくわからないために、誰に投票したらよいか決めるのに困る』という声があります。最近の地方選挙で、あなたは、そうお感じになったことがありますか」と尋ねている。この質問に、感じたことが「ある」と答えた回答者の割合を、過去と比較できるようにしたのが図27である。
この図からわかるように、候補者情報の不足を認識している有権者の数は、増加傾向にある。第9回統一選(昭54)から第12回統一選(平3)までは、その割合が30%台の前半であったのが、第13回統一選(平7)から40%を超え、今回の統一選では50.1%と半数を超えた。地方選挙における候補者情報の不足は大きな問題となってきている。
上の質問で感じたことが「ある」と答えた50.1%の回答者に、そう感じたのは「どの選挙でしたか」と尋ねたところ(複数回答可)、道府県議選が最も多くて65.1%、次いで市区町村議選48.1%、知事選36.2%、市区町村長選32.2%であった。
政治に対する評価
調査結果の概要「10 国と地方の政治の評価」は、国や都道府県、市区町村など地方政治への有権者の評価を尋ねた項目です。それぞれ「非常によい」「まあよい」「あまりよくない」「非常に悪い」「どちらともいえない」の5つから選択してもらい、「非常によい」「まあよい」の肯定的評価を合計したのが以下になります。バブル期以降、政治への評価は全体的に下がり、第15回から16回に当たる2000年代中頃に良化しました。今回も、地方政治は評価が高まりましたが、日本政治への評価は初めて10%を割り込むことになりました。
-
図30からは次のようなことが読み取れる。第一に、調査開始以来一貫して「日本の政治」より「都道府県の政治」の方が、また「都道府県の政治」より「市区町村の政治」の方がより評価が高い。第二に、「都道府県の政冶」及び「市区町村の政冶」に対する評価は前回に引き続き上がったが、「日本の政治」に対する評価は大きく下落して1割を切り、過去最低となった。第4章で見た政冶満足度の調査で不満足派が急増したのは、「国の政冶」に対する不満が急増したからと解せられる。
議員に望む役割とは
調査結果の概要「11 議員の役割」は、「県(都道府)議会議員」「市(町村)議会議員」に対し、有権者がどのような役割を望んでいるかを7つの選択肢から選んだもので、今回、初めて行った調査項目とのことです。
-
今回の調査では、初めて、全調査対象者に対して「県(都道府)議会議員に対してどのような役割を望まれていますか」「市(町村)議会議員に対してどのような役割を望まれていますか」という二つの質問をし、7つの選択肢から一つだけ選んでもらった。
その結果をまとめたのが図31である。
これによると、都道府県議会議員、市区町村議会議員ともに、「地域の発展を考える」が最も多く、次いで「県・市全体の将来を考える」、「地域の面倒をこまめにみる」の順になっている。「地域の発展を考える」という役割は市議会議員よりも県議会議員により多く期待されており、逆に「地域の面倒をこまめにみる」という役割は県議会議員よりも市議会議員により多く期待されている。
選挙ピックアップ 一覧
- 統一地方選挙全国意識調査(明推協)(2012/02/22)